
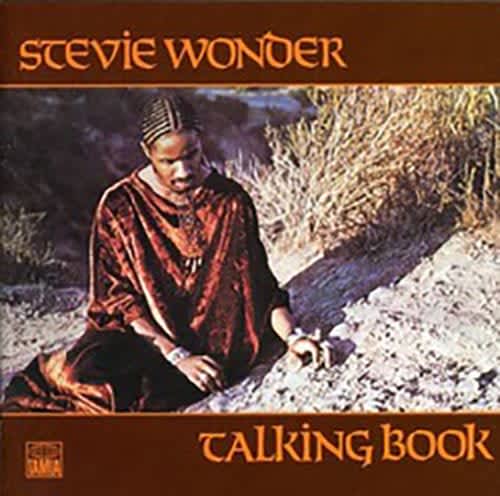
ジェフ・ベックの訃報があってからだいぶ日が経った。でも、今もなおSNS上には唐突に天空に旅立ってしまったギターヒーローを惜しむ書き込みが途絶えない。彼の追悼号のような体裁の雑誌、ムックが書店に並び出したタイミングなので、彼を偲ぶ声はまだ当分続くだろう。このコラムでも彼が亡くなった際には追悼を兼ねたアルバム紹介を書かせていただいたわけだが、その際に過去のアルバムをおさらいしたせいか、今も何かの拍子に彼のギターが脳内に鳴ることがある。簡単に忘れられる人ではない。それで、本人のアルバムではないけれど、彼もセッションで参加したスティーヴィ・ワンダーの『トーキング・ブック』も聴き直し、取り上げておきたいと思った次第です。なお、スティーヴィの名作『キー・オブ・ライフ』に焦点を当てたコラムも以前のこの連載にありますので、ぜひ併せてご覧ください。
通算15作目となる、 黄金期の幕開けを告げる意欲作
本作はスティーヴィ・ワンダー3部作と言われることになる黄金期を飾る作品のひとつで、シンガーとしてだけでなく、コンポーザー、演奏者として、いよいよその才能の全てを示し始める、才人スティーヴィの代表作となったアルバムだ。何せ若干11歳でモータウンと契約を結び、本作が出た時点ですでに10枚を越えるアルバムのリリースを重ねてきていて、充分にベテランだった“リトル”スティーヴィ・ワンダー。さすがに、60年代も末ともなれば、それまで「モータウンの秘蔵っ子」というか、どことなくアイドル路線みたいな扱い、売られ方をされていたスティーヴィの姿は微塵もない。すでにR&B;界を代表する“アーティスト”のひとりなのであり、ほぼ全ての曲を自分で書き下ろすようになり、稀に取り上げるカバー曲も月並みなヒット狙いからではなく、スティーヴィのこだわりで選ばれ、独自のアレンジが凝らされるようになっている。そしてプロデュースも自身で行なう。時にスティーヴィ、若干22歳、という年齢なわけなのだが…。
70年代ともなれば、音楽もまた混然としてくる。民衆に根付くフォークミュージック、新しいアイデンティティーを生み出すことにもなったロックの台頭、スライやJBによるファンク革命、シンガーソングライターの内省的な歌、ジャズに接近したニューソウル、ブラジル音楽、ラテンのリズム…と、あらゆる音楽があふれ、それら全てがスティーヴィを刺激し、彼の身体の中を通過することで、新しい音楽が生まれようとしていた。
ソウル・ミュージックに シンセサイザーを導入する先駆的な試み
そのひとつとして、スティーヴィは、前作となる『ミュージック・オブ・マイ・マインド』からシンセサイザーを取り入れたプログレッシブなサウンドアプローチを試みるのである。そして、コラボレーションとして、レコーディングに招いたのがトントズ・エクスパンディング・ヘッド・バンド(Tonto’s Expanding Head Band)だった。略してトントズ(Tonto’s)=T.O.N.T.O. synthesizerはマルコム・セシルとロバート・マーグーレフからなるシンセサイザー音楽のデュオで、ミュージシャンというよりは研究者っぽい人たちで、本作ではシンセのプログラム、エンジニアとして関わっている。1971年にアルバムデビューしてから何枚もアルバムを残し、1996年頃まで活動している。スティーヴィとのコラボは『ミュージック・オブ・マイ・マインド」(‘72)に始まって、『カンバセーション・ピース』(’95)まで、トータル6作と長きに渡って関わることになる。また、スティーヴィ以外にもアイズレー・ブラザーズ、ランディ・ニューマン、ラヴィ・シャンカール、ウェザー・リポート他、ジャンルをまたぎ、多くのアーティストとも仕事をしている。
アルバムを聴くとしよう。温かなエレピのイントロに導かれて「サンシャイン(原題:You’re The Sunshine Of My Life)」でアルバムは始まる。聴く人全てを幸福な気持ちにしてくれそうな、スティーヴィの代表曲のひとつ。本当に最愛の人がいたなら、この曲のシングル盤をプレゼントしたくなるような曲だ。バックコーラス、スティーヴィのヴォーカルも温かくて素晴らしい。唯一、後半で入ってくるパーカッションのリズムが個人的にはうるさく感じられるのだが、スティーヴィがOKなら文句は言えない。
本作は複数のギタリストを贅沢に使っていることでも知られるが、2曲目の「メイビー・ユア・ベイビー」ではレイ・パーカーJrがギターで参加し、渋いソロを弾いている。バックで鳴っているスティーヴィが弾くクラヴィネットもファンキーだ。
打って変わって3曲目「ユー・アンド・アイ」はスティーヴィのピアノの弾き語りをベースに、効果音的に使うシンセが幾重にも織りなすサウンドが夢幻的な雰囲気を作り出す、実に美しいスローバラードである。ヴォーカリスト、スティーヴィの魅力も全開という珠玉の一曲。これがスティーヴィとTonto’sによるシンセだけで録音しているのだが、シンセにありがちな空疎感、冷たさもまったく感じさせないところも実に驚きである。
4曲目は「チューズデイ・ハートブレイク」。アップテンポに乗せ、ワウワウを効かせたファンキーなギターを弾いているのはバジー・フェイトン(Buzzy Feiten)だろうか。元はポール・バターフィールド・ブルースバンド出身で、その後、フルムーンというフュージョンバンド、キーボードのニール・ラーセンとのコラボ等で活躍する人だが、前作「ミュージック・オブ・マイ・マインド」(‘72)からスティーヴィのアルバムに参加している。また、フェイトンと前述の ポール・バターフィールド・ブルースバンドのバンドメイトだったアルト・サックスのデイヴィッド・サンボーンがこの曲に参加しているが、この段階ではまだサンボーンはまったく無名だったのだそうだ。
5曲目「バッド・ガール」もシンセ、キーボードをうまく使った曲だ。ベースになっているのはフェンダーローズとおぼしきサウンドで、そこにムーグシンセサイザー等を織り交ぜている。今の耳で聴くとナチュラルなものだが、当時は斬新なアンサンブルだったのだろう。オリジナルが出るなり、ハービー・ハンコックがカバーするなど、ジャズ系ミュージシャンによく取り上げられているそうだ。
ジェフ・ベックとの 友情の証として書かれた「迷信」
そして、6曲目が「迷信(原題:Superstition)」である。この曲はジェフ・ベックとのいわくつきの曲であるので、少し触れておきたい。アルバムが完成するとモータウン側はアルバムからの第一弾シングルを「迷信」にすると決定する。これにスティーヴィは抵抗し、本来はジェフ・ベックのために書いた曲で、彼は自分のバンド(ベック・ボガート&アピス)のシングルで出す予定で録音も済ませている。自分が先に出したのではジェフを裏切る行為になる、と。しかし、スティーヴィの主張は通らず、ベックより1年先に「迷信」はリリースされ、ヒットを記録する。当時ジェフは激怒したと報じる記事もあるが、真相は「まぁ仕方ないさ」と、和やかなものだったのではないか。
後年、ふたりの共演シーンを見ると、厚く結ばれた友情は壊れることはなかったと確信する。ジェフも予定通りベック・ボガート&アピスのアルバムに同曲は収録され、シングル・カットされるや人気曲になり、また同曲はジェフのキャリアの代表曲のひとつにもなったのだから、まぁ結果オーライだったのではないか。
ただ、スティーヴィにすれば当時、ジェフに申し訳ない気持ちを抱えていたようだ。そして、彼は改めてジェフに曲を贈る。それがジェフの1975年のソロ作『ブロウ・バイ・ブロウ』 に収められるギターインストの名曲「哀しみの恋人たち(原題:Cause We’ve Ended as Lovers)」だったというわけである。
※なお、この曲でも実はジェフは弾いたという証言もある。クレジットにないところを見ると、先のモータウン側との行き違いで、ジェフのトラックが外された可能性もなくはない。だとすれば惜しい…どころか愚行だ。
スティーヴィのアルバムに戻ろう。7曲目「ビッグ・ブラザー」は珍しくアコースティックギターが聴こえる…と思ったら、これもクラヴィネットをギター風に演奏しているみたいなのだ。少しフォーキーさを漂わせたこの曲は人種差別に対する辛辣なメッセージソングになっているのだが、それと感じさせない爽やかなサウンドはスティーヴィのハーモニカによるところも大きい。この曲もほぼスティーヴィひとりで演奏しているらしい。
8曲目「ブレイム・イット・オン・ザ・サン」もなかなかの名曲だ。スティーヴィの歌のうまさにハートを掴まれる。ドラム、ベースが生み出すグルーヴ感も素晴らしい。そこにTonto’sがプログラミングしたシンセが生み出す独特のサウンドが相乗効果となって彩りを加えている。
短くも美しい、息を止めて 聴き入ってしまいそうなジェフのソロ
9曲目「アナザー・ピュア・ラヴ」でジェフとバジー・フェイトンがギターを弾いている。リードを取っているのがジェフで、バッキング的に弾いてるのがフェイトンか。これはジェフの数ある客演の中でも珠玉の一曲だろうと思う。ソロ自体は短く、物足りないくらいだ。でも、あくまで歌を立てるジェフはそのさじ加減をわきまえた尺で決して弾きすぎない。時にジェフ・ベック28歳。結構な経験を積んできているとはいえ、そのほとんどはロック畑を歩んできたのであり、普通ならその方面にありがちな、はやる気持ちが勝るあまり、グイグイ弾いてしまいそうなものだのに。ジェフはグッと音数を絞って弾く。絶妙なチョーキングの間合いに、彼の天才的なうまさが出ている。くどいほど言うが、この、粋も甘いも噛み分けたようなクリーントーンのソロは本当に見事だ。
10曲目、アルバムのエンディングを飾るのが「アイ・ビリーヴ」という美しい曲で、これまたキーボードからドラムまでスティーヴィがひとりで録音している。正式なタイトルフレーズ《I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever) 》がリフレインされながら歌われ、盛り上がるドラマチックな曲で、アルバムを締めるのに相応しいスケール感がある。美しいギターのアルペジオ風の…と思いきや、これもクラヴィネットをギター風に弾いている。他の曲でも聴かれるそのセンスに脱帽なのだが、一方で疑念が湧いてくる。別にギターのパートならシンセ、クラヴィネットではなくギターで弾けばいいじゃないかと。で、「迷信」のところで書いたが実はオリジナルのマスターテープにはジェフのギターのトラックが入っていたりするんじゃないのか? 揉めたのが原因でそのトラックは没になり、スティーヴィ自らクラヴィネットでそのプレイをトレースした? 根拠なく詮索するのは無意味なことなのかもしれないが、つい思ってしまうのは私だけだろうか。
話を本作がいかに意欲作であったかという部分に戻すと、やはりT.O.N.T.O. synthesizerとの関わりが大きいだろう。シンセサイザーは当時、まだ新進の楽器で、それを使うのはEL&P;(エマーソン・レイク&パーマー)に代表されるロックの人たちが、一種飛び道具的に使うものだった。スティーヴィたちも、まだまだシンセをどのように使えばいいのか模索している段階だったと思う。それでも彼は独特の感覚、センスでもって、まやかしでもなく、流行りモノというわけでもなく、この機械を楽器として使いこなしている。変わった音色、キワモノ的な刺激音、人の手では弾けないようなフレージングが可能だと分かれば、「どうだ!」とばかりに試してみたくなりそうなものだが、そんなのはロックの連中にやらせとけばいいということだったのだろう。このアルバムでも聴かれる、それまでのソウルミュージックにはないシュールなサウンド、テイストとR&B;の融合は80年代に隆盛を極めるブラックコンテンポラリー(Black Contemporary)の扉を開けたと言えるのかもしれない。
アルバム『トーキング・ブック』は全米チャートで3位にまで上るヒットを記録している(全英でも16位と健闘)。休む間もなくスティーヴィはT.O.N.T.O. synthesizerとともに次作『インナーヴィジョン』、さらに『ファースト・フィナーレ』の制作に挑んでいく。
TEXT:片山 明
アルバム『Talking Book』
1972年発表作品
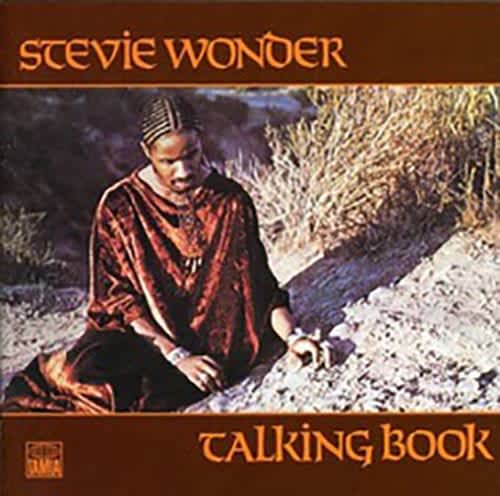
<収録曲>
1. サンシャイン/You Are the Sunshine of My Life
2. メイビー・ユア・ベイビー/Maybe Your Baby
3. ユー・アンド・アイ/You and I (We Can Conquer the World)
4. チューズデイ・ハートブレイク/Tuesday Heartbreak
5. バッド・ガール/You've Got It Bad Girl
6. 迷信/Superstition
7. ビッグ・ブラザー/Big Brother
8. ブレイム・イット・オン・ザ・サン/Blame It on the Sun
9. アナザー・ピュア・ラヴ/Lookin' for Another Pure Love
10. アイ・ビリーヴ/I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever)

