
「文学フリマ」をご存じだろうか?
2002年に始まった文学作品の展示即売会で、出店者が「文学」だと思うものであれば自由に販売できる。新型コロナウイルス禍で中止の憂き目にも遭ったが、来場者数はV字回復。開催地域も広がり、22年には出店者から芥川賞作家も出た。20周年を迎え、かつてない活況を呈している。
02年に大学に入学し文学サークルに入会した私は、第1回の文学フリマに先輩や友人らと出店した。その後、いろいろあって記者となり、地方勤務を挟んでご無沙汰していたが、どんな因果か文芸担当として東京で働くように。果たして文学フリマはどのように変化しているのか―。関係者を取材し、かつての仲間たちに声をかけ久々に出店もしてみることにした。(共同通信=鈴木沙巴良)
▽「笑い事じゃねえんだよ!」凍りつく会場
まず、文学フリマが始まった経緯を振り返っておきたい。
発端となったのは、批評家の大塚英志さんが文芸誌「群像」(02年6月号)に発表した評論「不良債権としての『文学』」だ。その中で大塚さんは、出版市場が縮小してそれまでの「文学」が持続不可能になっていると指摘し、その「対症療法」の一つとして、既存の流通システムの外側に市場をつくる試みを提案した。漫画などの同人誌即売会「コミックマーケット」に倣ったものだ。
開催に前後して、文芸界隈では新たな雑誌がいくつも創刊された。大塚さんと批評家の東浩紀さんが責任編集を務めた「新現実」、文芸評論家の福田和也さんや作家の重松清さんらが編集同人となった「en―taxi」、ジャンル横断をうたった「重力」―。それぞれカラーは異なれど、背景にはやはり文学作品が売れなくなっている状況への危機感があったように思う。
そんな雰囲気は、大学の文学サークルに所属していた私たちも感じていたようだ。サークルでは毎年秋に講演会を開催していたが、この年のテーマは「出版不況」だったと記憶している(講演者はライターの永江朗さんら3人)。年に1回出していた同人誌に加え、会員による書評などを載せたコピー本を新たに作り、文学フリマに参加したのは自然な流れだった。

02年11月3日、第1回文学フリマが開催された。会場となった青山ブックセンター(東京都渋谷区)のイベントスペースは、多くの人でにぎわっていた。特に来場者が集まっていたのが、講談社の編集者だった太田克史さん、作家の佐藤友哉さん、西尾維新さん、舞城王太郎さんが執筆陣に名を連ねた「タンデムローターの方法論」のブース。今で言う“推し”の作家にサインしてもらったと喜ぶ先輩の、ほくほくとした笑顔が忘れられない。ちなみに、この日の成功が後に雑誌「ファウスト」の創刊につながり、一世を風靡する。
もう一つ、よく覚えているエピソードがある。午後に大塚さんと文芸評論家の鎌田哲哉さんらの討論会が催されたのだが、主催者である大塚さんが会の開催に当たってテロも懸念したという趣旨の発言をすると、聴衆からクスクスと笑い声が漏れた。「まさかテロなんて」という反応だったと思うが、大塚さんが間髪入れず「笑い事じゃねえんだよ!」とほえ、会場が凍りついた―。そんな記憶だ。第1回文学フリマは和気あいあいとしながらも、どこかに緊張感があった。
▽芥川賞・高瀬隼子さんは2011年から出店
初回は大塚さんらが主催した文学フリマだが、第2回以降は有志が引き継ぎ運営してきた。
「こんなに拡大するとは想定していなかった」と話すのは、第2回から事務局代表を務める望月倫彦さん。約70の出店、約千人の来場者で始まった文学フリマは当初、イベントの規模としては決して大きくなかった。「地に足を着けていこう、独自の参加者をつかもうとやっていた」。文芸誌への広告やプレスリリースは出したが、他のイベントでの広報活動はせず、口コミを大事にした。「文学フリマの中核は来場者」と強調する。
初期は小説や評論の出店が多かった。08年には、東さんによる批評家の発見&育成プロジェクト「ゼロアカ道場」の一環として、“門下生”らが同人誌を販売。東日本大震災のあった11年には、「早稲田文学」の主催で川上未映子さんや中村文則さんら著名作家が集まってチャリティーサイン会を行った。その際に客として来場した又吉直樹さんがとある編集者と知り合い、後に芥川賞を受賞する「火花」の依頼につながったという。
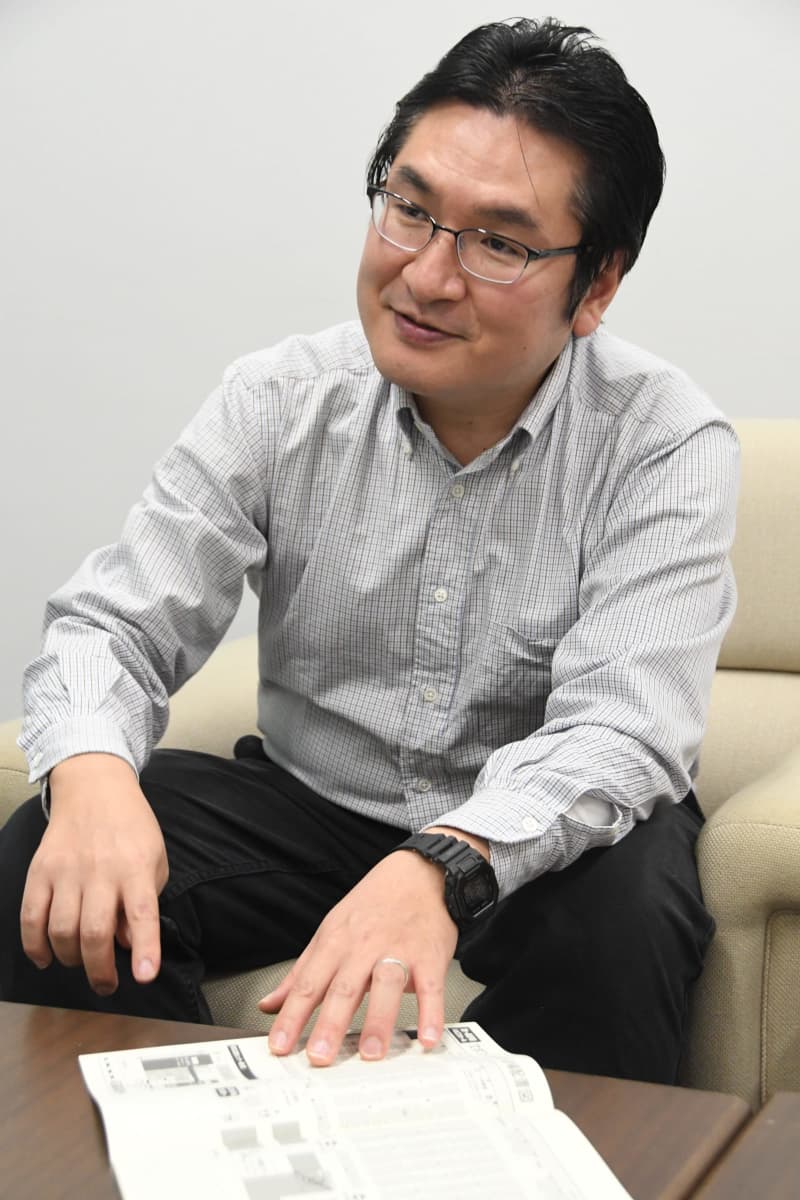
開催を重ねるごとに出店数や来場者数は増えていった。もともと仲間内で同人誌を作る文化があった短歌などの愛好者も参入。近年は、交流サイト(SNS)での情報拡散を出店者に呼びかけ、その効果も出ているという。19年11月には出店数が約千、来場者数は約6千人に達した。
しかし、翌年に新型コロナウイルス禍が直撃。20年5月の東京開催が中止されるなど、大きな影響が出た。それでも、文学フリマは立ち直り、来場者数はV字回復していく。背景に、多地域への広がりがあったと望月さんは言う。10年代に各地で有志を支援する取り組み「文学フリマ百都市構想」を始め、これまで11都道府県で開催。コロナ禍によりある地域で中止を余儀なくされても、別の都市では開けるなど「存在感が途切れなかった」。20周年となった22年11月の東京開催では、出店数1300超、来場者数約7400人となり、過去最多を記録する。
「活字になるのがすごくうれしかった。お客さんに『前回読みました』って言われたりして、励みになりました」。そう語るのは、作家の高瀬隼子さん。大学時代のサークル仲間たちと同人誌を作り、11年から出店を続けてきた。同人誌には、文芸誌の新人賞に投稿した落選作を掲載。「本の形になって存在してほしいと、供養のつもりでした」。執筆を続け、19年にすばる文学賞を受賞して作家デビュー、22年夏には芥川賞を射止めた。「文学フリマはお祭りみたいで、やる気を楽しく引き出してくれました」と感謝する。今後も参加するつもりだ。
望月さんは高瀬さんの芥川賞受賞について「とうとう出たなという感じ」。文学分野の商業出版が細る中、書き手や読み手を育てられる文学フリマは存在感を増していると指摘する。「『日本の文学は文学フリマで変わった』と言われるようになることを目指しています」

▽大学時代の仲間に声をかけてみると…
そんな文学フリマにほぼ20年ぶりに参加しようと思い立ったのは、22年夏のことだった。果たしてどんな反応が返ってくるか―。大学時代に所属していた文学サークルの仲間たちにこわごわ声をかけてみると、「なんか面白そう」などと前向きな返答が続々寄せられ、ホッとした。
好反応に気をよくして会合を企画したが、集まったのは3人だけ。そう、コロナの第7波の影響だ。特に小さい子どもを持つ人たちは感染を恐れて参加できない。オンラインの時代なのである。
そんなわけで、参加希望者でLINE(ライン)のグループを作成し、情報交換の場とするとともに、必要があればビデオ会議を開くことにした。メンバーの住む地域はバラバラだから、とても便利だ。20年前に部室に集まって作業していた頃とは、時代も環境も大きく違う。
同人誌のテーマをどうするか、会議で話し合う中で浮上したのも、20年という時間の経過に伴う変化だった。「文学」で結び付いていた(はずの)当時の自分たちが今の世界を見たらどう思うのか―。そんなテーマを決め、表現方法には縛りを設けず、作品を募ることにした。営業職や編集者、大学教員、記者など、今やさまざまな職に就く11人が原稿を執筆。装丁は本などのデザインの仕事をしている先輩が担当してくれることに。
私は、かつてトルコを旅行中にハサンケイフという町で出合った猫との思い出を、フィクションを交えて書こうと決めた。15年以上が経過しても、あれは一体何だったのか消化できておらず、何らかの形で文章にしてみたいと思ったのだ。
学生時代のように時間に余裕があるわけではないが、11月の文学フリマを目指して夜に会議を繰り返し、休日に原稿を書いた。負担と言えば負担なのかもしれない。でも、仕事の文章とは異なる自由な文章を書き、一冊の本の形が見えてくる経験はワクワクした。何よりも、ゲラとして上がってきたみんなの作品を読むのは楽しく、ついつい明け方まで読みふけってしまった。同人誌作り、面白いじゃないか。
そして、11月20日、文学フリマが開催される日がやって来た。サークル名「戸惑い文学会」、冊子名「みどりシャッポのひと」。会場に設置されたブースに行けば、印刷所から同人誌が届いているはずだ。自分たちの言葉は、果たして誰かに届くのだろうか。胸を高鳴らせて、家を後にした。(後編に続く)
https://nordot.app/1006116100743364608?c=39546741839462401

