
2022年はナチス・ドイツの親衛隊中佐、アドルフ・アイヒマンの死刑執行から60年という節目の年だった。1961~62年にイスラエルで開かれた裁判では、ホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)生存者が初めて公の場で経験を語り、その残虐さは衝撃を与えた。
傍聴したユダヤ系哲学者ハンナ・アーレントは「悪の陳腐さ」という表現で組織の命令に服従するだけの役人としてアイヒマンを描き、人口に膾炙した。
だが、イスラエルではむしろ、虐殺の生々しさが国民に伝わり「ホロコーストとは何だったのか」が理解され始めるきっかけとなった点で意味を持つ。ラジオや新聞を通じ多くの市民が実態を知り、ホロコーストは「ユダヤ民族共通の記憶」に昇華した。同時に、政府や軍だけでなく、社会全体が共有するイスラエルの強固な国防意識やナショナリズムの源流にもなった。(共同通信=平野雄吾)
▽さげすみ
「イスラエル建国後、われわれは二つの戦線で戦った。一つはアラブ諸国との戦いで、もうひとつはホロコースト生存者へのさげすみだった」。イスラエル軍元幹部ヨシ・ペレド氏(82)は当時の社会をそう表現する。ベルギー北部アントワープで1941年、ユダヤ人家庭に生まれたが、迫害を逃れるため、生後6カ月でキリスト教徒家庭に預けられた。両親はアウシュビッツ強制収容所(ポーランド)へ送られ、父は死亡、母は生還しペレド氏の前に現れた。

「自宅の庭で遊んでいると、小さな暗い雰囲気の女性が現れた。(キリスト教徒家庭の)父が私を呼んで言った。『実は私たちはおまえの本当の両親ではない』」。ペレド氏は当時8歳。「空が頭の上に落ちてきたような衝撃だった」
ペレド氏はキリスト教徒家庭を離れたが、生みの母は体調が優れず育てられなかったため、移住をあっせんするユダヤ機関に預けられ1950年、イスラエルへと渡った。
建国間もないイスラエルでは、第1次中東戦争が休戦に至ったばかりで治安も安定せず、社会は「力強さ」を求めていた。「なぜ抵抗しなかったのか」「なぜ羊のように従順に殺されたのか」―。ホロコーストはユダヤ人の「弱さの象徴」とされ、さげすまれた。「(中東戦争で)エジプト軍の進軍を止めた兵士の息子が英雄視される中で、自分の父がアウシュビッツで死亡したとは言えなかった。私は過去を封印した」とペレド氏は言う。「1961年に始まったアイヒマン裁判を機に、社会がホロコースト生存者の話に耳を傾けるようになった」

▽証言
対外特務機関モサドは1960年5月、潜伏先のアルゼンチンでアイヒマンを拘束し、イスラエルへと拉致した。ベングリオン首相(当時)の狙いは公開の場で裁くことだった。
アイヒマンの拘束劇を描いた映画「オペレーション・フィナーレ」(2018年、クリス・ワイツ監督)で時代考証などを担当したモサド元諜報員アブネル・アブラハム氏は「モサドは当時、アウシュビッツで人体実験を繰り返した医師ヨーゼフ・メンゲレの潜伏先も突き止めていたが、拘束の許可は出なかった」と指摘する。
「ベングリオンの目的は裁判を通じホロコーストの全体像を浮き彫りにすること。ユダヤ人を収容所へ送る輸送責任者で、全収容所と連携していたアイヒマンは好都合な見せしめだった」

アイヒマンを裁くだけなら、証拠書類だけで十分だが、主任検察官ギデオン・ハウスナー(1990年死亡)は生存者に裁判でその体験を証言させた。大惨事を生々しく再現しホロコーストを知らない若い世代への教育的な意味合いもあった。
ハウスナーの長女で、弁護士のタマル・ハウスナー・ラベ氏(77)は「父が自宅に生存者を招き、母のクッキーでもてなしながら証言するよう説得していた。あまりに残酷な話のため、生存者は誰も自分の話を信じないと思っていて語りたがらなかった」と振り返る。
森に連行され、地面を掘るように命令される女性。男児を抱える女性に銃を持った兵士が言った。「どっちが先に撃たれたいんだ? おまえか? 赤ん坊か?」。穴の前に並ばされた無数のユダヤ人が次々と撃たれていった。みな死亡したが、女性は助かり、夜になって穴からはい出た―。
「父がリビングで生存者と話をしているとき、私は追い出されたが、廊下でドアに耳を当てて話を聞いた」。10代のタマル氏に強烈な記憶を焼き付けた生存者女性の経験談。「怖くなり、しばらく夜寝られなくなった」

▽アイデンティティー
裁判は1961年4月、劇場を改造したエルサレムの特別法廷で始まった。「シナゴーグ(ユダヤ教会堂)に集められ、みんな撃たれた」「妻と子の遺体を溝に投げ込んだ」―。生存者約120人が証言した。涙を流すほか、気絶する証言者もいた。
イスラエル紙ハーレツの元記者で、歴史家のトム・セゲブ氏(78)は16歳のとき、法廷近くの修道院に設置されたスクリーンで裁判を傍聴した。
「検察官は劇的に話を展開した。傍聴席には涙を流す人や『そんな話は信じられない』といった具合に、開いた口を手で覆っている人もいた」
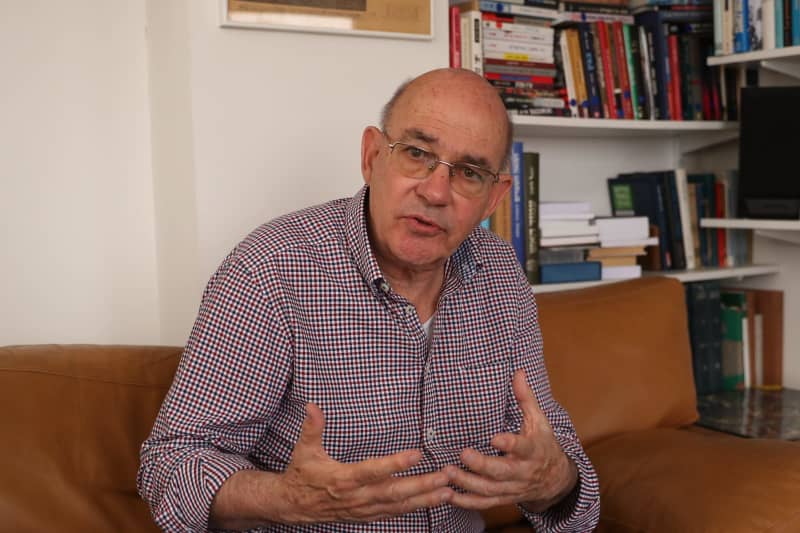
裁判のクライマックスはアウシュビッツを生き延びた作家イェヒエル・デヌール氏の証言だ。
「住民は生きているのでも死んでいるのでもありません。数字が名前でした。数字が消えていった。次々と周囲の数字が消えていったのに私はいつも後回しになり、見送るばかりでした」
そう語り気を失ったデヌール氏。ざわつく法廷。「静粛に」と繰り返す裁判官。気絶の瞬間は映像に収められ、多くの市民に共有されるアイヒマン裁判の象徴になった。

生存者取材や文献調査を実施し「七番目の百万人―イスラエル人とホロコースト」(邦訳は2013年)を著したセゲブ氏は「この瞬間はイスラエル史で最も劇的な瞬間の一つだ」と指摘する。「裁判がイスラエルの民族的カタルシス(浄化)になった」
イスラエル建国後まだ十数年で、国民意識は未熟だった。特にアラブ諸国出身のユダヤ人は欧州出身者中心の社会へうまくなじめない。ベングリオン首相の狙いを「国民意識の統合」とみるセゲブ氏は、「裁判を通じホロコーストはユダヤ民族の記憶として共有され、ナショナルアイデンティティーになった」と強調する。
裁判後、生存者を受け入れる土壌ができ、ホロコーストの教育も広がった。1980年代からは政府が希望する高校生をアウシュビッツの見学に連れて行く学習も始まった。ナショナリズムや国防意識が醸成され、政治家の関連発言も増えていく。
「国家がなかったから虐殺された」「ユダヤ人の避難場所としてイスラエルを守る必要がある」
一方、ナショナリズムや国防意識と表裏一体で、ホロコーストの記憶は恐怖心も植え付けた。セゲブ氏は、欧州諸国のパスポート取得手続きの代行をする弁護士事務所の広告が現在も日刊紙にあふれていると指摘し、「この国の将来に対する不安の表れだ」と話す。
エルサレムで取材していると、パレスチナ自治区ガザへの空爆をはじめ、イスラエルの「やり過ぎ」とも言える攻撃を目にする。国際社会は「過剰防衛だ」と非難するが、イスラエル政府がそうした懸念に耳を傾けることは少ない。
過去の虐殺から生まれる無意識の恐怖心や不安感。その裏返しの強さへの憧憬。イスラエルを理解する一つの鍵がここにあると感じている。
地元記者がこう語ったことがある。「国際社会はホロコーストを防ごうとしなかった。そんな国際社会への不信を抱えるユダヤ人は多い」

▽煙突
1年強続いた裁判で、アイヒマンはユダヤ人を強制収容所へ輸送する事業で中心的役割を担った自らの業務などを巡り、「上の命令に従っただけだ」と無罪を主張した。
アーレントは、組織の方針に服従する役人を「悪の陳腐さ」と表現、「まったく思考していないこと、それが彼があの時代の最大の犯罪者の一人になる素因だった」と強調した。
だが、イスラエルではこの見方は少数派だ。ネゲブ・ベングリオン大のハンナ・ヤブロンカ教授(ホロコースト研究)は「アイヒマンは、単なる陳腐で凡庸な人間ではない」と指摘する。「アーリア人の優越というイデオロギーを徹底して信奉し、自ら率先してユダヤ人問題の最終解決に向け行動していた」

セゲブ氏も「多くのドイツ人はナチスに参加したわけでも、投票したわけでもない」とした上で、「ナチス関係者は、自分たちは正しいことをしていると考えており、イデオロギー的にナチスの犯罪行為に加担していた。その意味では、(誰もがアイヒマンになり得るという)『悪の陳腐さ』という考えは間違っている」と付け加える。
公判中、イスラエル北部ハイファ郊外の刑務所で、アイヒマンの看守責任者を務めた元警察官のルスキー・アルマン氏(88)は「毎朝6時半に目覚まし時計なしに起き、アイヒマンの起床でこちらが時間を認識した。ロボットのようだった」と苦笑する。
「看守は4時間おきに交代し睡眠中も含めてアイヒマンを1人にさせなかった。読書のほか、常に自分や家族について書き物をしていた。部屋にいる蚊やハエの動きを追い、コミュニケーションをとっているようだった」と振り返る。

アイヒマンは1962年5月29日、ユダヤ人に対する罪などで死刑宣告され、その2日後、中部ラムラの刑務所で処刑された。遺体は火葬され、その灰は地中海にまかれた。
火葬炉をつくり、遺体を炉に入れたのは生存者のピンハス・ザクリコウスキー氏(1999年に死亡)。息子のトゥリ・ジブ氏(70)に後年こう話した。
「火葬後の帰り道、刑務所を振り返ると煙突から煙が上がっていた。自分がいたドイツのブーヘンバルト強制収容所がよみがえる寒い朝だった」


