

トム・ヴァーライン(Tom Verlaine)が亡くなった。70年代末に短いながらロックシーンに名を印したバンド、テレヴィジョンを率いたギタリストだった。亡くなったのは1月28日のことで、それから少し日が経ってしまったが、簡単に忘れ去られてしまっては、あまりにも惜しいアーティストのひとりなのであり、このコラムでも取り上げておきたいと思いました。
短命ながら、70年代末のロックシーンに刻み込まれたテレヴィジョンの ギターサウンド
ヴァーラインが率いたバンド、テレヴィジョンは2枚しかアルバムを残さなかった。後年、発掘されたライヴ音源からいくつかのアルバムが作られたり、1992年に再結成されて『Television』というアルバムが制作されているのだが、スタジオ録音としては今回紹介する『マーキー・ムーン(原題:Marquee Moon)』と『アドヴェンチャー(原題:Adventure)』だけと考えてもいいだろう。
『マーキー・ムーン』は1977年、エレクトラレコードから発売された。レコーディングは前年から行なわれていたが、ヴァーラインは納得できるまで執拗にリハーサルを繰り返すという人で、録音作業に辿り着くまで膨大な時間をかけたと言われている。しかも、1974年末に始まったそのレコーディングセッションの最初のプロデュースを担当したブライアン・イーノのサウンドメイクにヴァーラインは難色を示し、タッグは決裂する。今となってはイーノによるテレヴィジョンの録音がどのようなものだったのか。同じニューヨークのインディシーンからデビューしたトーキング・ヘッズがイーノのプロデュースでニューウェイブという枠を超えたバンドへと飛躍しただけに、興味がそそられるのだが、ヴァーラインはレーベルが推す人材を使うよりも、あくまで自分主導で録音したいと考えるタイプだったようだ。いかにも繊細でエキセントリックだったという彼らしいエピソードである。結局、サウンドエンジニアにアンディ・ジョーンズを招き、プロデュースはヴァーライン自身が行なった。
アンディ・ジョーンズという人はプロデューサーとしても超一流の人で、ハンブル・パイやロッド・スチュワート、ヴァン・ヘイレンをはじめ、紙面が尽きてしまうのではないかと思われる膨大なアーティストのアルバム制作を行なうほか、エンジニアとしてもローリング・ストーンズやレッド・ツェッペリン、スティーブ・ミラー、エリック・クラプトン…と、有名どころのアルバムに関わっている。よく新人バンドのテレヴィジョンを手掛ける気になったものだ。
翌年、レコーディングスタジオをアトランティック所有のA&R; Studiosから地元ニューヨクのRecord Plantに移して、翌年リリースされたのがセカンド作『アドヴェンチャー』である。こちらもプロデュースとエンジニアにジョン・ヤンセンを招き、ヴァーラインは共同プロデュースの体制を取っている。ヴァーラインはあまりライヴをやりたがらなかったと聞いたこともあるのだが、楽曲が溜まっていて、アルバム制作の意欲が高まっていたからなのかどうか、『マーキー・ムーン』リリース後、プロモーションを兼ねてのツアーに出ることもなく、彼らはスタジオに入ることを選択したわけだ。こちらはファースト作に比べると、幾分曲想やアルバム全体にある空気感に刺々しさが後退し、曲によってはポップなギターアルバムと感じられるところもある。オープニングの「グローリー」やライヴの定番曲「デイズ」「フォックスホール」、カッコ良いリフが決まる「エイント・ザット・ナッシン」「ザ・ドリームズ・ドリーム」など、よく練られた曲が並び、実はこのセカンド作のほうが好きというリスナーも少なくない。
孤高と呼ぶに相応しい異能のギタリスト
トム・ヴァーラインこと、本名トム・ミラーは1949年ニュージャージー州モリスタウンで生まれている(NYマンハッタンまで小1時間ほどの距離である)。子供の頃から音楽に親しみ、ピアノやサックスなどの楽器にも触れていたようだ。その楽器からもうかがえるように、彼が最初に興味を惹かれた音楽はジャズで、その嗜好は終生続くのだが、彼がティーンエイジャーを過ごした時期は紛れもなくロックンロールが沸き起こった時代であり、その刺激から彼も逃れることはできなかった。その頃、やがてバンドを組むことになるリチャード・レスター・マイヤーズ、後にリチャード・ヘルと名乗ることになる男と知り合っている。意気投合したふたりは学校をドロップアウトし、ニューヨークに移り住み、バンド活動を始めている。それは1968年頃のことだが、残された写真を見ると、気の弱そうなロングヘアーのふたりが所在なげに写っている。そこに、髪の毛をツンツンに立てて、破れTシャツを身にまとい、麻薬常習者のように虚ろな眼光で睨む、後のリチャード・ヘルの片鱗を見出すことは不可能だ。一方のヴァーラインは痩せぎすで神経質そうな風、後のテレヴィジョンやソロ活動時のアルバムジャケットに見られるような佇まいが見られる。写真が撮られた頃というのは前年には『モンタレー・ポップ・フェス』、翌年には『ウッドストック・フェス』が開催されるという時期で、彼らとて例外なくロックの渦に揉まれていたことと思う。その頃から互いに平凡な本名を封印し、トム・ヴァーライン、リチャード・ヘルと名乗り、バンド活動(ネオンボーイズ)と並行して詩作に励んだりしていたという。
※ヴァーライン、ヴァーレーン、ヴァーレイン、どれが正確な発音/表記なのか分からないが、マレルメやランボーと共にフランスに象徴派詩人として名高いポール・ヴェルレーヌから名前の綴りを借りたという話である。
偶然、私の友人にその頃のリチャード・ヘルのポエトリー・リーディングを観たという人物がいる。スティーブ・ディニーノという、当時ロングアイランドシティに住んでいたという彼が言うには「リチャード・ヘルの詩はお世辞にもとても聞けたものじゃなかったよ。およそ文学的なセンスは感じられなかった」と苦笑いしながら「ただ、街角やカフェでやるそのリーディングにはアコギの伴奏がついて、それは不思議な陶酔感を誘うものだった。今思えば、あれはヴァーラインだったのかも」と話してくれたものだ。本職はイラストレーターだと言っていたが、ニューヨークに住んでいた時に一時期週末に版画を学んでいたのが縁で知り合ったスティーブは当時のNYのパンク・ムーブメントをリアルタイムで体験した男で、パティ・スミスやトーキング・ヘッズ、ラモーンズ、ブロンディ、ブライアン・イーノ、ルー・リード、そしてテレヴィジョンのギグなども何度か観たという。
「それから何年かしてテレヴィジョンのライヴを観たんだけど、リチャード・ヘルはもういなかった。彼はヴァーラインと喧嘩別れしてジャンキーのジョニー・サンダースとハートブレイカーズを組んだり、ヴォイドイズを結成してたんだね。ヴォイドイズの詞も酷かったね」と、ことヘルに対しては酷評ばかりだったが、テレヴィジョンのライヴは絶賛していた。「ステージングも独特だった。チューニングがやたら長くてヤキモキさせられたもんだけど、曲が始まるとそんなイライラを忘れさせるほど、演奏はすごかった。1曲の演奏が長くてね、例えは変だけど、ジャムバンドみたいなところがあった。おまけにアルバムと違い、彼らのライヴはすごくアグレッシブだった。ヴァーラインともうひとりのギタリスト、リチャード・ロイドも信じられないくらいギターが上手かったが、ふたりの微妙なギターの絡みはそれまで聴いたことがないスリリングなものだったし、その後も出会わない類の奇跡的なコンビネーションだったと思う。ヴァーラインのプレイはあの時代のNo. 1ギタリストだったんじゃないかな? 誰も言わないけど」と言っていた。
ちなみにスティーブはテレヴィジョンの2作が出たのとほぼ同時期にリリースされたダイヤー・ストレイツのデビュー作『悲しきサルタン(原題:Dire Straits)』(’78)も愛聴していたそうなのだが、片やギタリストとして激賞されていたマーク・ノップラーにひきかえ、まるで話題に上らないヴァーラインの才能に「みんな、もっと知るべきだよ。まぁ、クラプトンやジミー・ペイジは無関心だろうけど。でも、少なくともディランはノップラーではなく、ヴァーラインを起用していたら、もっと面白いアルバムが作れたんじゃないかな?」と言って、暗に低迷期のディランを皮肉っていた。
※ダイヤー・ストレイツを気に入ったディランは自身のアルバム『スロートレイン・カミング』(’79)のセッションにマーク・ノップラーを起用、以降、アルバム、ライヴで競演を続けた。一方、ヴァーラインはと言えば、実はボブ・ディランをモデルにした映画『アイム・ノット・ゼア』(’07)のサントラにギターで参加している。
およそパンクらしくない 音楽性、演奏力の高さ
スティーブがおよそ20年以上前に語ってくれたヴァーライン、テレヴィジョンについての話を思い出しながら、私も初めてテレヴィジョンを聴いた時に、少し困惑させられたことを思い出す。ミュージックシーンを席巻するようなパンク、ニューウェイブ勢力の中にあって、テレヴィジョンの扱いは真打ち登場みたいな感じだった。なにせ、ラモーンズと並んでNYパンクの総本山みたいなライヴハウス「CBGB」の、彼らはメインアクトというべき存在だったからだ。実兄が買ってきたセカンド作の『アドヴェンチャー』のほうを先に私は聴くことになったのだが、とにかくシンプルというか、ほぼエフェクターなど使わず、クリーントーンで弾くギターからは、パンクにありがちなワイルドで粗野、攻撃的な響きはまったく感じられなかった。当時のヴァーラインの恋人、パティ・スミスのアルバムのように、尖ったサウンドを期待していたから、最初の印象は拍子抜けだった。その痩せた体躯そのもののような繊細なヴォーカル、そのしゃっくりあげるような歌い方もパンクらしくない。パティ・スミス直伝のものと思われるそのスタイルは、そもそもあのトッド・ラングレンが彼女に施した指導&特訓によるものらしいのだが。
ジャムバンドを思わせる長尺演奏
バンドを紹介する際、ニューヨーク・パンクの、というのが今でも一般的なのだが、私は彼らのアルバムを発売当時に聴いた時から、その枠内で扱うことには得心がいかなかった。ニューウェイヴのカテゴリーに入れられる時もあるが、それも微妙に違うような…。彼らがパンクらしくないなと感じた要因のひとつには、演奏が、特にギターが上手かったことも挙げられる。音源配信でアップされている『アドヴェンチャー』収録の「エイント・ザット・ナッシン」のインスト・ヴァージョンなど聴いてみると、長いジャム風の即興演奏がとらえられ、さまざまなアイデアをメンバー間で即興的に投げ合っているのが分かる。なるほどスティーブが「ジャムバンドみたいだった」というのもうなづけるところだ。人気曲で、タイトル・チューン「マーキー・ムーン」はアルバムでも10分を越える長尺曲だが、後年、全盛期のサンフランシスコ公演で録られた音源からなるライヴ盤『Live At The Waldorf In San Francisco, 29th June, 1978』を聴くと、同曲は14分まで拡大している。昔からのライヴレパートリー「リトル・ジョニー・ジュエル」も12分弱と、通常のロックバンドではあり得ない長い作品になっている。そこからはスタジオ盤ではうかがい知れなかったバンドの生身の姿、試行錯誤しながら青白い炎を燃え盛らせ、格闘しているみたいである。
ヴァーラインの訃報が届いたのを機に30年振りくらいに集中して聴いてみたが、改めてその特異とも言える独自のスタイルは衝撃的だ。ブルースの影響もまったくないと言っていいのではないか。ヴァーラインがジャズに心酔していたことは前に触れたが、テレヴィジョンを始める前、彼はコルトレーンやアルバート・アイラーのフリージャズ、ヤードバーズのようなギターロック(ということはジェフ・ベックか)、それからヴェルベット・アンダーグラウンドのような実験的なビートバンドを聴き込んでいたという。ヴァーライン自身は好きなバンドとして、ジム・モリスン擁するザ・ドアーズの名を挙げている。詩人でもあったモリスンに共感する部分もあったのだろうと思うが、ドアーズの混沌としたインプロビゼーションなど、どこかテレヴィジョンの中に影響を感じなくはない。
バンドのもうひとりのギタリスト、リチャード・ロイドも、上手いギタリストだった。ヴァーラインに対するサイドギターという立ち位置ではなく、彼もまたリードを弾ける人だった。なんでも、彼はティーンエイジャーの頃、あのジミ・ヘンドリックスにギターを習ったことがあるという逸話の持ち主である。ヴァーラインとロイドが、片方がバッキングに回って…という定石のスタイルではなく、主旋に対するカウンターメロディーとも言うべきふうの互いに異なるリード、フレーズをクロスさせ、決して競い合うことなく曲にメリハリ、流れを作っていく…というような展開を追っていると、それは確かに奇跡のようなものだった。彼らなりのギター美学が貫かれているとも言えようか。現在流通している、やはり『アドヴェンチャー』にボーナストラックとして収録されている「エイント・ザット・ナッシン」(シングルヴァージョン)などを改めて聴くと、あまりにも上手いギタープレイヤーぶりに、ちょっと唖然とさせられるはずだ。リフ、リードの凝ったアイデアなど今でも新鮮で、世のギター弾きは彼らの演奏をぜひ一度聴いてみてほしい。
アルバム『マーキー・ムーン』は売り上げこそ伸びなかったが、批評家筋からも高い評価を受けている。彼らは本国よりむしろ英国で人気を得たようで、シングル「マーキー・ムーン」は英国チャートでトップ30に入っている。また、セカンド作『アドヴェンチャー』は、これまた英国ではトップ10入りしている。先に挙げたライヴ盤を聴く限り、1978年当時、いかにバンドのエナジーは沸騰し、演奏も充実していたかが分かる。それだけに順調に活動を続ければ、バンドはいろんな変化を飲み込みながら、面白い展開が待っていたかもしれないのだが、ヴァーラインは突然バンドを解散してしまう。テレヴィジョンでのツインギター体制に飽きたのか、限界を感じたのか、本当の理由はヴァーラインのみぞ知る、だ。
ソロ活動に移行してからもヴァーラインは多くの映画音楽でギターを弾くほか、『醒めた炎 (原題:Tom Verlaine)』(’79)や『夢時間(原題;Dreamtime)』(’81)をはじめとして、完成度の高いギターロックアルバムをコンスタントに発表していた。ほとんどの作品が日本盤でも出ていたことも意外だが、一度もメジャーアーティストになることもなく、終生アンダーグラウンドの住人みたいな生き方を貫いた人だった。
TEXT:片山 明
アルバム『Marquee Moon』
1977年発表作品
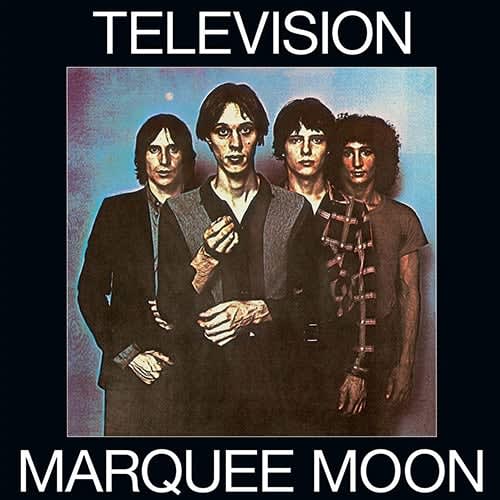
<収録曲>
1. シー・ノー・イーヴル/See No Evil
2. ヴィーナス/Venus
3. フリクション/Friction
4. マーキー・ムーン/Marquee Moon
5. エレヴェイション/Elevation
6. ガイディング・ライト/Guiding Light
7. プルーヴ・イット/Prove It
8. 引き裂かれたカーテン/Torn Curtain
アルバム『Adventure』
1978年発表作品
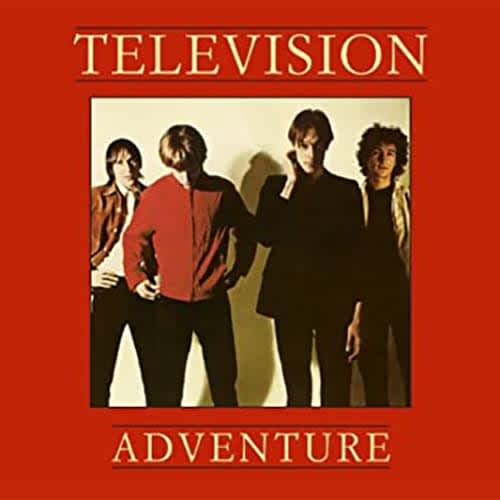
<収録曲>
1. グローリー/GLORY
2. デイズ/DAYS
3. フォックスホール/FOXHOLE
4. ケアフル/CAREFUL
5. キャリード・アウェイ/CARRIED AWAY
6. ザ・ファイア/THE FIRE
7. エイント・ザット・ナッシン/AIN'T THAT NOTHIN'
8. ザ・ドリームズ・ドリーム/ザ・ドリームズ・ドリーム

