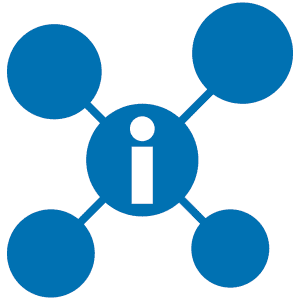茨城県自然博物館(同県坂東市)と東京農工大(東京都)の共同研究チームは12日、動物に付着する植物の種子「ひっつき虫」について、動物の種類や体毛の長さ、体高の3要素が付着量に影響すると解明したと発表した。6日、フランスの生態学誌アクタ・エコロジカのオンライン版に掲載された。
研究チームは2021~22年、同館の野外施設で、キツネやタヌキ、イタチなど、関東地方の平地に生息する中型哺乳類6種の剥製標本を使って、体表に付着する種子量を調査。イノコヅチやチヂミザサなど植物7種計9千個余りが、動物にどのように付着するかも調べた。研究では、同館が所有する野生動物の剥製模型を使用した。
その結果、チヂミザサの種子がキツネなどに多く付着するなど、種子の付着量が動物によって異なることを突き止めた。また、研究では、植物が枯れる前と後で、種が付着しやすい動物の種類が変化する可能性も判明したという。
同館などによると、動物の体表に付着することで散布する植物の種子は、トゲや粘液など付着しやすい構造を持っており、動物の体毛に付着することは知られているが、野生動物による付着散布の実態は国内外でほとんど知られていないという。
共同研究に携わった同館副主任学芸員の後藤優介さんは「洋服に付くひっつき虫の生態を、科学の視点で解明できた。自然の不思議を明らかにできたことに価値がある」と話した。