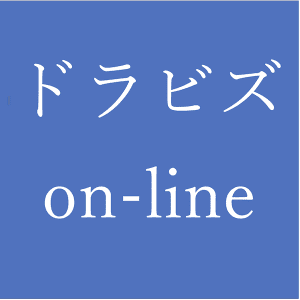【2023.04.27配信】厚生労働省は4月27日、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」を開催し、報告書の骨子案を提示した。「流通取引の改善」については、「薬価差縮減のための制度整備」を記載。「薬価と大きな乖離が発生している取引がある場合は、その見える化と薬価差の偏在の是正に向けた方策を検討」とした。
過度の薬価差が発生するといった薬価差の偏在が課題
報告書の骨子案はあくまで骨子であり、事務局は今後、骨子案からさらに詳細な記載を検討するとした。
同日の検討会で提示された骨子案では、 各テーマについて【課題と要因】と【目指す姿と対策例】 を記載。
「流通取引の課題」については、【課題と要因】として以下のように記載した。
○ 薬価基準制度の変遷や医薬分業の進展とともに、流通実態も変化。購入主体や医薬品のカテゴリー別の薬価差にも影響。こうした状況の中、現在は、一部の取引において、医療上の必要性に関わりなく、過度の薬価差が発生するといった薬価差の偏在が課題
○ 市場実勢価方式による薬価改定が行われる中、取引条件の違いによる購入価格のばらつきも存在。調整幅については、薬剤流通の安定のためのものとされてきたが、20 年以上変更が行われていない中で、流通実態との乖離している可能性
(考えられる要因)
○ 以下のような流通実態が薬価差の偏在の一因
・ 近年は、チェーン薬局や共同購入組織が大規模化することで購買力を強め、また、全国の取引価格をデータ化しベンチマークを用いた価格交渉が業態化するなど、薬価差を得ることを目的とした取引が増加
・ 医療機関・薬局は、卸売販売業者との取引において、前年度の値引き率をベースに総額での一律値下げ(総価取引)を求めてくることが多い。汎用性が高く競合品目が多い長期収載品や後発品は、総価取引の対象とされる傾向にあり、薬価改定による薬価の下落幅が増大
○ 調整幅の流通実態との乖離については、後発品の数量シェアが拡大し、希少疾病用医薬品や再生医療等製品といった配送場所や患者が限定される医薬品が増加するなど、医薬品のカテゴリーチェンジがある中で、配送効率による価格のばらつきに変化が生じていることがその一因
加えて、「流通取引の改善」において【目指す姿と対策例】としては以下のように記載した。
○ 製薬企業、卸売販売業者及び医療機関・薬局といった流通関係者全員が、流通改善ガイドラインを遵守し、過度の薬価差が発生しない健全な流通取引が行われる環境の整備が必要
(ガイドラインの改訂)
○ 医療上特に必要性の高い医薬品については、過度の価格競争により医薬品の価値が損なわれ、安定供給に支障を生じさせないため、これらの医薬品を従来の取引交渉から別枠とするなど、流通改善に関する懇談会等で検討の上、流通改善ガイドラインを改訂
(薬価差縮減のための制度整備)
〇 薬価と大きな乖離が発生している取引がある場合は、その見える化と薬価差の偏在の是正に向けた方策を検討
(流通コストの実態把握)
○ 地域差や医薬品のカテゴリーごとのばらつき状況について実態把握が必要
こうした観点から、以下のような意見があった
・ 配送コストの地域差の状況や医薬品のカテゴリーによって流通実態が異なってきていることが配送効率に与える影響についてよく把握することが必要ではないか