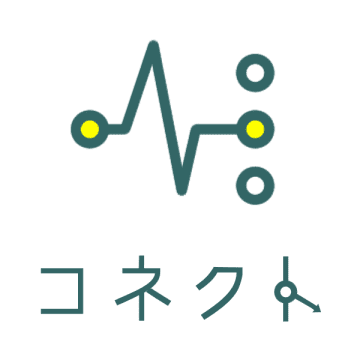東京電力福島第1原発事故で今も約2万7千人が避難生活を続けている福島県。事故当時、富岡町の小学5年生だった佐藤勇樹さん(23)は歴史的な体験を後世に伝える「語り部」として2年間活動を続けたが、今年3月で休止した。事故から12年。町は復興が進み、当時の面影をほとんど残していない。「町を忘れることを受け入れてもいいのかな」。古里にとらわれるのをやめた佐藤さんの心情を追った。(共同通信=加我晋二)
▽分からないまま避難
東日本大震災の発生時は体育館で、卒業式に備えてパイプイスを並べたり紅白幕を張ったりしていた。もうすぐ準備が終わるという時に突然、地鳴りのような音が聞こえ、バスケットボールのゴールがきしんだ。
「なんだこの音は」と思った瞬間、建物全体がねじれるように大きく揺れ始める。「でっかい地震だ」とようやく気づき、先生に言われるがまま並べていたパイプイスの下に頭を隠した。その後は迎えに来てくれた家族と合流。余震が続いていたため自宅近くの空き地で車中泊した。
翌朝、防災行政無線から「避難してください」と大きな音が流れ、何が起きたか分からないまま隣の川内村に移動する。途中、誘導している警察官が白い防護服を着て、ガスマスクのようなものを着けていた。こんな光景は見たことがない。だが当時は近くに原発があることも知らず、ただ「なんでこんな格好しているんだろう」と不思議に思った。
数日後、一家は親戚を頼って茨城県鹿嶋市に避難。富岡町の自宅は居住制限区域になった。
▽初めての一時帰宅
新しい生活が始まっても、なぜ転校し、友達と離れなければならないのかよく理解できなかった。事故のニュースは「炉心溶融(メルトダウン)」「放射性物質」など難しい言葉ばかり。親も新生活で余裕がなく聞けなかった。
それでも新しい友達をつくり、学校になじまないといけない。既に6年生で周りは友人関係ができており、輪に入るのに精いっぱいだった。富岡のことを考える余裕はなくなった。
あの日の朝「行ってきます」と言ったきり、一度も戻れていなかった家に初めて一時帰宅したのは2014年9月だ。周辺の田んぼは雑草が生い茂り、家の中には靴にカバーを付けて入らなければならなかった。床を見ると大量のネズミの死骸や動物のふん。壁には穴が開いていた。
「3年半でここまで変わってしまうのか」。ようやく「大人がどうすることもできないくらいのことが起きた」と被害の大きさを実感した。

▽語り部を始める
大きなショックを受けた一時帰宅だったが、同時に「自分に何かできることはないか」と考えるようになる。もう一度、町と関わりたいとの思いが日に日に大きくなってきた。
2015年、復興を支える人材育成を目指し開校した福島県立ふたば未来学園高に1期生として入学。大学は福島市の福島大に入り、郡山市から通った。そして、富岡町の姿を自分の記憶に刻み続ける目的もあって、2021年に伝承に取り組むNPO法人「富岡町3・11を語る会」に所属し語り部になった。
福島県双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館で、一時帰宅した時の自宅や事故直後の避難の様子を写真で説明しながら、自身の体験を伝え続ける。帰還希望者向けに、地元にどんな仕事があるのか発信する活動にも取り組んだ。
▽町が変わった
だが古里への思いとすれ違うように、富岡町は変わり続けていく。半壊した自宅の取り壊しは「しょうがない」と受け入れたつもりだったが、いざ更地になった跡地を見ると喪失感に襲われた。
その後も原発事故前からあった建物は少しずつ減り、唯一残っていた小学校も取り壊された。「富岡はもう、別の町だ」。関わり続けたいと思っていた以前の町の姿からかけ離れたように感じ、語り部活動をする意欲が薄れたが、辞めると地元のコミュニティーにいられなくなる気がして続けた。

▽距離を置く
大学4年になり、進路の選択が迫った。避難解除が進んでいた富岡に住むかどうか、迷いが頭をもたげる。「同世代の人の考えを聞いてみたい」との思いもあり、同じ地域出身の友人らにインタビューし、YouTubeにアップして発信する活動を始めた。
地元に戻った人、戻らないと決めた人、遠い場所にいてもつながりを持ち続けている人。さまざまな立場の意見を聞き、富岡に戻ることだけが全てではないと思えた。選択は自由で、関わり方はさまざまある。自分は一度、地元と距離を置いてみようと決めた。
大学卒業後は関心があった教育関係の仕事に就き、福島市で新たな生活を開始。農業高校の生徒による商品開発をサポートするなどしている。原発事故にとらわれず落ち着いて将来を考えられるようになり、ゆくゆくは教員を目指す道も考えるようになった。
語り部は月1回ほど続けたが、車で富岡に通いながらの活動は負担に感じるようになった。「原発事故前の富岡を忘れてはいけない」という義務感のような気持ちは、気付けばなくなっていた。
▽校舎跡地を歩いて
今年2月下旬、小学校の跡地を記者と歩いた。校庭があった場所には介護や福祉の拠点となる施設が建ち、バス停や校門の柱など一部しか面影が残っていない。だが風景は一変していることは「今は何も思わないです」と言い切る。

ところどころで「あっちにブランコや遊具があって、こっちには児童用の玄関がありました」と教えてくれた。なくなったことは仕方ないが、忘れてしまった部分もあることには寂しさがあるという。「せめて卒業アルバムは欲しかったですね。転校先のアルバムには6年生だった1年間分の思い出しかないので」。校庭だった場所に建つ真新しい施設を眺め「みんなばらばらに避難したので難しいとは思いますけど」とつぶやいた。この10日後の3月5日、語り部活動に区切りを付けた。

▽緩い関わりに
原発事故から12年。もう避難している意識はない。今後富岡町に住むことがあっても「帰還」ではなく「移住」する感覚だという。思い返せば、町に関わることを難しく考えすぎていた。今は「無理に覚えようとするのではなく、緩い関わり方でいい」と思っている。古里は「行きたい店がある」とか「友達に会いに行く」という感覚で足を運ぶだろう。「自分にとっての『復興』は終わりつつあるんです」と前を向いた。