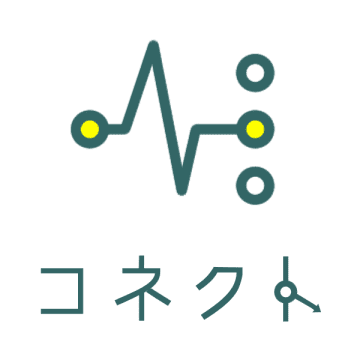短時間に局地的な豪雨をもたらす線状降水帯の発生情報を、気象庁が最大30分早く発表する運用をきのう、始めた。
これまで降雨の量や範囲など一定の基準を満たしてからの発表だったが、30分先までに基準に達すると判断される場合にも広げる。
前倒しは、土砂災害や洪水が発生する危険性が高まっていることを少しでも早く伝えるためだ。2026年からは、2~3時間前の発表を目指すという。
局地的豪雨では、冠水によって瞬く間に水位が上昇して逃げ遅れるケースがある。早期の避難につなげ、命を守る行動に活用することが求められる。
線状降水帯は、発達した積乱雲が次々と発生して帯状に連なり、同じ場所で豪雨をもたらす。18年の西日本豪雨や20年の7月豪雨など、大規模被害を引き起こす要因となっている。
このため、気象庁は降水帯情報の強化に取り組んでいる。発生の発表は「顕著な大雨に関する気象情報」として、21年6月から開始した。昨年6月には、約12~6時間前に発生の可能性を伝える「半日前予測」の提供も始め、発生時と予測の両面から警戒を呼びかけてきた。
半日前予測は現在、大まかな地方単位での発表だが、24年には都道府県単位に、29年には市町村単位に絞り込んでの情報提供を視野に入れる。
ただ、発展途上の技術であることは踏まえる必要がある。降水帯の形成には、海上の水蒸気や陸上の湿度などが複雑に関係し、予測が難しいという。
昨年6~10月に発表した半日前予測で、実際に予測が的中したのは13回中3回。発生した11回のうち、予測がなかった「見逃し」は8回だった。
気象庁は新たにスーパーコンピューターを導入し、水蒸気の観測体制も強化する。情報の信頼性を高め、防災対策につなげるためにも精度の向上を加速させたい。
もうすぐ梅雨入り。近年、短時間に大雨が降る頻度は増加しており、降水帯情報の発表も増える見通しだ。気象庁の担当者は「危機のスイッチを押すきっかけにしてほしい」と呼びかける。
例え情報が空振りであったとしても、発表の対象地域が大雨になる確率が高いのは、過去データからも明らかという。
気象庁や自治体の防災情報への感度を高め、暮らしを守る判断材料として生かしたい。