
人気作家、村上春樹さん(74)の6年ぶりとなる新作長編小説「街とその不確かな壁」が4月13日に発売された。発売日には書店でカウントダウンイベントが行われるなど話題を集め、出版取次大手の日本出版販売とトーハンが発表した2023年上半期のベストセラーランキングでいずれも1位に輝いた。本書は1985年の長編「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」と同様、80年に文芸誌に発表した中編が下敷きになっている。ドイツ文学者の松永美穂さん(64)と英米文学者の阿部公彦さん(56)が、新作について率直に語り合った。(司会・聞き手は田村文・共同通信編集委員)
▽「最近の村上作品には違和感を覚えることが多かったが…」
―「街とその不確かな壁」は村上春樹さんの6年ぶりの長編小説です。3部構成で、第1部は17歳の「ぼく」と、「ぼく」が年を重ねた「私」の話が交互に語られます。「ぼく」が恋をしている16歳の「きみ」は、「本当のわたし」が生きているのは高い壁に囲まれた街なのだと語った後で姿を消す。一方、中年になった「私」は「きみ」が語っていた街に入り込んでいます。街の時計には針がなく、人々は影を持たない。壁の内側にとどまるべきか、外に出るべきか。決断の時が来る。第2部は舞台を福島県に移します。70代の子易(こやす)さんの後を継ぎ、図書館長になった40代の「私」は図書館に毎日のように来る少年と出会う―。ではまず、新作を読んでの印象を教えてください。
松永美穂 私は村上さんの最近の作品には違和感を覚えることが多かったのですが、本書には好感を持ちました。セックスや暴力は姿を見せずに内面に向かう話で、出てくる他者は限定的ですが、登場人物が絞られているからこそ関係性がよく見えます。丁寧に作り込まれていて、集大成的な作品になっていると思いました。
阿部公彦 第1部に80年の中編が原形をとどめる形で残っていることもあり、昔の自分をどう受け止めるかということ自体が作品になっていると感じました。第1部は初期の村上作品の叙情的な感じがあり、第2部はそれを受け止めて展開し、第3部で融和する。昔の自分と今の自分が拮抗(きっこう)するのが興味深い。

松永 「世界の終り―」は一番好きな作品だったので、本書を読み始めたときは既視感があり、戸惑いました。でも読み進めていくと、主人公が自分の影と分かれる分裂の仕方が成熟した書き方になっているのをはじめ、どんどん印象が変わっていく。若いころとは違う場所に行こうとしたのでしょうね。
阿部 冒頭でイギリス・ロマン派の詩人、コールリッジの「クブラ・カーン」を掲げています。村上さんがこの詩を意識したのがいつなのか分かりませんが、本書には「クブラ・カーン」の一節に似ている箇所がある。「壁に囲まれた街」自体、コールリッジが書いたザナドゥという桃源郷を思わせます。
「世界の終り―」もそうですが、壁をはさんで自分と影、現実と幻想、生と死といった二項対立が描かれますが、それが不安定で揺らぐところが面白い。同じモチーフを繰り返し書いていても、創作態度としては自然だし必然であると思います。

松永 今年3月に亡くなった大江健三郎さんもそうでしたね。
阿部 同じモチーフを何度も書く人には、特定の場所へのこだわり、空間的なオブセッション(強迫観念)のようなものがあるのだと思います。大江さんにとっては四国の谷間の村で、中上健次さんは和歌山の新宮、村上さんは壁に囲まれた街なのでしょうね。
松永 村上さんの小説には壁だけでなく、穴や井戸もよく出てきます。そしてある建物を下りていくと異世界とつながる。今回は半地下にある図書館長室がそうでした。
▽「カフカへの反論のようなものを感じる」
―村上さんにとって「壁」とは何だと思いますか。
阿部 壁に直面した時の無力感、システムの壁にはねかえされる感覚みたいなものが、村上さんの世代の感性としてあるのだと思います。2009年にイスラエルのエルサレム賞を受けた際のスピーチも思い出しました。「ここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます」と話していましたよね。
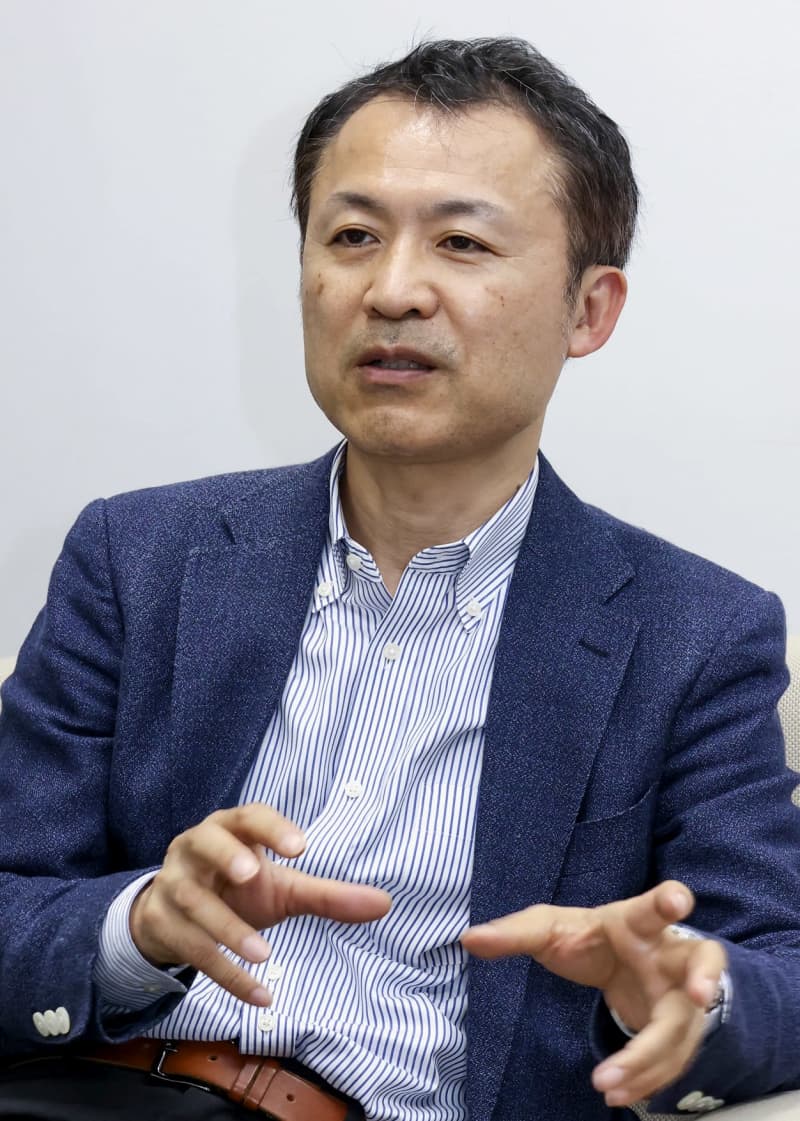
松永 私はカフカを想起しました。「審判」と「掟(おきて)の前で」には門番が登場し、男は最後まで「掟」の中に入れない。でも村上作品に出てくる壁は「壁抜け」できる可能性がある。そこにカフカへの反論のようなものを感じます。
人々を分断する壁は至る所にありますが、抜けて向こう側に行けるというポジティブなメッセージを受け取りました。壁の高さは8メートルと書いてあり、ベルリンの壁の高さの2倍ほどで、随分高い壁ですよね。
また新型コロナウイルスを受けてのロックダウン(都市封鎖)で、私たちは境界線の存在を意識した。そのことも思い出しました。
―本書の登場人物や舞台についてどう思いますか。
阿部 名前が付けられている登場人物が少ないですね。第2部に出てくる70代男性の「子易さん」や図書館司書の女性「添田さん」など限られています。場所も福島以外に具体的な地名が出てこない。固有名詞が少ないので、小説全体が寓話(ぐうわ)的な印象です。
男性の子易さんがスカートをはいているとか、少年が耳をかむといった描写から、村上さんのセクシュアリティーやジェンダーの捉え方の変化を感じます。
松永 そうですね。性的同意についても意識しているようです。ただ母親たちの描き方がステレオタイプに感じられ、それが少し気になりました。好きな女性が手の届かない所に行ってしまい、それが物語の起動力になるという書き方もどうなのかな…。
一方で、異世界をつなぐ子易さんの存在は重要です。少年は特別な能力を持っていて「私」の後継者になる。子易さんと「私」と少年を結び付けるのが図書館です。図書館というのは物語や記憶が蓄積され、作家が死んだ後も物語が生き延びる所でもある。

▽「村上さんは日本文学のアンチとして出発」
―村上さんはいま74歳です。でも作品からは老いを感じません。なぜなのでしょう。
阿部 若い頃の村上さんは断片的なエピソードをつなぐ書き方で、中期以降は水も漏らさぬ緻密な文章になり、ひねりやキレも加わりました。語り方というか、作中の声が強めに聞こえる作家だと思います。老いた声というのはもっと枯れて薄いものなのですが、それとはかけ離れています。
松永 大江健三郎さんは意識して語り方を変えていった作家でした。2013年出版の「晩年様式集(イン・レイト・スタイル)」には、デモに出かけて疲れてしまう老人が出てきます。

阿部 大江さんも欧米文学の影響を受けていますが、彼をつなぎとめる故郷、確かな足場というのがあった。村上さんにはそれがなく、根無し草的です。でも西洋文学を輸入して成り立った日本の小説は、本質的に根無し草ともいえますよね。
―日本文学の中心にいた大江さんが亡くなり、今後の日本文学はどこへ向かうのでしょうか。村上さんの立ち位置は?
阿部 村上さんは日本文学のアンチとして出発したのだと思います。女性にもてまくる主人公が登場するし、フィッツジェラルドを思わせる決め台詞も出てくる。日本文学的なウエットな駄目男の系譜に反発したのが分かります。そこから徐々に自由になっていき、成熟した文章を書く作家になりましたが、日本文学の中心にはならないだろうと思います。
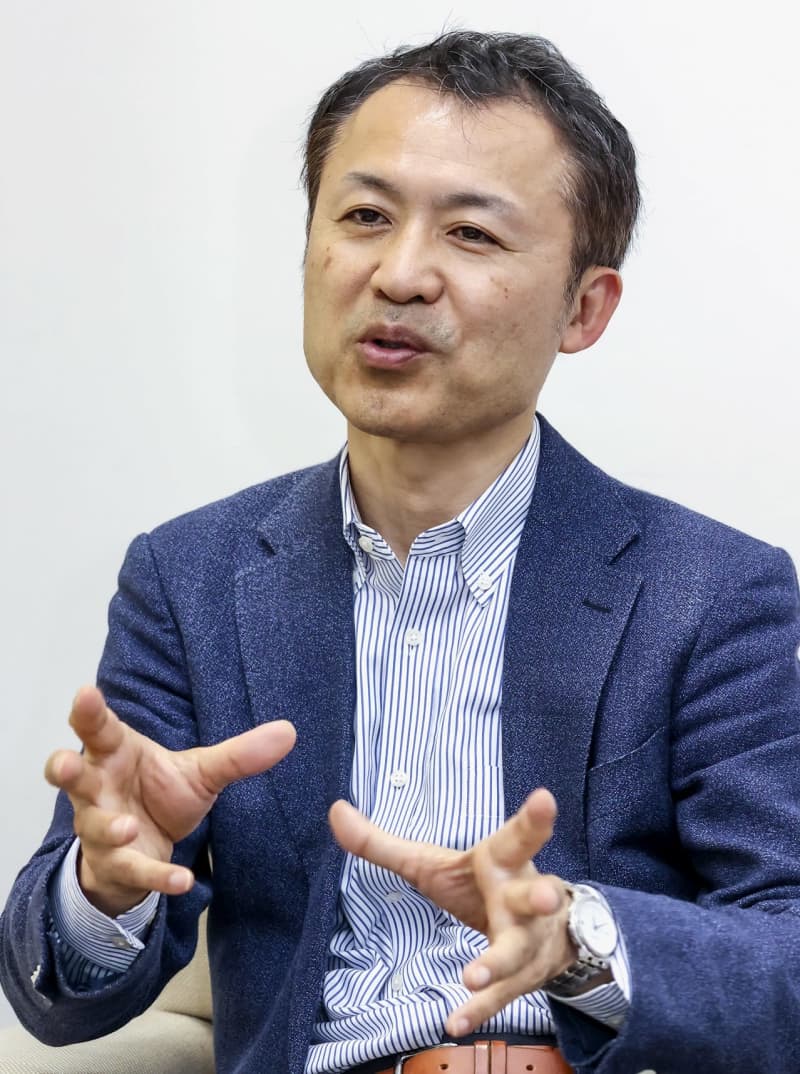
▽「どう受け取るかは読者に委ねられる終わり方」
松永 私も村上さんは日本文学の中心にいるのではなく、遠い場所に屹立している気がします。でも中心には誰がいるのかというと、分からないですね。
日本語による文学は多様化し、海外では村上さん以後の需要が高まっています。多和田葉子さんや小川洋子さんに加え、川上未映子さんや村田沙耶香さんといった女性作家が読まれるようになっている。リアリズムというよりも想像力を豊かに働かせて書く作家が多く、日本文学の新しい面を発信しています。
―本書の終わり方についてはどう思いますか。
阿部 この作品は生と死を、対立するものではなく、連続しているものとして捉えていると思うのですが、最後も同じように感じました。
松永 いわゆるオープンエンドで、どう受け取るかは読者に委ねられる。それは読者を信じ、物語や言葉が作り出す力を信じることでもあると思います。

× × ×
松永美穂(まつなが・みほ) 1958年名古屋市生まれ。ドイツ文学者。翻訳家。早稲田大教授。2000年に翻訳、出版したベルンハルト・シュリンク「朗読者」がベストセラーになり、毎日出版文化賞特別賞受賞。著書に「誤解でございます」など。
阿部公彦(あべ・まさひこ) 1966年横浜市生まれ。英米文学者。文芸評論家。翻訳家。東京大教授。2012年出版の「文学を〈凝視する〉」でサントリー学芸賞。他の著書に「幼さという戦略」「病んだ言葉 癒やす言葉 生きる言葉」など。
田村文(たむら・あや) 1965年埼玉県生まれ。共同通信編集委員。11年間、全567回にわたる連載「本の世界へようこそ」をまとめた著書「いつか君に出会ってほしい本」を今春、出版した。

