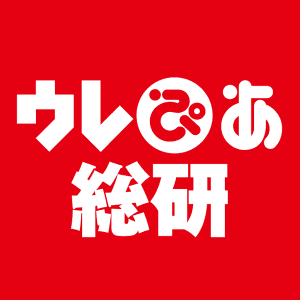発達障害と診断される子どもたちが増え、「自分の子どもにも発達の遅れがあるのでは?」と心配するママ・パパも多いようです。
その多くの場合は杞憂に終わりますが、中にはなかなか発達障害に気づけないケースもあります。
そこで今回は、40年以上小学校教員をしてきた村田しのぶさんの著書『[特別支援学級]しのぶ先生が教える 発達障害&グレーゾーンの子どもが「1人でできる子」になる言葉のかけ方・伝え方』より、発達障害&グレーゾーンの子どもの教育現場でよく見られる特徴(症状)についてまとめます。
特徴1 パニックを起こしやすい

発達障害の子どもたちの中には、「見る、聞く、触る、味わう、嗅ぐ」などの五感がかなり異なっている子がいます。音や触感に敏感だったり、逆に暑さ・寒さに鈍感ということもあります。
慣れないことが多く、ただでさえ不安が多い学校での新生活では、教室の騒がしさでイライラし、耳を塞ぐ、大声を出す、机の下にもぐる、勝手に席を離れて教室の外へ飛び出すなどパニックになる子も。
私たちが意識しないようなかすかな音でも、耳障りな騒音に聞こえ、両手で耳を塞いで机に突っ伏してしまったり、癇癪を起こしたりする子どもたちもいます。学校生活に慣れてくると、落ち着きが見えてきますが、そうすると今度は、身体測定や遠足などの行事が入ってきて、予定が変わることでパニックになってしまいます
もちろん、身体測定や遠足などについては事前に説明があるものの、そのイメージが湧きません。イメージできないことは不安につながり、怖いと思ってしまうのです。
特徴2 コミュニケーションが苦手
「会話が成立しない」のも、発達障害の子どもに見られやすい特徴の一つです。
「○○できましたか?」と聞くと、同じように「できましたか?」とオウム返しをしたり、「何を見つけましたか?」という質問に、「バッタ」「蝶々」というように一語で答えるだけで、どこで、どのようになど、順序立てた話がなかなか難しいのです
言葉の理解や会話力が不十分なため、ほかの友だちとの関係でも良好な関係を築けないことがあります。
また抽象的な言葉や例え話の理解が難しい、言外の意味を読み取るのが苦手という特徴もあります。
特徴3 同じことをいつまでも繰り返す
発達障害がある子どもの行動は、簡単にパターン化できないものの、よく見られる行動として、クレーン現象や行動の繰り返しが挙げられます。
クレーン現象というのは、たとえば、子どもが「あの積み木で遊びたい」と思っても言葉がうまく出てこないため、近くにいる人の腕をとって、その人の手で積み木をとらせようとするというようなことです。相手は急に腕をつかまれるため、驚いてしまいますが、年齢の割に言葉がうまく使えないために起こっています
クレーン現象のほかに、同じことを続けるという特徴もあります。積み木や小石を並べて、一人で遊び続け、並べ終わると元に戻して、また最初から始めます。
慣れた行動パターンを好み、初めての経験を嫌うのです。見通しが立つと安心するので、運動などでは何度か見学し、ルールを理解することで、少しずつできるようになります
特徴4 勝ち負けにこだわる

ジャンケンで負けると、負けたことが悔しくて「もう一度やって」と相手を困らせたり、かけっこでみんなに抜かれ始めるととたんに泣き始めたり。負けることが受け入れられないのです
思うようにならないと、自分の気持ちをコントロールできなくなるという特徴もよく見られます。

特徴5 学習科目でのハードル
小学校に入ると見えてくるのが、学習に関することです。
衣服を自分で着たり、トイレに行ったりなど、日常の身辺処理は自立しているし、教科書もスラスラ読める…それなのに、文字が書けない子がいます。見ていると、文字のバランスがとれていなくて、マスの中に文字が入っていません
また、目の上下運動がうまく機能していないため、黒板の「タテ書きの文字」を視写できなかったり、「あ・め」「ぬ・ね」「ソ・リ」といった「似ている文字」の区別も苦手だったりします。
こうした特徴は、発達障害について熟知していない先生や保護者が「ふざけている」「なまけている」と誤った対応をしてしまうことがあるので注意が必要です。
学習障害がある場合は、その子に合った教材を工夫し、繰り返し練習することで、少しずつでも苦手を克服するよう支援します
*
「それぞれの障害を理解し、対応方法を実践し、焦らず子育てをしていくことが大切」と村田先生。
そうすることで、保護者自身も将来の不安から解放され、子育てに希望をもって歩き出せるようになるといいます。
担任の先生や相談機関、医療者などと協力・連携しながら、あきらめることなく歩みを進めていきましょう。
著者:村田 しのぶ
神奈川県綾瀬市、秦野市立小学校の普通学級教諭を15年務める。その際、学級の中に自閉スペクトラム症、場面緘黙症など、さまざまな発達障害の児童がいたことがきっかけで特別支援を要する児童の教育に関心を持ち、その後、特別支援学校教諭の免許を取得し、特別支援学級を25年以上にわたって担当する。
(ハピママ*/ 庄司 真紀)