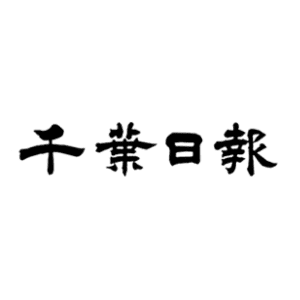東京電力福島第1原発の処理水について、政府と東電は夏ごろの海洋放出開始を目指している。福島県や千葉県などの漁業関係者らから風評被害への不安の声が上がる中、千葉県の報道関係者にも放出に向けた準備状況や廃炉作業の現状が公開された。東日本大震災から12年。いまだ事故の爪痕が残る原発構内を取材した。(報道部・吉田夏子)
5月16日、同原発を訪れた。入り口となる入退域管理棟で、所持品チェックや本人確認などの入構手続きを1時間以上かけて受け、原発構内に入った。
原発構内では、東電職員や協力会社の作業員が1日平均約4500人働いている。現在、構内は9割以上のエリアで全面マスクや防護服着用の必要がない。身に着けたのは、作業用の靴やヘルメット、使い捨てマスク、軍手など。想定していたよりも軽装で各施設を回った。
構内に入ると、高さ10メートルを超える巨大なタンクが所狭しと並んでいた。その数は千基以上。タンク内には、今なお増え続ける「処理水」が貯蔵されている。
福島第1原発では、溶け落ちた核燃料を冷やすための注水や流入した地下水、雨水によって「汚染水」が1日平均約90立方メートル発生。処理水は多核種除去設備「ALPS(アルプス)」などで、高濃度の放射性物質を含む汚染水を浄化させたもの。ただ、トリチウムは除去が難しく、放出前に国の規制基準値を下回るまで海水で希釈する。
タンクは来年2~6月ごろまでに満杯になる見込みで、廃炉作業を進めるためにはタンクを減らしていく必要があるという。政府と東電は夏ごろの海洋放出を計画しており、担当者は「放出の終了は廃炉作業が完了するまでと考える」と述べた。
原発構内では風評対策として、海洋放出時と同程度にトリチウムを薄めた処理水と、通常の海水の水槽を用いてアワビとヒラメの飼育試験を行っている。それぞれの生育状況を比べ、目に見える形で安全を証明するためだ。水槽の様子は動画配信サイト「YouTube」で常時生配信し、ウェブサイトで飼育日誌を公開している。
1~4号機の原子炉建屋も高台から見学した。水素爆発を起こした1号機は12年たっても上部の鉄骨がむき出しのままで、大きながれきが残っている。周辺では防護服を着た作業員たちが働く姿も見えた。線量の高い建屋での作業は思うように進まず、数十年かかる廃炉作業で最難関とされる溶け落ちた核燃料「燃料デブリ」の取り出しはまだ始まっていない。
事故から12年たった原発構内では、処理水の海洋放出に向け着々と準備が進められていた。一方で廃炉作業は数十年にわたり、その間も放出は続くのだから、漁業関係者をはじめ、不安を抱える人がいるのも当然と言える。
取材の中で、一見すると事故の処理が進んでいるようにも思えた。だが、いまだ残る事故の爪痕を見ると、今は廃炉作業の始まりに過ぎず、先は途方もなく長いのだと感じた。