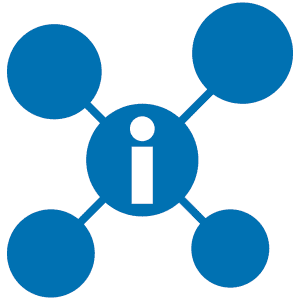■焦土「生きる希望に」
次は水戸だろうか。明日か、それとも今晩か。太平洋戦争末期、米軍による空襲が日立、土浦と相次ぎ、市民たちは不安を募らせていた。
すぐに現実となる。空襲警報が鳴り響く中、当時14歳だった大畠一良(92)は水戸駅前の自宅を飛び出し、両親と岩間街道を笠間方面へ急いだ。
持って出たのは、先祖の位牌とわずかな食べ物。周囲には、頭から布団をかぶった人、幼子と赤ん坊を背中と胸に抱いた母親、手を引かれる腰の曲がったお年寄り。暗い道は「なりふり構わず逃げる人たちであふれていた」。
1945年8月2日午前0時31分、米軍による空襲が始まる。夜空がピカッと光り、振り返ると、水戸駅方面に落とされた爆弾が途中で散らばり、雨のように降り注ぐのが見えた。焼夷(しょうい)弾だった。
すぐにあちこちで火の手が上がり、範囲が広がる。「もう駄目か」。地面のくぼみに腹ばいになり、泥に顔を押し付けた。いつまでそうしていたか、記憶はない。
夜が明け、市街地に戻って目にしたのは、一面の焼け野原。自宅は焼け落ち、柱がまだ燃えていた。
水戸を襲った爆撃機B29は160機。空襲は2時間近くに及ぶ。水戸市街のほぼ全域が焦土と化し、死者は少なくとも300人を超えた。終戦のわずか2週間前のことだった。
終戦により、きのうまで正しいと信じてきたことは否定された。数年後、大畠の家はようやく水戸駅前に再建されるが、心の穴は開いたままだった。
家のそばには、大イチョウが空襲で真っ黒に焼け焦げたまま立っていた。ある日、ふと見上げると、枝に小さな輝き。黄緑色の芽だった。「お前も助かったのか。よかったなぁ」。思わず声に出していた。空襲から2年半たっていた。
毎年春には芽吹くようになる。空襲で傷つき、焦げた大木が息を吹き返していく姿は、大畠にとって希望の光となった。
「子どもの頃から木の回りでよく遊んだ。楽しかった頃を思い出し、明日も頑張ろうと励まされた」
同市の加藤浩一(80)は戦後、祖父や近所の大人たちから大イチョウの話を聞いて育った。
「空襲で全てを失った市民にとって、焼け焦げても再び芽を出す姿がどれほど励みになったことか」
加藤は市長に就任すると水戸空襲を後世に伝えようと、大木のそばに説明板や平和記念館を設置した。
「打ちひしがれても、人間は何かをきっかけに頑張れる。戦後、大イチョウが多くの市民の精神的な支えとなり、水戸の復興につながった」。説明板を設けた当時の心境を振り返る。
水戸駅北口から水戸中央郵便局まで続く緩やかな坂は「銀杏(いちょう)坂」と呼ばれる。イチョウは江戸時代初期からこの地に立っていたという記録も残る。
樹齢300年余り。高さ約10メートル・幹周り5メートル。現在も銀杏坂交差点そばで、空に向かって両手を広げるように、青々と葉を茂らせている。時代とともに街の景色は変わったが、黙って見守り続けている。
市公園協会は年間を通して手入れを続ける。夏場は土壌の乾燥を防ぐため、幹の周りにこもを巻き、1回に1000リットルの水をまく。協会の半田浩之(52)は「水戸の復興のシンボル。しっかりと守っていきたい」と話す。
大畠は今も大イチョウのそばに住む。「平和な朝を共に迎えられることが何よりうれしい」。小さな芽を見つけた時のように仰ぎ見る。(敬称略、随時掲載)
■水戸空襲
1945年8月2日未明、米軍爆撃機B29が水戸市上空から無差別爆撃。市全域が焦土と化し、死者は少なくとも300人を超えた