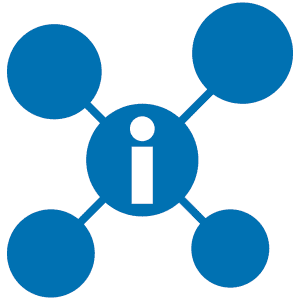■終戦後、両親と涙の再会
「やるしかないと覚悟していた。誰もが行くものと思っていた」。1944年6月、羽鳥泰司さん(100)=茨城県小美玉市=が畑仕事から戻ると、父から召集令状(赤紙)を手渡された。
出征先は海を渡り、郷里から1300キロ離れた朝鮮半島。最寄り駅から列車に乗り込むと、後ろから3、4人の若者が続いた。乗客は全て兵士だった。
何度も乗り継いで西進し、博多からは船で釜山へ。半島を北上して北緯38度線を越えた駐留地へたどり着き、陸軍の歩兵部隊「第42部隊」に入隊した。
■マラリアに感染
部隊では、銃剣に見立てたやりを握り、防具を着けた仲間の胸を突く練習に明け暮れた。「うまい人ほど階級がどんどん上がっていった」。数人ずつの班で銃を磨いたり、組み立てたりもしたが、実弾を撃つ機会は終戦まで訪れることはなかった。
暗号文を解読する仕事もあり、乱数表は3カ月ごとに変更された。それでも「探知されていただろう。どこで何をするか、米国に教えるようなものだった」。
生活は過酷そのもの。現地の生水は煮沸しなければ飲めなかった。マラリアに感染して40度以上の高熱に苦しみ、薬を飲んでも汗と体の震えが止まらなかった。その上、九州出身の先輩隊員には「内地に帰っても仕返しされる心配ないから、思いっ切りやってやる」といじめられた。
忘れられない言葉がある。「兵器を造るには金がかかるが、お前らはただで集まる」。当時の上官の何げないひと言は今も胸に突き刺さる。
駐留地近くの海岸沿いでは、米軍の空襲に備えて夜を徹して監視に当たることも。仲間と協力して機体の色や形を覚えたが、終戦まで敵機が部隊を攻撃してくることはなかった。
■広島に降り立つ
入隊から1年余りたった45年8月15日。音が割れたラジオの音声が兵舎に響いた。周りには耳を澄ませる同僚たち。次第に敗戦を伝える放送と分かった。「何だ、負けたんだ」とだけ感じた。悔しさが胸に湧くことはなかった。
終戦後は、生きて両親の元へ戻ることだけを考えた。2人の姉は開戦までに嫁ぎ、家を出ていた。「実家を継ぐのが自分の役目」。そう信じてふるさとを目指した。
ソウルや釜山を経由して本州へ渡り、原子爆弾が投下された広島にも降り立った。辺り一面が焼け野原。「原爆とはこれほどか」。ぼうぜんと立ち尽くした。
やっとの思いでたどり着いた自宅前には両親の姿。「本当に良かった」。3人で肩を寄せ合い、涙ぐみながら再会を喜び合った。
「戦争をしたくてしょうがなかった。そういう仕組みになっていた」。あれから78年。「人を殺して、物を壊して、生むことなんか何にもない」。厭戦(えんせん)の思いは今も変わらない。