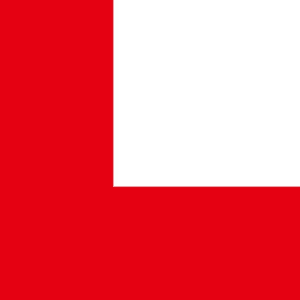モデル・俳優業の傍ら、20代から映像制作に積極的に携わり、プライベートでは移動映画館「シネマバード」を発案。業界きってのシネフィル(映画狂)として知られる俳優・斎藤工。2012年には本名の齊藤工名義で監督デビューを果たし、2018年の初長編作品『blank13』では『上海国際映画祭』で最優秀監督賞に輝くなど、監督としても注目を集めている。

『スイート・マイホーム』の齊藤工監督(左)と映画評論家・ミルクマン斉藤
そんな齊藤工監督の最新作となる『スイート・マイホーム』が9月1日に公開された。原作は選考委員の満場一致で小説現代長編新人賞に輝いた作家・神津凛子のデビュー作。長野県に住むスポーツインストラクターの清沢賢二は、愛する妻と娘のために一軒家を購入するも、ある不可解な出来事をきっかけに身の毛立つ恐怖へと転じていく物語だ。
「家」を中心にさまざまな思惑と怪異がスリリングに幾重にも重なり、これまでの常識を覆すホラー・ミステリー作品となった『スイート・マイホーム』。メガホンをとった齊藤監督と、以前から親交のある映画評論家・ミルクマン斉藤による「サイトウ」対談をおこなった。
取材・文/ミルクマン斉藤 写真/木村正史
◆「準備したものを瞬間的に覆す」(齊藤監督)
──こういうホラー的な映画というのは、ケーブルテレビ局『HBOアジア』で製作された短編を除けば、長編としては初めてですよね?
そうですね。監督として原作モノを映画化するのも初めてでしたね。今までは、2021年の映画『ゾッキ』(竹中直人、山田孝之、齊藤工の3人が共同監督をつとめた)も含めて、企画の段階から立ち会っていたものが大半だったので。ある種、自主映画的というか。
本来、この原作は黒沢清さんとかが監督をされるべきなんじゃないか、僕じゃないよなって何度かお断りしたんです。
──確かに、私も黒沢さんに話が行きそうな題材だな、と思いました(笑)。
僕じゃあ無理かなと思って。2019年かな、映画『シン・ウルトラマン』の直後くらいにこのお話をいただいて、足踏みをしていたときにコロナ禍になってしまって。ステイホームの時期になって、原作の世界と現実が繋がってしまった感じがあったんです。スタートから4年くらいかかって、なんかじんわりと引き受けることになったというか。不思議なプロセスでしたね。

最新作『スイート・マイホーム』について語る齊藤工監督
──日本の小市民一家を描いている点では、齊藤監督の長編デビュー作『blank13』にも通じるなと思いました。登場人物の家庭環境も含めて。でも話が進むにつれて、人間描写も照明もさまざまなギミックがどんどん使われ、ときにシュルレアル(超現実)な様相も呈してくる。
そのあたりは、撮影の芦澤明子さんにおんぶに抱っこでした。コロナ禍もあって、作戦を練る時間だけはあったんですが、やっぱり現場での役者さんの予期せぬ表現だったり、生で起こるものにフォーカスしていくべきだなと思いましたね。実写である限り、やはり「生」っていうものを切り取らないと意味がないなと感じて。
最初は、もっとロングショットで構成しようと思っていて、編集の高橋幸一さんに日々素材を投げていたんです。けれど、今回の役者さんたちは寄りが強いので、撮影の3日目くらい前ぐらいに、高橋さん、芦沢さんと3人で方向転換して、クローズアップで顔を撮っていこうと。時間かけて準備したものを瞬間的に覆すという、そういうことがクランクアップまでありましたね。

©2023『スイート・マイホーム』製作委員会 ©神津凛子/講談社
──主演の窪田正孝さんをはじめ、蓮佛美沙子さん、奈緒さん、そして、窪塚洋介さんと、寄りの強い面々が集まってますもんね。それにしても、キャスティングが絶妙です。
たぶん、このキャスティングじゃなかったら成功しなかったと思います。スタッフもそうですけど、窪田正孝さんと撮影の芦澤さん、この2人は僕のなかで第一条件でした。この2人がキャスティングできなかったらオファーは受けないという条件だったんで、そこは恵まれました。
◆「僕は最初から白旗を掲げて・・・」(齊藤監督)
──とにかく、窪田さんが素晴らしいんですよね。寄りのショットが強いとおっしゃっていましたけど、まさにそうで。しかも芝居自体は、どちらかというと受けに徹しているにも関わらず。
彼に反射するように、奥さん役の蓮佛美沙子さんも科学反応を起こしていくのが面白かったですね。何が起こるかは予想しなかったんですけど、あの夫婦が変化していくという話なんで、それぞれ良い意味で影響し合って。ラストも当初の予定とは全然違って、おふたりの顔に始まり、顔で終わることに変えましょう、と。
──で、エンドタイトルが終わったあとにもう1度、女の子の顔が来るという。
そうですね。
──それがプロローグと同じく、手で顔を覆う女の子で。枠構造のようになっている。
僕は結構、自分の映画でも枠を作りがちなんです。終わりの意味をつなげたいというのがあって。原作にはなかったんですが、母性というか、女性性の伝承みたいな話だなと。全然世界観は違うんですけど、アリ・アスター監督の『ヘレディタリー/継承』(2018年のホラー映画)なんかがイメージにあって。なにかを継承してしまう、男性ではなく女性の母性というか深い愛ゆえの魔性というかな。

©2023『スイート・マイホーム』製作委員会 ©神津凛子/講談社
原作の神津凛子先生も女性だし、それを女性キャメラマンの芦澤さんに切り取ってもらいたかった。男性の無力さを撮影行為としても日々感じ取っていきたいと思っていたんで、自然にそういうフォーメーションになっていきました。子役の女の子たちも含め、そういう女性性みたいなものを女性たちに描いて表現してもらうという、ちょっと蚊帳の外みたいなアングルで僕は関わっていた感じですね。
──私も『ヘレディタリー/継承』を想起しました。あの映画もミニチュアの家から始まる入れ子構造で、家への執着がありますもんね。おそらくアスター監督も影響を受けたであろうジャック・クレイトン監督の『回転』(1961年のホラー映画)もそうで。その枠を落とし込んだ脚本の倉持裕さんは最初から想定されたんですか?
ちょうど『ゾッキ』を作っていた時期と重なったり、(主演映画の)『零落』(2023年)があったり。決して2時間で収まるような原作ではなかったですし、原作では本田(奈緒)から見たパートがあったり、甘利(松角洋平)から見たパートがあったりしますから。僕は甘利が一番好きだったんですけど。それを一本化するのはなかなか至難の業で。
──原作は、複数の視点から語られる構成ですからね。映画にすると冗長になりかねない。
なので、あの大橋裕之の世界を脚本に落としこむっていうウルトラCみたいなことを『ゾッキ』でやってのけた倉持さんなら、原作に対して誠実に自分のエッセンスで掛け算ができる方だという実感があったので。倉持さんだったらこの映画は成立するかなと。
最初は僕もこの原作を映画にすることに、なかなか難しい橋を渡ることになるんじゃないかと思っていて。監督という立場だけじゃなく、自分が観る側として考えて、どこに柱があればこの映画は成り立つんだろうか、ということを、窪田さんや芦澤さん、そして倉持さんだけでなく、現場で袖を触れ合わせた方たちにお話しました。
──窪田さんと最初に対決するときの青いライト、あそこでこの映画のムードが決まったような気がするんですね。そのあと地下室の灼熱の赤いライトや蓮佛さんのラストの照明。そうした色彩設計もかなり計算されてますよね?
照明の菰田大輔さんに、ある程度自由にやってもらいました。これはほかの部所のスタッフもそうなんですけど、僕は監督として背伸びをするんではなく、むしろ最初から白旗を掲げて、プロフェッショナルな方たちにやりたいことをまずやってもらう。僕は、その場所を確保するのが監督の役割だと思っているので。それは役者さんもそうですね。
◆「蓮佛さんの表情を客席に浴びせたい」(齊藤監督)
──なるほど。
役者さんに「こういう風に演じてくれ」と、わりと解像度の高い演技を最初からオーダーしちゃうと、そこに囚われた状態の人間がただ現場にいるだけになるというか。僕が役者をする場合でもよくあるんですけど、それでよかった試しがないんですね。
なので、各部の方たちには、その職業に就いた頃の好奇心とかプロとしての挑戦を、この現場ではどうぞ遠慮なくやってください、と最初にお伝えしました。特に照明部さんはいろんな試みをしてくれましたね。やりすぎなときは話し合って、もうちょっと引き算しましょうか、とか。それはそれで健全かなと思いました。

映画評論家・ミルクマン斉藤
──いわゆるホラー的な照明は要所要所で出てくるだけで、やり過ぎない感じがすごく良かったですね。不穏な空気が漂い始めるなか、日常的な風景というか、例えば網焼きの鯵が煙り出したり、白子を引きずり出したり、そういうシーンで気味悪さを増していく。
そうですね。あれは、フルーツ・チャン監督の香港映画『三人の夫』(2019年)の冒頭にアワビが焼かれている描写があって。あれいいなと思って。原作にはないシーンなんですけど、白子をひとみ(蓮佛)が捌くっていうのは、さっきの男性性・女性性というのではないですけど、象徴になるなと。あと、焦げる。そういったところは嬉々としてやってました。
ただ、(ベテラン美術監督の)金勝浩一さんにお願いしながら、結実しなかったシーンもあって・・・。過去に人を殺めた経験のあるキャラクターの背景には、十字架を背負ってもらっているんですね。だから、最初のアパートや日本家屋も無理やり十字架にしてもらったんですけど、誰一人として伝わっていないっていう(笑)。
──私も正直、気づきませんでした(笑)。
そこはもう少しシンボリックに描いても良かったのかなぁと。映画『昼顔』(2017年)で、まさに十字架を背負うという西谷弘監督の演出があって、それを素晴らしいなと思って引用したんです。準備期間はたくさんあったので、こういうのがやりたいと金勝さんにはオーダーして。
でも、その伝え方の塩梅というのは、引きすぎても伝わらないし、露骨にしすぎてもなんか冷めてしまう、そのあたりは難しいなと思いましたね。でも、そういったロジカルなものを細やかに伝えたいというよりは、最初にお話ししたように「人の顔」を描くことで「家の顔」を描くべきというのはありました。

©2023『スイート・マイホーム』製作委員会 ©神津凛子/講談社
──なんといっても「家」がタイトルに冠せられていますもんね。ところで奈緒さん、近年めきめきと頭角を現していますが、彼女のキャスティングはどこから?
倉持さんの劇団の主演をされてたんです。その舞台を見て、奈緒さんなら演じ切ってくださるなと。原作だと年齢がもうちょっと上ですし、舞台では学生の役だったんで、原作との整合性はなかなか合いずらかったんですけれど、そういったものをすべて超越したなにかがある。
で、存在の引き算というものが重要で、ネタバレになるので詳しくは言いませんが、その存在感の匙加減というか、別に僕がオーダーしたわけじゃないんですけども、奈緒さんの表現の塩梅みたいなものが実に見事だったなと、仕上げのときに痛感しましたね。
──このところの奈緒さんの出演作を観てると、こいつちょっとヤバいぞ、っていうのがあるじゃないですか。女性の心理的な動機を描いている映画なので。奈緒さんも然りですが、蓮佛さんもとてもいい。最後、あの表情を見せるに至るというのはなかなかです。
そうなんです。今回の映画では、「目」と「蜘蛛」と「十字架」というのが、僕のなかにキーワードとしてあったんです。あの蓮佛さんのあの表情で最後、観客と目が合うというのが重要で。名前も「ひとみ」ですしね。
『殺人の追憶』(韓国の傑作サスペンス映画)のソン・ガンホじゃないですけど、最後にカメラ目線が来るというような、異常性を意識してああいうラストにしました。観客を見つめて欲しかったんですよ。窪田さんがそのリアクションをしてくれているけど、あの蓮佛さんの表情が出てる理由を客席に浴びせたいと。それって、狙ってできることではない気もしていて。
◆「お客さんに鍛えられないといけない」(齊藤監督)
──いやあ、あの顔は忘れられません。トラウマものです(苦笑)。
『零落』のとき、監督の竹中直人さんに「ラストシーンの表情は、最低な顔してくれ」って直前に言われたことが、すごく僕の心に残っていて。カメラがそこにあると、どうしてもよそ行きになるじゃないですか。役者を何年やろうが、見られている前提からは逃れられないので。そのとき、「最低な顔」というのはすなわち、人に見せないような部分だと僕は解釈したんです。
で、蓮佛さんにも似たようなお話をしました。各役者さんに言ったかも知れませんね。僕は監督としてのアイデンティティみたいなものはほとんどないので、自分が現場でいいなと思ったことをトレースしていくシステム。竹中さんにそう言われて霧が晴れるような感覚を受けたんで、その言葉をそのままお伝えした記憶がありますね。
──それでもしかし、最低といっても、ある種屈折した母性を感じます。それこそ中川信夫監督の『東海道四谷怪談』(1959年)のラストみたいな。あっちは天上に成仏するんで逆なんだけれども、そういう凄惨を突き抜けた美しさがやはりある。
そういう雰囲気はありましたね。蓮佛さんの表情だったり、子役の磯村アメリちゃんのエンドロール後の表情につながる「なにか」を感じてもらえたらいいなと思いながら構成しましたね。
──それが映画ですもんね。なんでも説明的じゃ面白くない。
そう、そうですね!

『スイート・マイホーム』の齊藤工監督(左)と映画評論家・ミルクマン斉藤
──それにしても近年、勢力的に映画撮られてますよね。あれだけ役者として出ていながら、今年は別府短編映画プロジェクトとして、短編映画『縁石 ふちいし』(主演:安部賢一)も控えている。
今、動いている映画が2本あって、実はもうクランクインしてます。その2本が落ち着いたらしばらくはないと思いますね。
──今後、原作モノのオファーも増えると思いますが・・・。
どうでしょうか?今回の映画制作を通していろいろ学ぶことはありました。キャスティングなどもデータ化されて、マーケティングの一種なんだなと。でもこれが日本映画の作り方のひとつということは分かっています。だからこそ今回は、わがままでそれを打ち破りたいと思っていました。
これまでは海外にデータを送って無料で出品できる映画祭があるので、21カ国くらいに送ったんです。自費も含めて半分くらいは現地に行ってそこで映画が拡がっていってました。だけど今回、それがそんなにできなくて。

「わがままでそれを打ち破りたいと思っていました」と語る齊藤工監督
僕はもっと作品に厳しいお客さんの目線に鍛えられないといけないと考えていて。だからやっぱりマーケティングベースの作品作りの危うさは感じています。モノを作るというクリエイティヴィリティと、情報データ、ロジカルさの良い調和というか、バランスは非常に難しいんだなと。
だからと言って、後ろ向きだけではないんですけど。こういう混乱のなかでこそ時代の危うさみたいなものは感じてるので、なんか良い作品は生まれるんじゃないかな。
──実際、インディペンデントでは面白くてチャレンジングな監督が実際に出てきてるのは工さんもよくご存じなのは知った上で話しますが、そこをもうちょっと商業ベースにのせていく、それこそATGみたいな弱小規模でもセンセーションを巻き起こしたりする、ある種の戦略みたいなもの。そういう団体というか、映画会社が少ないですよね。
今泉力哉さんと城定秀夫さんの『L/R15』(註)みたいな、小さなところでは起きているんですが、俳優組合がないように、日本って結託が下手ですよね。だから日本ではストライキが起きようがないというか。アメリカの方が自己主義なんだけど、こういうときには結託するじゃないですか。
※註:『L/R15』(今泉監督と城定監督がお互いの脚本を提供し合い、R15+のラブストーリーを2本を制作した、異色のコラボによるプログラムピクチャー)
それが日本だと逆で、パッと見た感じでは仲間意識があるようで、実は蓋を開けてみると自分のことしか考えられないというか、一枚岩になれないという脆弱さを感じてしまう。でも、意外とそういう状況だからこそ生まれるものも無くは無いなと。そこに心の拠りどころを持っていくしかないという気がしなくはないですけどね。
映画『スイート・マイホーム』
2023年9月1日公開
監督:齊藤工
出演:窪田正孝、蓮佛美沙子、奈緒、窪塚洋介、ほか
配給:日活、東京テアトル