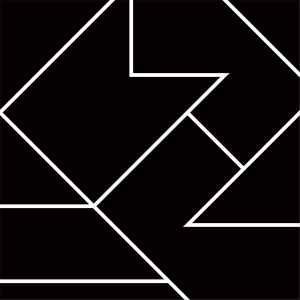見ているだけで元気がでるような、鮮やかな色柄の布で作られたワンピースやポーチ。
田賀朋子(たが ともこ)さんが運営するアパレルブランド「jam tun(ジャムタン)」の商品です。
jam tunは田賀さんが青年海外協力隊としてセネガル共和国(以下セネガル)に赴任したことがきっかけで生まれました。
jam tunができるまでと、商品に込められた田賀さんのセネガルへの想いを紹介します。
jam tunとは

jam tunはセネガルで使われている言語のひとつ、プラール語で「平和しかない」という意味で、あいさつの返事として1日に何度も使われている言葉です。
田賀さんは「支援ではないセネガルとのつながり」を形にするため、セネガルで親しまれている言葉を名前にもつブランドを立ち上げました。
ワンピース、パンツ、スカート、トートバッグ、ポーチなど、たくさんの商品がありますが、どれも素材はアフリカ布で、セネガルの仕立て職人が縫製しています。

まったく同じものが二つとないのも魅力のひとつで、同じ形のスカートも一つひとつ柄が違い、どれにしようか迷ってしまいます。
jam tunは常設店舗がないので、Instagramで期間限定店舗やイベント出展の情報をチェックしてください。
セネガルで出会ったアフリカ布

田賀さんは大学卒業後、イギリスの大学院で開発途上国の政治経済や貧困などの問題解決について学び、青年海外協力隊として西アフリカのセネガルへ2年間赴任します。
活動の中心は、首都から車で約9時間も離れているシンチューマレムという農村で、村に日本人は田賀さんたった1人。
けれど、アフリカ布で仕立てた服を着ている日は「どこで布を買ったの?」「どこで仕立てたの?」と声をかけられることが普段より増え、服がコミュニケーションの糸口になってくれました。
セネガルでは自分の好きな布を買い、それを行きつけの仕立て屋さんへ持ち込んで服を作るというオーダーメイドの文化が根差しています。
最初こそ、アフリカ布で作った服を「派手で少し苦手」と感じていた田賀さんですが、「次はどんな服を作ろうかな」とだんだん楽しみになっていったそうです。

セネガルで直面したゴミの課題

セネガルで生活していくなかで、田賀さんは村にカラフルなゴミが散乱しているようすを目にします。
従来、村の人たちは自然に還るものだけで生活をしていたので、ゴミの処理は自分たちで焼却するか家の外へ捨てていました。
そのため、ゴミの焼却場やゴミ収集の仕組みがなく、自然に還らないビニールなどのゴミは村の至る所に溜まっていきます。
カラフルなゴミの正体は、飲料水のパックに使われているビニールや仕立て屋さんが捨てた小さな布きれなど。
田賀さんは、ゴミを捨てることについて考えてもらうきっかけになればと、その小さな布きれとビニールのゴミを縫い合わせて、村の仕立て屋さんと一緒にバッグを作ります。

バッグは口コミで広まり、欲しいという人も出てきたため販売もスタート。
仕立て職人の新しい収入源にもなりました。
jam tunの田賀朋子さんに、これまでの経験やセネガルの魅力、アフリカ布でのものづくりについて、インタビューしました。
田賀朋子さんにインタビュー
jam tunが生まれるきっかけになったゴミのバッグ作り、そこから現在のjam tunへのいきさつについて、田賀さんにお話をうかがいました。
jam tunが生まれるまで
──もともと開発途上国の貧困問題などに興味があったんですか?

田賀(敬称略)──
はい、子どものころに「世界がもし100人の村だったら」というドキュメンタリー番組やユニセフのチラシで見た、同じくらいの年齢の子どもが働いたり、家がなくてマンホールの下で暮らしたりしている姿が印象に残っていたんです。
大学では違う分野について学んでいましたが、就職活動をする時期になって「やっぱり国際協力について学びたい」と思い直し、イギリスの大学院へ行くことを決めました。
──大学院卒業後に青年海外協力隊になることを選んだのは?
田賀──
イギリスの大学院ではフィールドワークがあまり無くて、知識は増えたけれど開発途上国の実態は知らないままでした。
理論上はこうすればいいとわかっているのに現実で解決していないのは、どこかに課題があって、それは現地に行ってみないとわからないのかなと感じたんです。
また、国連職員になりたいと思っていたので、その仕事をする前に現地のことを知っておきたいと思い、長期滞在できる青年海外協力隊を選びました。
──青年海外協力隊の任期が終わって日本に戻るとき、jam tunを始めることは決めていたんですか?
田賀──
いえ、決めていたらもっとスムーズにできたと思うんですけど(笑)
青年海外協力隊の活動中、一部の支援が本当に必要とする人に届いていない状況を目にすることもあって、国連職員になることをこのまま目指すのかどうか迷いながら帰国しました。
帰国してからは就職活動をするつもりでしたが、2年間セネガルで一緒に過ごし、仲良くなった人たちとのつながりを大切に続けていきたいと思い、セネガルで作ったポーチとトートバッグの販売を始めたんです。

jam tunという名前もなくて、地元矢掛の朝市で「セネガル雑貨」という看板で販売しながら、セネガルのことを紹介しました。
最初は上手くいかなかったらやり方を変えるか、やめるかという気持ちでのスタートでしたが、活動に共感してくれるかたなどが声をかけてくれるようになり、そこへ出展することを繰り返しているうちに、だんだん多くのかたに知ってもらえるようになりました。
支援ではない、対等な関係を
──jam tunの活動で「支援」や「フェアトレード」という言葉を使わないのは、どうしてですか?

田賀──
私にとって「一緒に仕事をする仲間」という感覚だからです。
セネガルで仲良くなった人たちに対して、支援する、されるという表現は私にはなじまなくて。
もともとフェアトレードやSDGsがやりたくて始めたことでもないし、今もそれを目指しているわけじゃない。
「対等な立場で、お互い楽しみながら」という自分の理想のつながりかたをしていくと、今やっている形になりました。
お客さんも「支援になるから」と買ってくれる人は少なくて、柄がおしゃれだから、着心地がいいからと買ってくれるかたがほとんどです。
──これからやっていきたいことはありますか?

日本のお客さんがセネガルの仕立て職人さんに、直接オーダーメイドできる仕組みを作りたいです。
日本ではオーダーメイドというとハードルが高いですが、セネガルでは子どももオーダーメイドで服を作るくらい身近なもの。
お客さんはお店に並んでいるものから選ぶより、本当に気に入ったものを選べるようになるし、どんな人が買ってくれるか知れるのは、仕立て職人さんのモチベーションにもなるんです。
セネガルで体験したオーダーメイドの心地良さをもっと日本に広めたいし、ただ商品を届けるだけじゃなくて、作る人と着る人、お互いをつなぐ役割をしていきたいですね。
おわりに
私もjam tunで何度か買物をしていますが、お店では接客中の田賀さんに代わって、初対面のお客さんが服のひもを結んでくれたり、着こなし方を教えてくれたりすることがあります。
そこは、田賀さんが大切にされている「つながり」が自然に生まれる、優しくて楽しい空間でした。
こんな空間がjam tunから世界に広がり、好きな服を買うことがいつの間にか国際協力や国際貢献につながっている仕組みがたくさん増えていくといいなと思います。