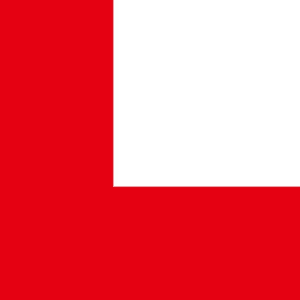徳川家康の厳しい選択だらけの人生を、松本潤主演で描きだす大河ドラマ『どうする家康』(NHK)。10月15日放送の第39回『太閤、くたばる』では、次回予告で茶々が告げた不穏なセリフの真相が明かされ、視聴者からはラスボス爆誕の恐怖と、今後の期待が混じった言葉が沸き起こった(以下、ネタバレあり)。

『どうする家康』第39回より、茶々(北川景子)が見つめるなか血を吐き苦しむ秀吉(ムロツヨシ)(C)NHK
■ どうする家康、茶々むき出した秘めた野望
側室・茶々(北川景子)が息子・秀頼を産んだことで、政への気力を取り戻した豊臣秀吉(ムロツヨシ)。秀頼を大切に思うあまり、ますます非情な振る舞いが目立つようになる。しかし、ほどなくして病に伏せるようになると、家康に「秀頼が無事に暮らしていけるならそれでええ。豊臣の天下は、わし一代で終わりだわ」と、天下を譲る決意を告げた。

『どうする家康』第39回より、秀吉が倒れる様を冷たく眺める側室・茶々(北川景子)(C)NHK
その後、血を吐きながら苦しむ秀吉の側にいた茶々は、「秀頼はあなたの子だとお思い? 秀頼はこの私の子。天下は渡さぬ」と秘めた野望をむき出しに。そして「あとは私に任せよ・・・猿」と言い聞かせると、秀吉は笑顔のような表情を浮かべながら逝去。茶々はその亡骸を抱きながら、思いがけず涙を流すのだった・・・。
■ 「秀頼はあなたの子だとお思い?」の答え
先週の予告で流れた、茶々の「秀頼はあなたの子だとお思い?」という爆弾発言。長年子宝に恵まれなかった秀吉の子を晩年に、しかも2回も身ごもったため「秀頼は不義の子では?」という憶測は、昔も今も語られ続けている。ちなみにその父親候補には、石田三成も入っているのだが、オタク気質&秀吉の忠犬な中村七之助版三成の場合、その可能性はゼロだろう。

『どうする家康』第39回より、病床の秀吉(ムロツヨシ)を看護する茶々(北川景子)(C)NHK
というわけで「秀頼は誰の子なのか?」問題に、大いに注目が集まった39回。その真相は不義の告白ではなく、「あなたの子でもあるけど、それ以上に私の子」という、天下人の母宣言だった。そしてこれはとりも直さず、秀吉の天下を受け継ぐという盟約をコッソリ交わした家康と、将来の全面対決が避けられない状態になったことを意味する。
この発言が出た瞬間、SNSでは「茶々、死ぬ間際の秀吉にラスボス宣言!」「『あとは私に任せよ、猿』と言うの、茶々の言葉であり、お市の言葉であり、母の夢、私の夢、ぐちゃっと混ざっているのがほんと茶々」「父親が違う云々の問題じゃない。それ以上に恐ろしい呪いの言葉だった」など、いろんな意味でビビリ上がる声があふれた。
■ 秀吉の死に涙も、茶々が見せた複雑な感情
こんな最後通告を、冷たい顔と声で秀吉に突きつけた茶々。しかし意外にも秀吉が浮かべた表情は、絶望でも怒りでもなく、不敵な微笑みだった。これには「絶望すると思ったら、ならばやってみろとばかりにニヤリと笑ったままくたばるムロ秀吉」「『残念でしたー、もう天下は徳川さまにやっちまった後だでよーw』とそんなふうにも取れる」など、さまざまな推察が。

『どうする家康』第39回より、亡くなった秀吉(ムロツヨシ)を抱きしめ涙する茶々(北川景子)(C)NHK
そして茶々が秀吉の死に涙を流す場面では、「絶望させるつもりが微笑まれ、涙を流すのね茶々。憎み愛した男の死に」「憎悪一辺倒じゃない複雑な感情があったんだな」「自分の復讐のためにとんでもない言葉を放ち、しかし寄り添い続けた情もあって泣く。怪物だよ茶々」など、戸惑いと同情の混じった言葉があふれた。
これまで大河で描かれてきた秀吉と茶々の関係は、愛情のあるものから、完全に踏み台扱いまでいろいろだが(個人的には、『真田丸』で竹内結子が演じた、愛も憎しみも感じない空虚な茶々が最も不気味だった)、今回の北川茶々のように「踏み台だと思っていたけど、自分が思っていた以上に死なれたら悲しい」という複雑な感情を見せてきたのは、珍しいパターンに思う。
こうして本作のラスボスポジションを盤石にした茶々だが、これから作間龍斗が演じる秀頼は「圧倒的なオーラを放つ」というキャッチフレーズが付いている通り、なかなか優秀なキャラクター設定になる模様。果たして彼は、ラスボスをたしなめる存在になるのか? それとも2人そろって悲劇の燃料を投下する立ち回りとなるのか? 豊臣親子が家康の天下に待ったをかける、その日を心待ちにしよう。
『どうする家康』はNHK総合で日曜・夜8時から、BSプレミアムは夕方6時から、BS4Kは昼12時15分から放送。10月22日放送の第40回『天下人家康』では、秀吉逝去後に家康がどんどんその存在感を増していくのと同時に、石田三成(中村七之助)と確執が生まれていく様子が描かれる。
文/吉永美和子