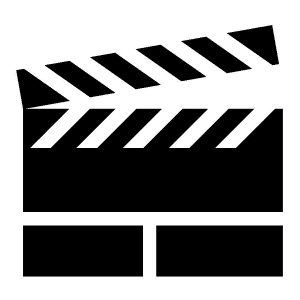はじめに
今月の新作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』。マーティン・スコセッシ監督の新作にして、監督作品の二大俳優とも言えるロバート・デ・ニーロとレオナルド・ディカプリオがついに共演。演技怪物の激突を目撃します。1920年代のアメリカ・オクラホマ州で次々に起こるアメリカ先住民オセージ族の不審死。石油利権から始まった連続殺人事件。アメリカ史上最も闇深い歴史を暴く作品です。
タイトルの意味とは?
『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』のタイトルは、映画で一言しかセリフに出ません。「フラワームーン」とは何でしょうか?原作はデイヴィッド・グラハムによる同名ノンフィクション。日本語訳は『花殺し月の殺人』。オセージ族の土地では4月になると平原に美しい小さな花が咲きます。しかし翌月5月になると、その小さな花より丈の高い草が生え、太陽光と水を奪って、花は折れ、やがて枯れてしまうと。オセージ族はこの5月を「花殺し月」と呼ぶそうです。後から生えてきた草が元々、生えていた花から栄養を奪う、非常に本作の物語を表しているこの「花殺し」。この5月「花殺し月」に起こった2件の殺人事件から、次第にオセージ族の不審死は相次ぎ、連続殺人事件へと発展していきます。
本作の背景
『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』の物語の背景をまず説明いたします。映画ではロバート・デ・ニーロ演じるヘイルが、レオナルド・ディカプリオ演じるアーネストに簡単に説明するだけで背景説明を済ませていますので、混乱された方もいらっしゃったかもしれません。
時は17世紀、オセージ族は他のアメリカ先住民族同様、元々持っていた広大な土地を合衆国に奪われ、狭い土地に追いやられ、その後、居住区を転々とする事になります。映画冒頭では、オセージ族長や大人たちが子供たちがこれから「白人」として生きなければならない事を嘆きますが、実際、合衆国はオセージ族に英語の名前を当て、英語を覚えさせ、教会に通わせる「白人同化」を行いました。最終的に合衆国政府は現在のオクラホマ州の一部を、オセージ族保留地として割り当てる事になりますが、ここがポイントで、その土地割当の際、オセージ族の代理人はある条項を土地割当の合意書に入れ込みました。それは「地下に埋蔵される鉱物はオセージ族が権利を有するものとする」というものでした。賢いオセージ族はその居留地の地下に石油が眠っていることをすでに知っていた。そんな事とは露知らず合衆国はドヤ顔でこの同意書にサインをした訳ですが、結果、オセージ族は正当な理由で石油の権利を獲得しました。
ここでようやく映画と繋がります。映画冒頭では、今までの西部劇では見た事がない裕福なアメリカ先住民族の暮らしが描かれます。スーツを着て、自動車も持っていて、驚くのはオセージ族の人が白人、アフリカ系を使用人として雇っている様子ですね。我々が西部劇と聞いて想像する、先住民族と白人の関係が逆転したような世界観が提示されます。この逆転の世界は最近、どこかで見ましたね。来年、おそらく本作とアカデミー賞を争う事になる『バービー』あれも男女、強者と弱者の関係が逆転した世界観が描かれましたが、とても似ているんですね。しかも本作と『バービー』どちらも同じ撮影監督ロドリゴ・プリエトがやっているという、本当に何でも撮れてしまう天才だなと思います。
話が逸れました。冒頭では、石油の権利によって裕福になったオセージ族の人々が、メディアによって過剰に報道される様子も描かれます。その報道によって白人からは不平不満、「インディアンが我々、白人を奴隷のように扱っている」と不満が出たわけです。そこで考えた合衆国は後見制度を悪用します。この映画の中でもオセージ族の女性モリーが、お金を使う度に、白人の元に行って「何に何ドル使うのか」を報告しているシーンが2回出てきます。オセージ族のヘンリーという男性が、銀行で「俺のお金だろ!」と叫ぶシーンもありました。
ひどい話ですが、オセージ族は自分のお金にも関わらず、自由に使う事ができませんでした。合衆国の言い分は、オセージ族は「人間」として能力がない未熟な部族なので、我々白人が資産を管理しないといけない、と。オセージ族は白人の後見人の管理下のみお金を使う事が許された。自分のお金、しかも正当な契約書上の条項によって認められた権利に基づいたものですが、お金が自由に使えないと。トンデモナイ話ですね。モリーが後見人の前で自らを「無能力者」と言うのは、そういう意味です。白人の後見人の中には管理しているオセージ族の資産を着服する者もいたそうです。
劇中、少し分かりづらいのはディカプリオ演じるアーネストが棺を購入する時に「俺にオセージ料金をふっかける気か!」と怒るシーンがあります。白人の商人たちは後見人と組んで、食品、日用雑貨を裕福なオセージ族に売る際に法外な値段を付けて売ったと。このぼったくり料金が「オセージ料金」の意味する所です。「フラワームーン」は、5月になると丈の高い草が生え、先に生えていた小さい美しい花々の栄養を取ってしまう。お分かりの通り、小さい花はオセージ族で、丈の高い草は彼らをあらゆる方法で搾取をしている白人を指します。以上が本作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』背景です。これだけご存知でしたら、ノイズなくお楽しみ頂けると思います。ここからは物語について具体的にまとめていきます。
あらすじ
映画『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』は以上の背景から繋がるように、白人たちが搾取をする裕福なオセージ郡に、アーネストという男性が訪れる所から幕を開けます。彼はオセージ郡の「キング」と呼ばれている牧場主のヘイル。ロバート・デ・ニーロ演じるヘイルの元を訪れ、運転手の仕事に就く……ある時、オセージ族の女性モリーと出会い、恋に落ちていきます。
原作の改変
まず本作の企画が発表され、予告とかティザーが公開された時に多くの観客は驚きました。何に驚いたかと言うと、原作と全然、違うという事ですね。原作『花殺し月の殺人』は、ミステリーとして進行します。本作に該当する箇所では、1章目はモリーの視点を軸にオセージ族の不審死、そこから連続殺人事件が発生する事件の実録。2章目はFBIの前身となる捜査局の捜査官ホワイトによる捜査劇と。次第にオセージ群に隠された陰謀が明かされるというものでしたが、今回の映画は原作で最後に明かされる犯人たちを主役にした、視点が真逆の改変を行いました。
これには驚きながら、本作は実際の、現実に起きた凄惨、悲惨な事件をある種、ミステリーというエンタメのジャンルで消費させないという強い意志を感じる一本です。とにかくこの『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』は、冒頭から、最後の最後の最後まで観客にエンタメとして、娯楽的な映画体験として、この実際の事件を消費する事を拒みます。そして本作を本国で鑑賞する多くの白人観客の視点を、主役にした悪役の視点と重ねる事で、どこかアメリカの闇の歴史、かつて白人が犯した罪を白人の観客に向かって告発するような映画にした改変だと僕は感じました。
同時に、犯人・悪役を主人公にしたというのは当然、スコセッシ的ですね。この『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』で相次いで起こるオセージ族不審死と殺人事件の首謀者はロバート・デ・ニーロ演じるヘイル、そしてヘイルの下、アーネストは叔父ヘイルの言いなりになって犯行を重ねていきます。スコセッシ的というのはミステリーだった原作を「下っ端ギャング」「下っ端犯罪者」を主役としたギャング映画にしたということですね。
有名な『グッドフェローズ』はイタリア系のマフィアにおいて、自らの人種から絶対に幹部になれないアイルランド系の下っ端ギャングを主人公とした犯罪映画でした。続く『カジノ』もカジノの運営を任された主人公は、やはり人種、ユダヤ系という事でよそ者扱いをされながら、カジノの大元にあるシカゴの犯罪組織には逆らえない人物でした。常にスコセッシの犯罪映画は、組織における絶対的な力関係、時にそれは人種が理由の力関係、それを前提とした下っ端犯罪者の物語でした。
今回、スコセッシが原作を読んで目につけたのが、原作では犯人の一人、脇役に過ぎなかったしょうもない犯罪者の、しかも子分、下っ端。おおよそ他の監督が仮にも本作をギャング映画的解釈をしたとしても、主人公は親分のヘイルにしますよ。実にこの主役のピックアップはスコセッシ的で、スコセッシは自分の今まで描いてきたフィルモグラフィに原作を近づけて映画として翻訳した改変だったと思います。
本作の悪役
過去の下っ端ギャング映画、『グッドフェローズ』、『カジノ』は少なからず観客を、その犯罪者である主人公に感情移入させて、ある種、観客を主人公の共犯関係にして、観客も主人公と一緒になってその犯罪・成り上がりを楽しめる感覚がありましたが、が、今回の『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』の主人公アーネストは感情移入がかなり難しいキャラクターとして造形されています。とにかく「平凡」平凡としか言いようのない“凡”すぎる悪。凡庸な悪。ただひたすらに叔父ヘイルの言われるがままに犯罪をする。愛嬌と、その素直さで人間としてギリギリ認められるくらいで、全く過去のスコセッシ映画にあったような観客を惹きつける吸引力がない、魅力がないというのが今回の主役アーネストの造形です。
元々このアーネストは、本作で捜査官ホワイトを演じたジェシー・プレモンスが演じる予定だったそうですが、レオナルド・ディカプリオが「やりたい!」と役を交換した形になったと。なのでレオナルド・ディカプリオの演技も、今までにはないような、弁も立たず小ずるいだけの意志のない平凡な小悪党に終始していて、どこかレオナルド・ディカプリオがジェシー・プレモンスのモノマネをしているようにも見えてきますね。そしてレオナルド・ディカプリオずっと変な顔しているんですよ。『ウルフ・オブ・ウォールストリート』とか元々、セリフに力が入ると、顎がしゃくれる表情の作り方をしていましたが、ずっとこのアーネスト=ディカプリオはしゃくれていますね。あの…ディカプリオがジャック・ニコルソンのモノマネをしている画像ってご覧になった方いらっしゃいますかね?あの顔をずっとしています。吹替を作るなら一人称は「おいら」ですね。今までのスコセッシ作品のディカプリオ像を覆すような、とっても変で平凡な悪を体現している、見事な演技・存在感だったと思います。
しかし『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』において決してアーネストだけが飛び抜けて「平凡」という訳では全くなく、今までのスコセッシ・ギャング映画とは異なり全員が「しょーもない」平凡で自分の金と保身しか考えていない人物です。最もキャラクター配置的に「崇高な悪」と描ける余地のある陰謀の首謀者、「キング」ことロバート・デ・ニーロ演じるヘイルもとても凡庸な悪です。全く格好良くはない。物語は、主人公アーネストとボスであり叔父のヘイルとの関係性を一つの軸にします。
今やディカプリオと言うとスコセッシ作品の看板俳優の一人ですが、元々ディカプリオをスコセッシに紹介したのはデ・ニーロで、デ・ニーロとディカプリオは『ボーイズ・ライフ』という映画で共演して、それがきっかけで今に至っている訳です。この『ボーイズ・ライフ』もディカプリオ演じる主人公と、非常に暴力的な父親デ・ニーロとのドラマでしたが、この『ボーイズ・ライフ』の延長線上に、本作のアーネストとヘイルの擬似的な親子関係があるようにも見えます。この犯罪集団における擬似親子関係もスコセッシ作品的で、最も分かりやすいのはまさしくディカプリオが主人公を演じた『ギャング・オブ・ニューヨーク』の主人公と、ギャング団のボス=ブッチャーとの関係性が類似すると思いますが、そんなブッチャーとヘイルは天と地の差です。
ヘイルは一見、気の良さそうな街の偉いおじさんという感じですが、どのコミュニティにも良い顔をして、自分を「キング」だと言う、結局、自分のお金の事しか考えていない。ヘイルはオセージ族の言葉を巧みに用いてオセージ族のコミュニティでも相談役としての地位を獲得し、一方、アーネストには聖書を引用して、神の言葉で彼を操ろうとする。この悪役の造形も『ケープフィアー』というスコセッシ作品で、デ・ニーロが演じた悪役とそっくりですね。この悪役も聖書とか、詩を引用して主人公の娘を誘惑する自分を神だと思い込んでいる悪魔的な存在でした。とってもベースは似ているんですが、やはり平凡と、結局、神の言葉も、聖書の引用も自分の保身、自己正当化、自分のお金のためという、神の言葉を使って、自分は神様気取り、王様気取りですが、観客の目には薄っぺらい凡庸な悪としか見えないという悪役がヘイルでした。
スコセッシは過去に、犯罪者に憧れた青年による成り上がりを、高揚感を持って描いてきた監督でしたが、前作『アイリッシュマン』から続き、本作でも犯罪者がいかに平凡なものかという事を描きます。『アイリッシュマン』は本作とキャラクターの配置、物語展開が似ている、『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』と対になっている作品だと思いますが、『アイリッシュマン』もデ・ニーロ演じる主人公フランクは、サラリーマン的というかボスに言われたことを言われた通りにやるだけの平凡な殺し屋でした。そのスタンス故に大きな罪を背負ってしまう。このフランクは本作のアーネストに重なると思います。平凡な悪こそが最も怖く、最悪の事件を起こしてしまう。システムの歯車になる事の悪と平凡さを、スコセッシはキャリアの後期で描こうとしてます。
本作の恐怖
『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』は、『アイリッシュマン』ととても似ています。何かと何かに引き裂かれる「板挟み主人公」というのもスコセッシ作品の頻出モチーフです。『アイリッシュマン』において、ボスの命令に従うだけの主人公は、ボスの命令と、一方で暴走する親友と愛する娘に引き裂かれます。スコセッシ作品を初期までさかのぼると、スコセッシの自伝的な青春映画『ミーン・ストリート』もこのモチーフで、主人公は、まさしく本作と同じく叔父ですね。叔父である犯罪組織の幹部と、暴走する親友との間に引き裂かれる。
サブチャンネルのPodcastではスコセッシ監督の生い立ちまでさかのぼりまして、彼がストリートのギャング、一方で教会、暴力・犯罪と宗教、その二つに引き裂かれながら映画に没頭していった幼少期と、この何かと何かに引き裂かれる主人公というモチーフに重ねました。本作でもアーネストは、ボスである叔父のヘイルと、一方で愛する妻モリーとに引き裂かれていきます。中盤以降になるとモリーが全てを見透かしたかのようにアーネストに接する瞬間が出てきます。まさに神的に。かつてスコセッシがギャングに憧れ、暴力の世界に魅了されながら、同時に神父を目指し、神に近づこうとした。スコセッシも青年時代、暴力と神に引き裂かれた人物でしたが、その自身の半生を繰り返すかのようにアーネストも引き裂かれていきます。
ただ本作の引き裂かれ方は非常に緻密で、怖いです。怖い。この映画は一言で言うと「怖い」んですね。今まで物語の要素をまとめてきました。これだけ見ると、どう見てもギャング・犯罪映画ですが、鑑賞中の感覚はホラー映画に近いと言っても良いものなんですね。この怖さは、大いに本作の語り手によるものです。スコセッシ作品、『グッドフェローズ』にしろ、『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』にしろ、過去作は成り上がっていく主人公が観客に語りかけ、その主人公のモノローグを映画のエンジンに、観客は成り上がりの共犯者として映画に巻き込まれていく構図がありました。本作の語り手は過去作のように主人公アーネストではありません。モリーでしたね。被害者です。
とても怖いのは、アーネストがヘイルと出会って、これから犯罪の道を進んでいくという時に、急にスクリーンはモノクロになって、オセージ族の記録映像、そしてそのオセージ族が相次いで不審死を遂げている映像が差し込まれます。その時に観客に語りかける声の主はモリーです。暴力的な映像を見せながら、どう見ても殺人なのに「捜査されず」「捜査されなかった」「No investigasion」と、モリーの怒りと悲しみが混じったような小声が観客に突き刺さります。これがとても怖いです。もちろんここで見せられる暴力の映像が乾いた、とても冷徹なものであるという事もありますし、モリーがささやくように「捜査されなかった」まるでゴーストストーリー、怪談を語っているかのような、稲川淳二さんの世界、耳にスッと入ってくる「捜査されなかった」「No investigasion」このモリーの語りが、この映画の土台、通奏低音になっているから怖いんだと思います。どんなにこの後、アーネストがモリーと出会って幸せな結婚式を迎えても、どこか観客の脳内にはモリーのこの語りが刻まれている。この怖さ。ホラーですよ。
驚いたのは公開直前のマーティン・スコセッシ監督のインタビューで、本作の非常にゆっくりとした編集テンポは、何とアリ・アスター監督のホラー作品、ジャック・ターナー監督の古典的な怪奇映画、ホラー映画を参考にしたおっしゃっていました。あながち僕のホラーを観ているような感覚は的外れではないと思うんですね。ホラー映画のように、モリーは追い詰められ、アーネストもじっくりじっくり板挟みの状態になっていく。
普通、こういった犯罪映画で主人公が一線を越えてしまう瞬間は、劇的にドラマチックに描かれることも多いですが、本作はぼーっとしていると一線を踏み越えた瞬間を見逃してしまうくらい、静かにヘイルの魔の手がアーネストに近づいています。実際は、モリーが姉妹を亡くした、そのお葬式でヘイルがアーネストを呼び出して「道筋を立てろ」と言うんですね。何の道筋か?後継される石油の権利、受益権の道筋だと。モリーの家族が亡くなってしまえば権利はモリーに集中する。夫であるアーネストはモリーの権利を継ぐことができる。物凄い怖いことをヘイルは言っていますが、一見、普通のビジネスの話のようにアーネストに語る。この怖さ、冷たい、ビジネス的だからこそ怖いという、この『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』の怖さはとてつもないものです。これぞスコセッシの腕だなと噛み締めました。
ネタバレ注意
ここからヘイルの陰謀はどんどんアーネストのコントロールできない範囲に拡大していくことになりますが、中盤以降の展開にも言及しますので、ここからは絶対に本編ご鑑賞後にご視聴ください。撮影、衣装、美術、俳優の存在感、どこをとっても最高のクオリティの作品だと思います。ぜひ劇場でお見逃しなきよう。
!!以下は本編ご鑑賞後にお読みください!!
原作から追加された要素
尤も本作の主人公アーネストは自分が引き裂かれていることにすら気付いていないほどに平凡、凡庸というのが、この映画の怖さではあるんですが、そんな愚かなアーネストにいよいよヘイルの企みがコントロールできないと思い知る瞬間が訪れます。モリーの妹の家が爆弾によって爆破されるという犯行が行われた瞬間です。ここでモリー含めオセージ族の人々が「タルサ虐殺がここでも起こる」と叫びます。
少し分からなかった方もいらっしゃったかもしれません。原作に無い要素として、この映画では「タルサ人種虐殺」が重要な事件として劇中登場します。「タルサ人種虐殺」というのは1921年同じくオクラホマ州で起こったアフリカ系への人種虐殺です。なぜ今回この事件が映画に出てきたかというと、非常にオセージ族連続殺人事件と背景が似ているからです。本当に簡単にご説明すると、南北戦争後、奴隷だったアフリカ系の人々がオクラホマ州、元々アメリカ先住民族の保留地とされていた場所に移住しました。そこでアフリカ系の人々はビジネスを成功させ移住した街は大発展を遂げました。南部の金融の拠点「ブラック・ウォール街」と呼ばれるほど、裕福なアフリカ系の人々が住む街に繁栄をしました。そんな中、それを不満に思った白人たちの嫉妬心が爆発して何百人も虐殺されてしまうという人種虐殺事件に発展したという訳ですね。
HBOドラマ版の「ウォッチメン」でこの「タルサ人種虐殺」がかなりフィーチャーされていましたので、ご存じの方も多いと思いますが、本当に酷い話で、ウォール街を焼きうちしたり、飛行機から爆弾を落としたりした訳ですね。片やオセージ族、方やアフリカ系と人種は違いますが、背景が似ていて当時のオセージ族がこの人種虐殺を見て、自分の街で起きている事と重ねない訳がないと。想像できないほどの大きな恐怖が、この事件を言及することで伝わる作りになっていました。
神となるモリー
スコセッシの過去のギャング映画とは全く違う、ずっとホラーのような恐怖に観客とモリーは晒されます。冒頭のモノローグがこの映画の恐怖の土台を作っていると申し上げましたが、モリーのモノローグは中盤にも反復します。アーネストとモリーに新しい子供ができたと、その子供の誕生を祝いの席で、そこに参列している白人たちが、モリーを見ている様子、これも怖いですね。
モリーは「オセージ族は標的にされている」と語ります。糖尿病を抱えていたモリーは病の床でヘイルが手配したインスリンの注射を受けることになりますが、現実、ヘイルは街の医者などあらゆる人々と内通していて、酒や薬に毒を混ぜることでオセージ族の人々を病死に見せかけ殺害していたそうです。モリーの体調がどんどんと悪くなるにつれ、アーネストにとってモリー全てを知っている神的な存在に見えてくるような描写をしています。現実世界とオセージ族の神=ワカンダの世界、生死を彷徨うことで、神に近づいたのか全てを見透かしたような発言をするようになります。
ヘイルが自分の牧場が燃やした夜、モリーはアーネストに「次はあなたよ」と言う。幻想なのか、現実なのかベッドに近づいたヘイルに「あなたは本物?」と言う、まるでヘイルに向かって「あなたは本当にオセージ族の味方なの?」と言っているように観客は聞こえる。何度も『アイリッシュマン』と本作は似ているという話をしてきましたが、終盤になると、モリーはまるで『アイリッシュマン』における主人公の娘ペギーと重なってきます。
『アイリッシュマン』において、主人公の行動、様子をじっと見つめる神的な存在がいました。それが主人公の娘です。扉の間からじっと主人公を見ている。主人公が重大な殺人を犯した後、娘は主人公に「なんで?」と言う。違う文脈から出た「なんで?」という発言ですが、主人公と観客にとっては「なんで殺したの?」と、まるで罪を問うているかのように聞こえる。終盤、主人公が娘に会うために銀行を訪れた時、まるで銀行の受付を教会の告解室のようにスコセッシは切り取りました。ここで観客は気付きます、娘は、ペギーは主人公をずっと見ている神なのだと。この『アイリッシュマン』と本作の全てを見ているモリーは重なりますね。どんなに題材が変わろうと、やはりスコセッシは暴力の世界と、神、それは時に娘の姿をしていて、時に妻、オセージ族の女性の姿をしている、その二つに引き裂かれる登場人物を描こうとしています。本作も同じでした。
アンチ西部劇
『アイリッシュマン』は徹底的に懺悔の映画でした。というかボスの言いなりになって、組織のシステムに呑み込まれたことで神的な存在の娘に見捨てられ懺悔の機会を失った哀れな殺し屋の物語でした。本作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』は逆でしたね。捜査官ホワイトによって逮捕されたアーネストは、ヘイルの悪事を法廷で証言しろと迫られます。ここでまた怖いシーンで、弁護士に呼ばれて家に行くと、ヘイルの家族だったり、ヘイルと組んでいた街の有力者たちが勢揃いして、アーネストを見ているという…モリーが子供誕生を祝う会で晒された白人の視点の繰り返しですね。皆が見ている。お前もヘイルの仲間だったの?という恐怖もありつつ、このショットの美しさの反面、恐怖は底知れないものがありました。
お話それましたが、『アイリッシュマン』と逆を行くのは、アーネストは『アイリッシュマン』の主人公と異なり、罪を告白しますね。一度、証人になることを拒否しますが、娘の死をきっかけに罪を告白します。ヘイルの悪事を暴きます。『アイリッシュマン』の主人公は告発しなかった。逆をいきました。現実でもアーネストは「もう罪を背負いきれない」と、最後にヘイルを裏切って罪を法廷で告白するんですね。
僕は、スコセッシは原作のアーネストのこの最後の告白を見て、アーネストを主人公に映画化しようと決めたと思った確信しています。僕がこのシーンを見て思い出したのは、エリア・カザン監督の『波止場』です。この映画はスコセッシが大大大好きで、幼少期に100回見たと言っている映画で、僕もそれを知って観た、ある種、スコセッシに教えてもらった映画なんですが、この『波止場』という映画も波止場を仕切っているギャング団のボディーガードをしている主人公が、家族の死をきっかけに最後に法廷でギャング団の罪を告発するんですね。このシーンとダブりました。スコセッシは『波止場』をやりたくて、原作では犯人の一人にしか過ぎないアーネストを主役にして映画にしたんじゃないかと思います。
システムに最後の最後で立ち向かった、最悪の男の最後の反抗。今までの嘘を認めながら、妻モリーへの愛は真実だと告白する、と。いかにもな西部劇的なセッティングの中、最後に白人男性に罪を告白させて終わると。本作は白人対アメリカ先住民という、古典的な西部劇の対立構造を流用しながら、白人にヒーローはいない。加害者しかいない。語り手モリーの怒りと恐怖が混じったモノローグは、観客へ与える加害者性を際立てる。
脚本を担当したエリック・ロスは、レオナルド・ディカプリオが演じたアーネストのキャラクターについてモンゴメリー・クリフトが生きていたら演じたかった役と表現します。この発言ではたと気付きましたが、本作の根っこにあるのは西部劇の古典名作『赤い河』ですね。『赤い河』ではジョン・ウェイン演じる牧場主、ヘイルと同じく牧場主の元、このエリック・ロスの言うモンゴメリー・クリフト演じる青年が働いている。エリック・ロスはジョン・ウェインにヘイルを重ねて、モンゴメリー・クリフトにアーネストに重ねていたと思うんですね。『赤い河』ではこの二人が擬似的な親子関係になり、圧倒的な父性を見せるジョン・ウェイン=牧場主に、モンゴメリー・クリフトは反抗する。この疑似的な親子主従関係を、本作に重ねながら、『赤い河』では他の西部劇と同じく、アメリカ先住民は一方的な悪役として描かれました。
多くの西部劇ではアメリカ先住民は野蛮な悪役でしたが、本作では全く逆転させて、今までヒーローだった白人は最悪な加害者でしかなく、最終的に罪まで告白させる。本作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』はスコセッシが撮った初めての西部劇と言えると思いますが、徹底的なアンチ・西部劇と言えると思います。凄い映画だなと思いました。白人ではない日本人だから、モリー側に立っているつもりもなかったです。僕は日本において白人側ですよ。日本にも少数民族はいます、人種虐殺はありました。この映画を見て、オセージ族側に完全に立てる人は少ないんじゃないかなと思います。
エピローグについて
普通の劇映画だったら、罪を告白し、自分の心の汚れを落とし、愛は真実だと語ったアーネストは最後、妻モリーと結ばれるかもしれません。それこそモンゴメリー・クリフト主演の『陽のあたる場所』では罪を犯したモンゴメリー・クリフトが最後には、恋人と結ばれます。そんな甘いことはしてくれない。モリーはアーネストを許さない、モリーから軽蔑のまなざしを受けて終わる。徹底的にエンタメとして消費されることをこの映画は拒みます。
捜査官ホワイトの視点では、さぁ事件が解決した!正義は勝ったぞ!で終わらせてくれないんですね。『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』のエピローグも鋭くて、この事件解決の一部始終全てがJ・エドガー・フーヴァーFBIの創始者によってプロパガンダに利用されて終わるという、観客に隙を与えない。お前ら感動してんじゃねぇぞ!と、お前ら白人はこの事件すら利用しただろ。後にJ・エドガー・フーヴァーが本作の事件解決を利用して、FBIを設立し、そのFBIを職権濫用します。その辺りはまさにレオナルド・ディカプリオがフーヴァーを演じた『J・エドガー』に続いていきます。フーヴァーはオセージ族連続殺人事件解決の過程を、ラジオドラマにしてプロパガンダに利用しているというエピローグです。徹底的に白人の罪を追い込む構成にしている容赦のなさですね。
このエピローグが無かったら、結局、白人のスコセッシが現実の凄惨な殺人事件を白人主人公の感動話にしただけじゃんとなる所に、この隙のなさ。最後にスコセッシ自ら、モリーの追悼文を読み、オセージ族の魂の鼓動とも思える、心の叫びとも思える太鼓の音で映画を締めくくる、この構成の隙のなさ。恐ろしいクオリティだなと思いました。
エンドクレジットではオセージ族の歌と一緒に、ハエの音、虫の声が流れます。『沈黙-サイレンス-』でも劇中、ずっとハエが飛んでいますが、これは「神」ですね。人間の営みとは無関係にただひたすら鳴く虫、飛ぶハエ。そこに神を『沈黙-サイレンス-』の原作者遠藤周作は象徴させたと。劇中も中盤からずっとハエがアーネストの周りを飛んでいますが、自然という神がお前を沈黙して見ていると。上に上がっていくカメラから、オセージ族の神ワカンダを虫に象徴させ、ある種、被害者を追悼するようなエンディングに見えました。
さいごに
『沈黙-サイレンス-』から『アイリッシュマン』、そして本作と明らかにスコセッシは、編集の盟友セルマ・スクーンメイカーと編集のテンポを落として、今まで『グッドフェローズ』で10分で語っていたシーンを敢えて40分に拡張したり、スローな編集に意図的にしていますね。これに好き嫌いあると思うんですが、僕は本当に3時間26分が心地良くて、早く感じたなんて全く思いませんけど、遅いんだけど何故か見ていられる、何故かもっと見たいと思わせる豊かなスコセッシ時間を堪能できる作品になっていて、僕は後期スコセッシの編集大好きですね。
この三作品『沈黙-サイレンス-』、『アイリッシュマン』、『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』は「歴史の闇レクイエム三部作」と呼びたくて、『沈黙-サイレンス-』は歴史から葬り去られていた棄教したキリスト教徒へのレクイエム、『アイリッシュマン』は懺悔できない犯罪者へのレクイエム、本作は今まで西部劇で悪役として殺されてきた、実際にも虐殺されてきたアメリカ先住民族へのレクイエム。そして『アイリッシュマン』はギャング映画というジャンルを終わらせるくらいの後悔に満ちたパワーがありましたが、本作は西部劇というジャンルを終わらせるくらいの、今まで西部劇のヒーローだった白人の加害性を暴いた作品になっているように見えました。
スコセッシの初長編監督作『ドアをノックするのは誰?』という作品では、スコセッシ自身を反映した主人公が、西部劇『捜索者』の話で女性と意気投合する様子が描かれましたが、そこから56年後の本作で、そんな西部劇を断固拒否するような本作に至ったというのは、いよいよスコセッシも映画の歴史を閉じ始めてきているんだなぁと感慨深くなります。今年ベストの一本でした、今月の新作は『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』でございました。
【作品情報】
『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』
劇場公開日:2023年10月20日(金)
©2023 20th Century Studios.

茶一郎
最新映画を中心に映画の感想・解説動画をYouTubeに投稿している映画レビュアー