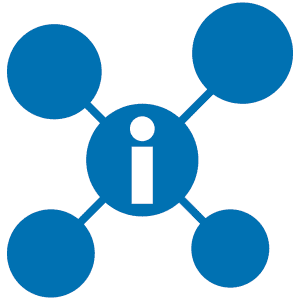■懐かしき商都の味 麺で隆盛「まだ進化」
三軒長屋の1軒を改装してラーメン店の看板を掲げた。店名は地元の易学者に相談。「昭和に栄える店」との願いを込めた。
高度経済成長が始まった頃の1957年7月2日、「盛昭軒」が茨城県下館市(現筑西市)に開店した。店主の松本明(故人)は23歳、フミ子(85)は19歳。半年前に結婚したばかりの若夫婦だった。
スープは鶏ガラベースのしょうゆ味。チャーシューは当時、豚肉が高価だったため、鶏肉にした。鶏油で炒め、しょうゆ、ざらめ砂糖、みりんで煮立てた。
商都下館では出前文化が発展した。自家製の中細ちぢれ麺は時間がたっても伸びないよう水は少なめ。スープは冷めにくいよう、うまみを含んだ鶏の油膜で表面を覆い、のり、メンマ、なると、ほうれん草、ゆで卵で彩った。
当時は1杯40円。目指したのは、安くて、おなかがいっぱいになること。のちに「下館ラーメン」と呼ばれるようになる。
味や具材の源流は、明の修業当時にある。下館駅近くのラーメン店「筑波軒」で、鶏肉を使った作り方を学んだ。
実家の納屋を改装し、製麺業を始めると、研究を重ねた。中華麺専用の小麦粉を大手メーカーと共同開発するほどのこだわりよう。市内の食堂に卸すと、たちまち評判となった。
その頃フミ子に出会った明が提案する。「麺を卸すだけじゃ食べていけない。俺がラーメンを作る。店をやろう」
開店当初は味を安定させるのに一苦労。「お客さんからはしょっぱいとからかわれた。これじゃ電気ソバだって」。フミ子が笑って振り返る。「だけど、そう言いながら、また食べに来てくれる。私たちが若かったから、みんなで応援してくれた」
次第に繁盛する。近くには警察署や消防署などが並び、出前の注文が夜更けまで続く。麺の卸先には「麺を使ってもらえるなら」と盛昭軒の味を惜しみなく伝えた。当時60店を超える隆盛ぶりを見せ、のちに下館のソウルフードと言われるようになる。
創業から50年ほどたつ同市の「さかえ屋食堂」も、盛昭軒の麺を使い続ける。2代目の男性店主(58)は「さっぱりした味だから毎日食べられる。流行を追わないから長く続けられるんだ」と胸を張る。
「下館ラーメンの店が広がったのは、麺の力が大きい」
「下館ラーメン学会」の創設メンバーで、筑西市シティプロモーション推進課長補佐の中山康範(46)が語る。各店の魅力をネット上などで発信している。
学会は2010年、下館ラーメンを愛する地元住民や市職員らで結成。店に足を運んで味を確かめ、リポートをまとめ、ホームページやインスタグラムに掲載する。学会公認として約15店を紹介している。
下館ラーメンと一口に言っても、それぞれの店の個性がある。チャーシューは胸肉か、もも肉か、全部位か-。懐かしい商都の味を守りつつ、細部は店主の腕が生かされる。
近年は県外から食べに来る客も目立つ。土産用商品が開発され、市のふるさと納税返礼品となった。青トウガラシを使うなど新たな素材に挑戦する店もある。
「下館ラーメンはまだまだ進化します」。昭和の面影が残る店内。学会特製の黄色いジャンパーを着た中山たちメンバーが、そう言ってうれしそうに麺を手繰ると、フミ子が笑顔を見せた。(敬称略、随時掲載)
■下館ラーメン
鶏チャーシュー、濃口しょうゆのスープが特徴。商都で出前が発達、伸びにくい自家製麺を卸す先は一時60店を超えた