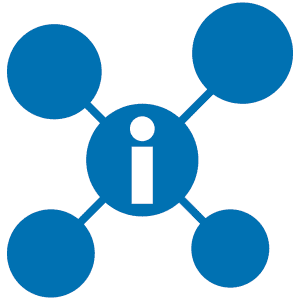正月の風物詩となっている東京箱根間往復大学駅伝(箱根駅伝)が第100回大会を迎えるのを前に、茨城県行方市出身の作家、額賀澪さん(33)が今月、長編小説「タスキ彼方」(小学館)を刊行した。戦時中と現代を交錯させ、箱根駅伝のタスキをつないできた青年たちの思いを紡いだ作品。「戦時中に開催された大会は何だったのか。ファンとして気になっていた」と執筆の動機を語る。
物語は2023年、ボストンマラソンの会場で、ある大学の駅伝監督が古い日記を受け取るところから始まる。日記の主は、戦時下に箱根駅伝開催に奔走した関東学生陸上競技連盟(関東学連)の男子学生。日記には、時代に翻弄(ほんろう)された青年たちの箱根に懸ける熱い思いが記されていた。
額賀さんは「箱根を『走る』以上に、『やる』ことがすごく大きなこと。学連にフォーカスした方が面白い」。ランナーではなく、学連の学生を物語の中心に据えた。戦時中の1941年に代替大会として開催された「東京青梅間往復大学専門学校鍛錬継走大会」、43年に復活した第22回大会などの開催経緯と大会の様子を、登場人物それぞれの視点で描いた。
物語にリアリティーをもたらしているのは、ちりばめられた史実。中でも、日中戦争に召集され、入営日に間に合わせるため得意な5区から1区に変更した選手が登場した第21回大会については、「(出征前に)どうしても箱根を走りたいという、今とは別の意味で大きな存在。スタートにこのエピソードを書きたかった」と話す。
一方、現代パートには、箱根に興味のない学生ナンバーワン長距離走者も。「箱根は面倒くさいと言いながら世界に出て行く選手もいるのでは」と想像を広げ、学生たちの思いの移り変わりも描いた。
額賀さんは、箱根駅伝と料理をテーマにした「タスキメシ」シリーズの作者で、駅伝ファンでもある。順天堂大時代に「山の神」と呼ばれた今井正人さんの走りをきっかけに「箱根を小説に書きたい」と思うようになった。蓄積した情報を生かした作品では、ランナーの心や体、競技の描写をリアルに描いており、駅伝関係者を驚かせている。
第100回大会は出場枠を23校に拡大し、2024年1月2日に往路、同3日に復路が開催される。
額賀さんは「箱根駅伝を楽しみにしている人はもちろん、これまで関心の薄かった人にも読んでもらいたい」と語った。