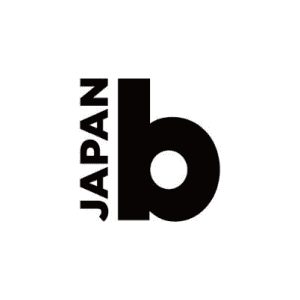ジャパニーズ・ダブの先駆的存在であるMUTE BEATからUK音楽界のメインストリームを飾ったソウルIIソウルやシンプリー・レッドまで、国籍やジャンルを超えて活躍してきたドラマー/プログラマー/プロデューサーが屋敷豪太だ。そんな彼が旧知のDUB MASTER XやMONDO GROSSOの大沢伸一らと組む自由のユニットが、その名もGota Yashiki & The Dub Messengers。思うまま音を重ね、自在に流れていく面々が打ち出す真価とは? 昨年7月に続いて行われた、面々の1月23日のライブの模様を報告する。
屋敷豪太。と書くと、ぼくの胸はなんか高鳴る。なぜなら、1980年代に彼はトランペッターのこだま和文らと伝説のダブ・バンドであるMUTE BEATを結成してシーンを闊歩。また1987年には故中西俊夫、そして藤原ヒロシら高感度な音楽発信者たちとダンス・レーベル「Major Force」も設立した。と思ったら、彼は広い世界を見据えてあっさり渡英してしまう。日本屈指の感性と技量は、彼の地でも通ず。レゲエとクラブ・ビートが見目麗しく交錯した “グラウンド・ビート”を打ち出し一世を風靡したソウルIIソウル(2012年7月にビルボードライブにも出演)の映えあるデビュー作『Club Classics Vol.1』(ヴァージン、1989年)に屋敷はプログラマーとして名を連ねる。当然、彼は英国のビート作りの最前線のクリエイターとして引っ張りだことなった。さらに決定的であったのは、英国で国民的人気を誇るブルー・アイド・ソウル・バンドであるシンプリー・レッドのドラマーに収まったことだった。
そんな彼を見たのは1999年7月末、ロンドンのハイド・パークだった。その一角で開かれた大規模野外コンサート【ルーツ・オブ・キングズ】のトリとして、シンプリー・レッドは登場。そのとき屋敷はこの人気バンドに再加入しており、そこにはギターのケンジ・ジャマー(鈴木賢司)もいた。万単位の観衆の熱い反応を受けるその勇姿に、ぼくがアガりまくったのは言うまでもない。2000年代中期から、再び日本で活動。屋敷は悠々と趣味性の高い活動に邁進してきている。そうした行動で彼が示した最たる意義は、日本も英国も飲み込むジャマイカを起点においたリズムの先進性や魔法であったろうか。
そんな才人によるGota Yashiki & The Dub Messengersは、屋敷の冒険性の高いプロジェクトだ。コアとなるメンバーはクラブ・ミュージック界の名プロデューサー/ベーシスト/DJであるMONDO GROSSOの大沢伸一、そしてMUTE BEATの重要メンバーで日本ダブ・ミックスの嚆矢であるDUB MASTER Xだ。彼らは「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」の2022年10周年パーティーのためにまず集結。その後、このプロジェクトは閉じることなく、臨機応変に維持されている。
今回のビルボードライブ公演はそんな3人に、クラシックからロックまでを自在に横切る鍵盤奏者の石坂慶彦、EL-MALOをはじめ様々な曲者ユニットに関与してきているギターの會田茂一、スカ・パンク・バンドのMAYSON's PARTYでトランペットを吹くSAKIEL、かつてSOIL & "PIMP" SESSIONSに所属もしたはみ出し派テナー・サックスの元晴が合流。ようは今回の“ダブの使徒たち”はサウンド・プロデューサー的資質を持つ4人のプレイヤーと、キャラクターに富む華ある2人の管楽器奏者がフロントに立つという図式を持つ。そして、その総体をカタマリ感と奥行きあるものとしてまとめているのが、コンソール・ウィザードたるDUB MASTER Xである。我々は思うまま音を出し合えばいい、その出口はDUB MASTER Xがしっかりと束ねてくれるから。ステージに上がった奏者たちには、そんな安心感があったのではないか。
さて、そんな発想と腕に覚えありの面々のギグは一言で表せば、野放し。そして、イケイケ。重いビートや、閃きある楽器音に各人が反応し合い、それが連鎖し、曲想はどんどん動き、流れていく。過剰な仕掛けや意思統一なんか、あっちへほい。それは“プロの音楽家がコドモに戻ったような初々しさ”や、“経験豊かゆえ、自分ならこうする”が横溢する。結果、わがままな出演者の発想がシンクロし、それは綺麗な音の尻尾を描いたりもする。かような重なりは、イケてるビートがあればどこにでも行けるという、真理も打ち出す。
大沢伸一は線の太いベース音を奏でるだけでなく、中盤でギターに持ち替えアート・リンゼイのようなパーカッシヴでアヴァンギャルドなカッティングを見せた。新鮮きわまりないが、それもThe Dub Messengersのなんでもありの自由な指針が導くものだろう。一方、會田茂一はマイクとギターを連携させてロボ声のようなものを送り出す場合もあったし、横に寝かせた弦楽器(ペダル・スティール?)で穏健な異音を出したりもする。石坂はずらりとキーボードを並べ、選択肢はたくさんあったほうがいいとばかりに鍵盤音を入れる。それから、この顔ぶれのなかではバークリー音大も出ていて一番ジャズを知っている元晴はウェイン・ショーターの「Footprints」のスピリチュアルな著名フレーズを吹き出し、それに従い面々がジャズ・モードで突っ走る箇所もあった。
そして、一番わあっと思ってしまったのは、屋敷がときに混沌を浄化させるようにドラムを叩きながら歌声を入れたこと。言葉のない詠唱もあったし、終盤には西條八十/服部良一の古い歌謡曲「蘇州夜曲」をしっとりと歌う場面もあった。わあ。なんかそういう様に触れると、彼はまず“歌心”の人であり、とにもかくにもジャンルレスなミュージック・ラヴァーであるという事実をぼくはめちゃくちゃ感じてしまった。
枠を越えていいじゃん。好き勝手やればいいじゃん。音楽のジャンルなんてどうでもいいじゃん。今回の7人の悦びに満ちた実演はそう雄弁に語っていた。だからこそ、The Dub Messengersはこれからも有機的に変わっていくのではないかと思えた。なお、ステージ背後にはスクリーンが降ろされ、音に合わせて幾何学的であったり抽象的だったりする映像が随時つけられた。そうした設定も利して、世界派たる屋敷豪太と仲間たちは突っ走り、山ほどのドキドキを残してくれた。
Text:佐藤英輔
Photo:SHUN ITABA
◎公演情報
【Gota Yashiki & The Dub Messengers
屋敷豪太(ds) 大沢伸一(b) 石坂慶彦(p) 會田茂一(g) SAKIEL(tp) 元晴(sax) DUB MASTER X(mix)】
2024年1月23日 東京・Billboard Live TOKYO