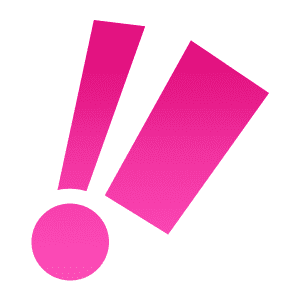俳優・賀来賢人が新たなる挑戦を行ったNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』が、2月15日より配信開始。本作で彼は主演・原案・共同プロデューサーを務め、「現代日本に忍者が潜んでいたら?」という設定の一大エンターテインメントを創り上げた。2020年秋に企画書をNetflixに持ち込み、約3年半で配信までたどり着いた道のりを「奇跡と呼ばれています」と振り返る賀来。こだわりから続編の意気込みまで、たっぷりと語ってくれた。
■忍者作品に忍ばせたオマージュ
――『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』の取材時に「『忍びの家 House of Ninjas』の仕上げを行っている」と伺いました。賀来さんが仕上げ(編集)段階で重視されたポイントを教えて下さい。
賀来:やっぱり第1話ですね。世界観を構築しつつ、見せ過ぎずに“めくる”ことのできる余白を多く作れるようにしたくて、「どこまで謎を残しつつ、家族が抱えているものを提示出来るかが勝負だ」と思い、みんなで議論しながら相当こねくり回しました。
特に話し合ったのは冒頭で、最初は「実は現代に忍びはいた」という説明から入ろうとしていたんです。でもそれをやってしまうと、“普通”なんですよね。そこでコンテナでのアクションから始めて「忍者ってこういうものかな、家族が一人死んでしまったのかな」と印象づけてから本題に入る方法をとりました。作品のテイストを示すものにもしたくて。ただやっぱり悩みどころではあったので、まずは粗く構成して、全体を仕上げてから最後に固めました。
――コンテナ上の戦闘シーンから始まることで「彼らは誰なのだろう? これが後々どう展開していくのだろう?」と能動的に入り込めました。忍者は闇に紛れて任務を遂行する存在かと思いますが、画面が黒(闇)×黒(装束)になってしまうのも調整が難しかったのではないでしょうか。

賀来:そこも考えた部分で、忍者の衣装自体はネイビーにしつつ、黒の画面の中でちょっと浮くような調整をずっと行っていました。「忍者が黒っぽくないのは絶対に違う」という思いがみんなにあったので、照明部と衣装部が常に連携をとりながら作っていきました。
――いまお話しを聞いたコンテナのシーンも含めて、第1話からアクション面でも見どころが連続します。実際に挑戦してみて、特に難しかった部分はありますか?
賀来:第1話で晴(賀来)と仮面の男が戦うシーンで、一本道を走りながら一連のアクションが繰り広げられる場面があります。長回し形式で挑まなければいけなかったのですが、全速力で走りながら横向きでアクションをして、床もやや滑るというなかなか大変なシチュエーションでした。でも成功するまでアクション部が全然OKを出してくれなくて(笑)。ただ出来上がりを見て、「面白いカットになったな」と手ごたえは感じました。
そして、クラブでの戦闘シーン。接近戦なのでパンチにしろ相手にちゃんと入れないと勢いが伝わらず、試行錯誤しながら作っていきました。
――オリジナル作品としての独自性は追求しつつ、デイヴ・ボイル監督と共通項としていた過去の作品などはありましたか? 個人的にはクラブでの戦闘シーンに『ジョン・ウィック』っぽさを感じて燃えましたし、そうしたアクション映画の系譜で見る楽しさも本作にはあるのではないかと。
賀来:僕は監督のブライアン・デ・パルマのスタイルをリスペクトしています。色遣いや雰囲気、60年代のスパイ映画っぽい音楽の使い方、ミステリー作品でのジャズなどなど…。デイヴもデ・パルマ監督が好きで、僕の想像を超えた演出を行ってくれました。
■忍者に誰よりも詳しかったのは、まさかのあの人!
――賀来さん自身が経験豊富な分、脚本時点で「これは出来ないかも」とセーブをかけてしまう瞬間はあったのか、それとも意識的にリミッターを外して臨んだのか、どちらでしょう。

賀来:それでいうと、脚本作りの時はワクワクしていましたが、ふと我に返って「これ出来るのか?」とは思いました。もうそれは全部が全部です(笑)。忍者×現代という設定と、事件も壮大になっていきますし、そもそも俵家が暮らす家をどうする?という問題がありました。やっぱりロケハンをしていても(理想の家が)見つからず、美術部がセットで作り上げてくれて。美術、撮影、照明、衣装、メイクと全ての部署に日本一の方々が集まってくれたので、助けられっぱなしでした。日本のクリエイターたちは本当にすごい才能を持っていると感じましたし、みなさんのおかげで自分たちのビジョンが実現できたと思っています。

そして現場では、山田孝之さんや江口洋介さん、宮本信子さんをはじめ、みなさんがどんどん「自分はこう思う」というアイデアを出してくれました。本番直前にセリフを変えることもありましたし、それをやられると嫌な方もいるかと思うのですが「むしろやらないの?」という空気を作ってくれて。
――そうした空気感は、撮影当初から出来上がっていたのでしょうか。
賀来:そうですね。僕とデイヴが現場でアイデアを出し合っているのをみなさんが見ていたこともあるでしょうし、そもそも素晴らしい役者さんだからそれが「出来る」ということもあったかと思います。みなさん本当に高い柔軟性をお持ちでした。
――ものづくりにおいて「これをやりたい」も大切ですが、「これはやらない/やりたくない」も同じくらい重要ではないかと。賀来さんが今回「これはやらない」と定めたものはありますか?
賀来:まず一つは、忍者らしさ。現代に忍者がいるとなるとやっぱりスパイものになってしまうんです。ガジェットも新しくしたいとなると忍者らしさがどんどん消えていってしまうので、「忍者のあるべき姿とは何だろう」と常に模索していました。撮影中も「忍者とスパイは違う」を念頭に置いていましたね。ただ、デイヴが誰よりも忍者に詳しかったのですごく助けられました。

そして、なるべく説明ゼリフをなくすこと。僕がずっと思っていたのは、日本の作品の説明ゼリフの多さです。映像があるのにセリフで説明するほどもったいないことはないと思うので、どこまで削れるか挑戦しました。削れば削るほど大変だということも分かったし、セリフがないからこそ空気感で伝わるものはやっぱりあるなということも、改めて感じることができました。
あとはもう、デイヴのやりたいトーンを守ることだけですね。予算やスケジュールといった外的要因はたくさんありますが、その中でもデイヴに寄り添って、彼のクリエイティブを尊重することを特に意識しました。
■今作で入らなかったアイデアは今後に
――賀来さんはデイヴ監督を「天才」と評していらっしゃいましたが、どういったところにそのセンスを感じたのでしょう。
賀来:彼が生み出す脚本やセリフ運びが、僕が見たことがないレベルのもので「この人でないと作れない、撮れないストーリーだ」と感じた部分が大きいです。なので彼に監督もやってほしいとオファーしました。

デイヴが今回フォーカスした忍者の面白さは、我慢や忍耐といった“忍ぶ”部分でした。史実にも基づきますが、お酒を飲んじゃいけないし肉も食べちゃいけない、セックスもしてはいけないといった縛りの中で常に陰に隠れて生きてきて、仕える先が悪か正義か知る由もないという忍者の“悲しみ”に着目する部分が、僕にはないものでした。
これはデイヴが話していたことなのですが、奥ゆかしさや優しさで気持ちを表に出さない日本人の遠回しな会話がすごく面白いと。例えばスペイン人だったらもっとパッションにあふれたストレートな会話になるでしょうし、僕たちが海外の方々の感情表現を面白いと思うように、日本人という人種の中に、もっともっと面白いものは眠っているんだと改めて気づかされました。たとえば日本語は「てにをは」一つでニュアンスが変わる言語ですし、Netflixのように世界配信ができたり、SNSが普及している時代だからこそ自分はもっと日本の文化や景色を知っていかないといけない、と思わせてくれました。
――お話を聞いていて、デイヴ監督との出会いが賀来さんのクリエイティブな面をより進化させたのだな、と感じます。

賀来:デイヴとは国籍も世代も違いますが、共通言語といいますか「良い」と思うところが本当に一緒で、イメージ共有はものすごく早かったです。僕らが盛り上がっちゃって、上層部が「待って! 予算がさらに膨れ上がっちゃう!」ということがあったくらい(笑)。「でもやりたいんです!」と子どものようにゴネましたが、それでも入れることが出来なかったアイデアはたくさんあります。そういった意味では、やりたいことを100%詰め込めたわけではありません。それはネガティブなものではなく、今回はこの形がベストだと自信を持っていますし、入れられなかったアイデアは、もし機会があれば続編でできたらいいな、と。
――『忍びの家 House of Ninjas』は大きな挑戦だったかと思いますが、“燃え尽きた”ということはなく…。
賀来:はい。むしろ次が勝負だという気持ちです!
(取材・文:SYO 写真:上野留加)
Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』は、2月15日からNetflixにて独占配信開始。