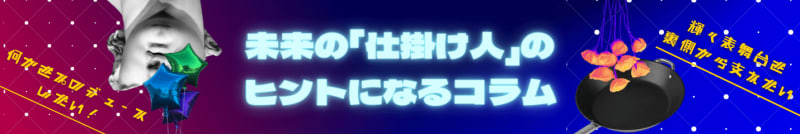ドラマや映画などの制作に長年携わってきた読書家プロデューサー・藤原 努による、本を主軸としたカルチャーコラム。幅広い読書遍歴を樹形図のように辿って本を紹介しながら、自身の思うところを綴ります。
今回は、2024年1月に発表された直木賞受賞作である『ともぐい』と『八月の御所グラウンド』について、独自の目線で考察します。
直木賞二作 “「非社会性」と「京都人の独特」について”
朝日新聞1月29日付の朝刊に今期の直木賞受賞2人の受賞エッセイと言うのが載っていました。河崎秋子と万城目学。書かれている内容は全く違うのに、どちらも妙な味のようなものが感じられ、今期は芥川賞も直木賞も読まないだろうな、と僕は何となく思っていたのですが、急にこの人たちの2冊を読んでみようと思いいたりました。
まずは河崎秋子『ともぐい』。
著者の見た目に触れるのはこのルッキズム時代どうなのかと言うのはわかりつつも、この人の写真を見た時、僕は、出し抜けに、あの木嶋佳苗を思い出してしまったのです。そう、知り合った男たちに保険金をかけて殺したとされる人物です。あの人は、声と字がすごく綺麗だったと言うのをどこかで読んだのですが、何となく河崎さんもそうなんじゃないかと言う気がしました。
しかも何と河崎さんは木嶋と同じ北海道・別海町出身だと言うではありませんか!そんな符号があるものなのかと僕は鳥肌が立ちました。
今回の受賞作品を読む前に、熊文学の極北、みたいな世評とは別に、きっと性欲にまつわる話に違いない、と僕は目星をつけました。読後の今、部分的には当たっていたのではないかと思います。
明治の初頭、北海道の山中でただ一人、熊や鹿を狩ってそれをたまに町に持っていってお金に変えて生計を立てている熊爪と言う男のお話。とてもなまぐさい、生理にくるような表現が何度も何度も繰り返される文章ですが、熊爪の主観で綴られる行動原理や考え方は、いわゆる社会性とは無縁であることもあって、どうしてその時そんな風に思うのか、凡人である僕には理解できないこともありました。ここには当然、男女の保守的なジェンダー観なんてものもそもそも存在しない。あるのは自然の中で狩りをして生きる中で彼だけが身につけたのであろうと思える哲学。たぶんそこには他者に対する愛、なんてものもありません。だから性欲もより純粋で身体が発する欲求そのままに行動する、とも言える。しかし熊との格闘でケガをした熊爪は、唯一の社会との接点である町で獲物と品物を交換する中で、人間社会とのとば口に少しずつ立っていく。でも彼にはその人たちがどう言う思いを持って自分に語りかけてくるのか、ほとんど理解できない様子でもあるのです。
河崎秋子という作家は、北海道に住みながら、どのような肉体的精神的必然を持ちながらこういう小説を書いたのか?作家自身への興味をどうしても拭うことのできない読書となりました。
一方、『八月の御所グラウンド』。僕に取っては初めての万城目学作品でした。京都市生まれ育ちの僕には、この人の作品が京都を舞台にしたちょっとファンタジーコメディが多いと言う先入観があって、勝手な同族嫌悪みたいな感情が働いてなんとなく手に取らずにきてしまいました。しかし冒頭に記した直木賞受賞エッセイで、これまで何度も直木賞候補になってその度に落選して苦杯を舐めてきたのもあり、もうすでにそこについては諦めの境地に入っていたと言う感じのことを書かれていたので今回初めて読んでみようという気になりました。
こう言うことを言う作家は、きっともはや何か新しいことをして読者を驚かせてやろうと言うような若さとシャープさを売りにするような作風とはたぶん違うだろうと思ったもので。
内容そのものに触れるとネタバレになってしまうので、ここは物語の舞台である京都という街をこの作家がどのように捉えているのか、京都生まれ育ちで今はもう東京のほうが長く後者をより愛するようになった僕自身の眼から少しばかりシニカルに捉えてみようかと思います。若干うがち過ぎと思われるかもしれませんがご容赦ください。
まず主人公の朽木についてですが、百万遍の近くの大学寮みたいなところに住んでいる法学部4回生と言う設定(この○回生という表現も関西独特の表現で東へ向かうと○年生という表現しかない)で、これ京都に住んでいる者なら誰でも京都大学に在籍している学生なんだなと分かります。
しかしこの作家は、京大という世間的知名度も圧倒的に高い大学の固有名詞を決して表に出さない。これは百万遍という京都に実在する地名に暗喩として含まれるものであるにも関わらずです。スーザン・ソンタグもびっくり、ですが、万城目学という人の京都認識の一端が伺えます。この人のプロフィールを見ると大阪出身で京大卒ということなので、純然たる京都人でないこともこうした姿勢を生むのかもしれません。つまり京大、と明確に言ってしまうと、エリートの卵、と捉えられてしまうことを避けたい、でも分かる人には分かる、と言う高等テクニックの一種だと思います。蛇足ですが、僕自身、大学受験の際、現役と浪人時の2回、当時存在した共通一次試験というものを京大キャンパスの教室で受けたのですが、いずれも自己採点の結果、京大には手が届かず、名古屋大学へと進みました。京都から名古屋に初めての一人暮らしをするために向かう時、生粋の京都市民である父から「おまえも都落ちするんやな」と言われたことが今でも耳にこびりついています。僕は内心で、京都は今は都じゃない!都は東京であって僕はむしろそちらへ向かって上がっていくのだけれど、と父にツッコミを入れましたが。
またこの物語に出てくるキーとなる歴史上の人物に、戦時第一線のプロ野球の投手として名を馳せた沢村栄治がいます。物語の中では何でこの人物が京都に?みたいなフリもあるのですが、現在60歳で高校3年の夏、高校野球の京都代表が京都商業高校になり、これが甲子園で大活躍して準優勝したことに驚喜した僕を含めた京都市民にとっては、そんなフリへの答えはすでに見えています。当時、京商の選手たちが必ず沢村栄治の遺影をスタンドに持ち込み、これをテレビ放送で何度も紹介していたこともあって、“沢村栄治=京商の象徴”みたいな刷り込みができており、京都で展開する野球の話、と言うことで沢村栄治の登場はむしろすんなりと受け入れられる流れでした。
歴史上の人物の登場は、その人について特別な知識を持っていたりすると、そこに別の見え方が見えてくるものだなと、今回この小説を読んで改めて思いました。
そしてもう一つは、小説の最後に出てくる大文字の送り火のこと。このイベントを幼い頃“大文字焼き”と称して、これまた父に「おまえは京都に生まれ育ちながらこんな大切な行事に他県の者たちと同じような呼び方をして恥ずかしいと思いなさい」と怒られた記憶のある僕としては、ある意味この小説の本筋とも関わってくるこの行事の持つ意味に別の感慨も生まれてくるのでした。
京都では大文字送り火の8月16日の夜に、亡くなった魂が送られていくのでその翌日からグッと気温が落ち着いて季節は秋に向かっていくのだ、などと言うことがまことしやかに語られ、そんなことあるかいなーと幼い頃は思ってたけど、年を経るに連れてほんとにそんな気がしてくるようになり、京都市民としてより馴化されていこうとしている自分自身に気づいてハッとなったことがあります。今では東京都民としての時間のほうが遥かに長くなってしまいましたが、あのままずっと京都市民であり続けていたら、こうした伝統のイベントも含め頑固な京都中心主義の市民になっていた可能性を否定できないのではないかと言う気がします。
かの『徒然草』の時代から、京都人だけが知る風雅な考え方や斜に構えた態度などと言うものがあるように語られ、それによって京都の人が他県の人たちからちょっとした嫉妬感も含んだ先入観を持たれることもあるわけですが、この小説を読んで本筋の面白さとは別に、そんな京都人が図らずも持ちがちな特質を思い出してしまう読書となりました。
しかし直木賞にしても芥川賞にしてもその受賞は、人の人生をプラスにもマイナスにも変えていくのでしょうね。かつて『オキナワの少年』で芥川賞を受賞した東峰夫のようにその後貧窮に耐えてガードマンなどをして食い繋いだ人もいれば、村上春樹のように芥川賞候補に二度選ばれながら受賞できず、しかし今ではノーベル文学賞の候補に何度もなっていると言われている人もいる。村上春樹自身はそんな賞になんかこれっぽっちも興味ないんじゃないかと僕は思っていたのですが、この前年明け最初のTOKYO FM『村上RADIO』を聴いていたら、ボルヘスという作家が何度もノーベル賞候補になりながら受賞していないんだけど、ノーベル賞はノミネートされた人が誰だったかが分かるのも50年後なんですよね、などとさもノーベル賞に興味あるような発言をされていました。村上春樹と言う人も、ラジオを通じて、ファンへのさり気ないサービスをするのだなと思いました。
info:ホンシェルジュTwitter
comment:#ダメ業界人の戯れ言