インタビューをした部屋で、彼女はソファを前に立ったまま、生まれたばかりの長男を抱いていた。「揺すっていないとすぐにぐずるんです」。そう言いながら育児を楽しんでいるようだが、ふとした時、いまわしい記憶がよみがえる。

30代のアユミさん(仮名)が性被害に遭ったのは、滋賀県草津市の小学校に勤めていた5年前。加害者は校長だった。校長はアユミさんのミスに対処した後、「貸しやで」と言ってハグを求めてきた。次第に行為はエスカレートし、胸を触られたり、キスをされたりした。
被害を受けた時に断れば良かったのだろうか。だが、職場はヘルプを出せるような環境でなく、ましてや加害者はそのトップ。やめてください、と言い出すことは難しかった。
告発すべきかどうか、アユミさんは苦しみ続けた。相手は権力者で、否認されたら周りに信じてもらえない恐れがあるし、むしろ、「曖昧な対応をしていた」と責められるかもしれない。校長から逆恨みされないか、自分の生活にどう影響するのか―。いろいろな想像が駆け巡り、自分の感覚が間違っているのでは、とすら考えた。
1年半ほどがたち、親しい元同僚たちにどうにか被害を伝えることができた。強い後押しをもらって、被害を申告した。校長は滋賀県教育委員会からセクハラ行為による停職処分を受け、依願退職。警察に逮捕され、被害は公になった。
アユミさんは「言わなかったら悔しいまま。誰にも言えないまま生活するのはしんどかったと思う」と話す。自分が受けた行為は性被害だったと客観視できるようになり、新しく頑張ろうという気持ちになれた。
ジレンマがある。腫れ物扱いされるのが嫌で、気丈に振る舞う。そうすると周囲から、もう気にしていないと思われてしまう。「普通にしゃべれるぐらい楽になったんでしょ」と言われ、冗談めかした言葉をかけられることもある。「どこまでの傷があるのか、どうしても他者には分かってもらえない」と吐露する。
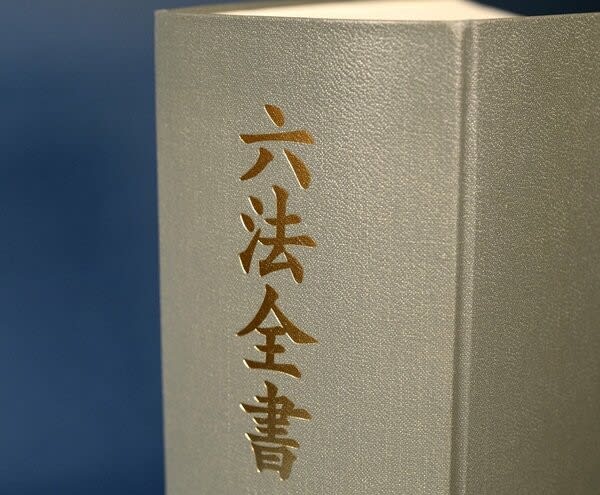
忘れようとしていたのに、子どもが生まれた時に思い出してしまった。「メンタルが弱った時期はしんどかった。自分の人生の一つだと捉えて、背負っていくしかないのかな」
被害を受けた人の心と体に深い傷を残す性暴力。#MeToo運動やフラワーデモなど、当事者や支援者が勇気を出して声を上げたことで、社会は近年大きく変わってきた。
ただ、性暴力被害者の支援に携わってきた上谷さくら弁護士は、「被害者がバッシングに耐えながら訴えて、それでようやく変わるということは不健全だ。そういうことをしないでいいように、国や自治体が制度を整えなければならない」と強調する。
メディアはどうだったか。毎日新聞で記者経験もある上谷弁護士はこう振り返る。「大きく注目されるケースなどを除き、性被害は十分に報道されてこなかった。家族で見るニュースとしてふさわしくないというふうにタブー視され、だから性暴力の実態をみんな知らなかった」
◇
刑法の性犯罪規定が改正され、男性アイドルへの性加害問題で大手芸能事務所が社名変更に追い込まれた。自衛隊では女性隊員が訴えた性被害に有罪判決が出た。性暴力撲滅に向けた大きな潮流を止めないために、被害者の声に耳を傾け、今も残る課題を探りたい。
(まいどなニュース/京都新聞)

