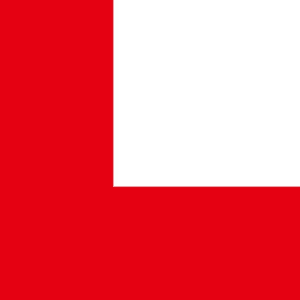昨年で結成25周年を迎えた、京都の人気劇団「ヨーロッパ企画」を率いる劇作家・演出家の上田誠。2023年は、ラブコメらしからぬ複雑な時間構造が話題となった吉岡里帆・永山瑛太主演のドラマ『時をかけるな、恋人たち(以下トキコイ)』(カンテレ)や、映画『リバー、流れないでよ』がカルト的な人気を集めた。ドラマよりも物語の仕掛けに凝りまくるその作風は、間違いなくヨーロッパ企画の舞台で培われてきたものだ。

脚本家・演出家の上田誠、2023年で結成25周年を迎えたヨーロッパ企画の代表を務める
とはいえ、特に若者のなかには「ヨーロッパ企画とは、上田誠とはなんぞや?」ということを、今さら聞けないという方も多いのではないだろうか。そこで『Lmaga.jp』の若手編集部員が「私、ヨーロッパ企画のことはなにも知らないんです!」というお断りを入れた上で、上田を直撃するという大胆な取材を敢行。あらためて、その唯一無二のスタイルのルーツや、演劇・映像の両ジャンルでの展望を語ってもらった。
取材・文/吉永美和子
写真/木村正史
■ 「高校生から、今でもやりそうな劇をやってた」
──私は今26歳で、ヨーロッパ企画さんとはほぼ同い年です。まず、なんでヨーロッパ企画を作ったんですか?・・・というところから始めてしまってすみません。

上田率いるヨーロッパ企画の本拠地、京都にある「ヨーロッパハウス」でインタビューを実施
いやいや、ありがたいです(笑)。今さらね、話すこともあまりなかったんで。僕はもともとものづくりが好きで、中学生ぐらいのときから、ゲームや音楽を作るようになったんです。それで高校生のときに、文化祭のクラス劇の作・演出を頼まれて「やってみようかなあ」と。
──演劇には馴染みがあったんですか?
三谷幸喜さんの劇や番組はTVで観てましたし、小劇場が好きな友達に連れられて「維新派」(注1)や「MONO」(注2)を観に行ってました。それでクラス劇を作ってみたら、なかなか評判が良かったし、僕も「おもしろいなあ」と思って。それまでは1人でモノを作っていたけど、集団で作ると1人じゃできない意外性もあって、全然楽しさが違った。それで「大学に入ったら劇団を作ろう」と思って、大学1回生でヨーロッパ企画をはじめたから、わりと最速でしたね。

当時を振りかえりながら、丁寧に投げかけられる質問に答えてゆく上田。「なぜ劇団を作った?」
──ちなみにクラス劇って、どんな内容だったんですか? クラスで劇を作るって、なんとなく『桃太郎』のイメージが強いんですが。
いやいや、当時から仕掛けっぽいやつでした。1年目は、舞台上にマンションの部屋を2つ並べて作って、2部屋同時進行で物語を見せるみたいな話。次の年は、学校のロッカーを8個並べて「外からしか閉められないシェルター」ということにして。それで舞台中央に、30分後に爆発するという爆弾を置いて、8人のうち、誰が最後に全員のシェルターを閉める1人になるか? という会話を、30分のリアルタイムで見せる。当時から、今でもやりそうな劇をやってました。
──すごくおもしろそうですね。 そういう変わった仕掛けの舞台を作る、ルーツみたいなものってなんだったんですか?
芸人さんの笑いと、ゲームじゃないかと思います。両方ともエンタテインメントなので。演劇って社会的なテーマを描くとか、アート志向のものが多いなかで、自分としては広い意味でエンタテインメントにしか興味がなかったんです、今も昔も。でもヨーロッパ企画ができた頃って、京都でエンタメ系の劇団がいくつか誕生して、お互いが競い合うように作品を発表して、盛り上がってた時期だったんですよ。僕らもそれに引っ張られて「負けへんぞ!」って感じになって、いろんな作品を量産できました。

面白いコンテンツを生み出す根底には、上田の「果てしないコンテンツ愛」が土台として存在する
──そのときに生まれたのが、映画化もされた『サマータイムマシン・ブルース』だったわけですね。その一方で、演劇以外に映像とかゲームも頻繁に作っていたそうで。まだYouTubeもスマホもなかった時代に、そういう劇団はめずらしかったとも聞きました。

映画『サマータイムマシン・ブルース』(C)2005 ROBOT 東芝エンタテインメント 博報堂DYメディアパートナーズ IMAGICA
エンタメ劇団というと、すごく派手なケレン味のある芝居を想像しがちなんですけど、僕らはエンタメのなかのインドア派というか(笑)、すごくかっこいい演技とか体術はできない。でも劇団員のみんなも、ものづくりが好きで得意だったんです。それで劇団でビデオカメラを購入して、暇があったら映像作品を作って、みんなで見せ合いっこしてました。こう言ったらアレですけど、演劇だけが好きだったわけではなかったのかもしれないです。
──それがヨーロッパ企画さんがよく言う「コンテンツ地獄」に。
そうですね。映像以外にも、「ヨーロッパ企画のスタジオ祭り」と称して、公式HPで24時間企画をアップし続けるとか、PC用のゲームを作ったり、ラジオ番組を作ったり。それを続けていった結果、本当にコンテンツだらけになりました。
■ 昔のLマガ片手に「なんでこんなことを?」
──今回ヨーロッパ企画さんのことを調べているときに『Lマガジン』(注3)の最終号で、すごいページを作ってたのを見つけたんです。Lマガジンのことをいじり倒していて、これもすごいコンテンツだなあと思いました。

最終号となった2009年2月号の『Lmagazine』より

ヨーロッパ企画・上田が『Lmagazine』の(ありもしない)歴史をひたすらに書き続けるという企画。よく読むと今の時代じゃとんでもないものも
ああ! ありましたね(一通り目を通して)・・・なんでこんなことを書いたんやろう?(笑)昔Lマガジンで「Eマガジン」という、Lマガの特集に噛みつくというコンセプトの連載をやってたんです。今見ると、誌面を借りて大喜利をやってるだけのコーナーでしたけど。でもそんなことを、Lマガというちゃんとした雑誌でやるというのがおもしろい。KBS京都で放送している『(ヨーロッパ企画の)暗い旅』もそうですけど「なんでここで、こんなことをやってるんだ?」というスタンスを作るのが、どんなメディアに出たときも、やっぱり大事だと思います。

「やっぱり面白い」と、思い出に浸りつつも、「締め切りがタイトだった記憶がある」と苦笑い
──そう言われると『トキコイ』も、フッと「なんでこんなことをやってるの?」と我に返るような、不思議な感触のドラマでしたね。タイムマシンで物語の時間軸がどんどん変わるので「今私、どこにいるんだろう?」という、今まで感じたことのない気分になりました。
ああ、それはめっちゃわかりますし、うれしいです。カンテレのあの時間帯は、ギリギリ攻めたことをやってもよさそうな枠だったので「じゃあ、振り抜きましょう」みたいなことができました。結構ヨーロッパ企画のやり方に近い形で書けたので、そういうめずらしい空間が作れたと思いますし、コアなファンがたくさんできた作品になりました。ああいうちょっと特殊な、最大公約数的な番組じゃない番組の方が、深く刺さることってあると思うんです。こういう時間ものが好きなお客さんが、ジワジワと増えてくるかもわからないですね。

主人公・常盤廻を演じる吉岡里帆(左)と、恋の相手役・井浦翔役の永山瑛太 (C)カンテレ
──忘れられないドラマになりました。そうやってテレビをやっていて、一番おもしろいこととか、意識していることってなんですか?
それこそ僕が演劇に興味を持つきっかけになった、三谷幸喜さんや維新派を初めて観たのが、どっちもテレビだったんです。大多数の人は、いきなり劇場には行かない。やっぱりテレビとか映画とか、劇場の手前にあるメディアで触れることが多いと思うので、僕らも新しいお客さんに触れるためには、やっぱり映像をやった方がいいなあと。しかも『トキコイ』や『暗い旅』のように、できるだけ自分たちの劇団のテイストに近い形のものを・・・実は『暗い旅』って、企画から撮影、編集まで全部自分たちでやって、完成したものをKBSさんにお渡ししてるだけなんです(笑)。
──そんなことができるんですね!
でもテレビって当然、視聴率を取らなきゃいけないとか、一定の枠のなかでやらなきゃいけないとか、演劇にはない制約がたくさんあって。演劇は完全に自己責任で、完全に自分たちの作りたいものをやれるんですけど、テレビってそういうものじゃない。視聴率を取るような戦い方をするのが前提で、それには今も苦労しています。でも『暗い旅』があったことで、テレビでも演劇のような作り方ができることがわかったし、ほかの局でも、自分たちの得意技に引き寄せた考え方ができるようになってきました。
ヨーロッパ企画や僕のやり方をわかってくれる方が、テレビ側にも増えてきて、それでちょっとずつやりやすくなってきた感じです。でも演劇に比べると、まだまだわからないことだらけ。単純に、やればやるほど映像が上手くなってきてる時期かなあと思います。
■ 「映画は、演劇とは真逆のアプローチ」
──映画の方も、劇団で作った『ドロステのはてで僕ら』(2020年)が、世界各地の映画祭で23個の賞を取っていて、すごいです。
構造とかパズルっぽいものって、意外と海を超えるんですよ。物語の構造に凝った映画って、海外のものを観ても「すごい」って思うし、逆もそうなんだなあと。日本独特の感性を描いたものよりは、難なく言語の壁を超えるのかもしれない。それで映画の方は、構造が入り組んだ話を、わざと選んでやっているところはあります。

「ヨーロッパハウス」に飾られている輝かしい受賞歴、日本での受賞だけでなく海外でも功績を残してきた
──上田さんのなかで、世界でウケたいという意思はどれぐらいあるんですか?
全然思ってなかったですね。演劇って・・・どう言ったらいいんだろう? たとえばどこそこの遠い県に「日本一おいしいコロッケ屋さんがある」って言われても、近所のおいしいコロッケ屋さんにしか買いにいかないじゃないですか?・・・いや、このたとえは忘れてください(笑)。
──いえいえ、なんとなくわかります。近所に十分美味しいものがあるのに、そこまでして行く価値があるかな? って。
あ、つながってよかったです。要は演劇って、劇場に足を運ばないと観られないんで、距離に縛られるんですよ。だから世界に通用する演劇を作っても、海外公演をしない限りは世界の人が観に来られるわけじゃないので、だったらご近所の人が楽しめるものしよう、と。だから今のヨーロッパ企画は、ハワイアンセンターじゃないですけど、ロンドンとか香港とかの「僕らが思う海外の世界」を作って、それを国内の人に楽しんでもらうという意識でやっています。逆に映画の方は簡単に海を超えるから、日本・・・というか、僕らの地元の京都の風景を撮って、それを世界に見せる方がおもしろいと思ったんです。だから、演劇とは真逆のアプローチですね。

演劇、ドラマ、映画とすべて違うアプローチで臨むという上田誠
■ 「京都は、切っても切れない関係」
──この取材の話があるまで、私はてっきり上田さんは東京に住んでいると思ってたんですけど、今も京都のこの(取材場所である)「ヨーロッパハウス」を拠点にされてるんですね。京都にいるメリットが、なにかあるんでしょうか?
正直、今も「東京に行こうかなあ」って悩むんですよ。やっぱりシンプルに、交通の便ってありますから(笑)。でも京都で旗揚げして、ここを拠点に活動していくと、やっぱり京都がどんどん好きになって、切っても切れない関係になっていったというのはあります。特にロケをするときには、地縁があったらなにかと便利ですしね。それに僕はメインストリームみたいな流れがあるときに、あるオルタナティブというか、メインとは違う道を作っていこうという気持ちがずっとあって。

26年目を迎える「ヨーロッパ企画」だが、「やりたいことがたくさんいろいろありすぎて追いつかない」と上田はうれしそうにこぼす
なにか見たことがない面白さをエンターテインメントにしようとしたときに、それを端的に表現するのに「京都にいる」というのは、わかりやすい記号にはなるんです。既存のメディアや業界とちょっと距離を置きながら、独立独歩でめずらしいものを作ろうとしたときに、京都という土地、ヨーロッパハウスという場所があったのは、いいことだったんじゃないかなあと思います。
──そうして25年京都でやってきて、今年は26年目に入りますけど、上田さんが今後やってみたいことってなんですか?
ここまで演劇以外の話が多かったですけど、やっぱり一番やりたいのは演劇。昨年25周年記念で「南座」(京都市東山区)で1日だけ公演を打ったんですけど、リアルな場所に集まること自体が、演劇のひとつの醍醐味だし、劇団をやってるおもしろみだなあ・・・という、本公演とは違う手応えを強く感じました。だから今後も演劇活動がメインにはなるけれど、問題なのはやりたいことがたくさんありすぎて追いつかないんです、体と手が(笑)。
──なにを選んでいいかわからない。
そうですね。新作もやりたいけど、今まで作ってきた良い作品も再演したいし、映画も作りたければドラマもやりたい。弾数がめっちゃあるなかで「どれを選んだら、お客さんがおもしろがってくれるかな?」ということを、最終的には一番に考えています。「自分がやりたいこと」っていうのも大事だけど、それだけを突き詰めてお客さんが離れてしまったら、活動を続けられなくなってしまいますからね。僕が本当にやりたいことはすごくマニアックで、広く一般性があるエンタテインメントではないと、自分でもわかっているので(笑)。そのバランスをうまく取りながら、これからもやっていきたいなあと思います。

「お客さんを、どう面白がらせるか?」を念頭にコンテンツを作り続ける上田、まだまだこれからも彼が作る新世界に出会えるだろう
──ぜひこれから、いろんなコンテンツをチェックさせていただきます。最後に、26年目の目標を聞かせてください。
去年の25年目は、はからずもいろんな意味で集大成っぽくなったので、リスタート感があるんです。年末には久しぶりに「ショートショートムービーフェスティバル」(注4)を開催するので、また新しいものが生まれることに期待しています。役者メンバーは昔からあまり変わってないけど、スタッフは新陳代謝が起こっていて、意外と若い人たちが動かしているんですよ。
「ショート・・・」はみんなが熱く競い合うことで、思いがけず新しい関係が生まれたり、僕らの知らないところでつながりができるイベント。そういったことを通して、新しい人たちの躍進に期待して、運営していくというのが、26年目のフェーズになると思います。
◇
直木賞作家・万城目学の小説を舞台化した『鴨川ホルモー、ワンスモア』を、4月の東京公演を経て、5月3・4日に「サンケイホールブリーゼ」(大阪市北区)で上演。8~11月にはヨーロッパ企画本公演として、上田の岸田國士戯曲賞受賞作品『来てけつかるべき新世界』を、大阪の新劇場「SkyシアターMBS」(大阪市北区)をはじめ、全国各地で上演する。
(注1)維新派
作家・演出家の松本雄吉が率いた大阪の劇団。大規模な野外劇場を使ったスペクタクルな舞台が国内外で人気を博した。松本の逝去により2017年に解散。舞台美術のアイディアを固めてから物語を考えるという松本のやり口は、上田の作品づくりに大きな影響を与えている。
(注2)MONO
TVドラマの脚本家としても活躍する作家・演出家の土田英生が主宰する京都の劇団。日常の一片を切り取ったようなワンシチュエーション・コメディのスタイルと、京都を拠点に全国的な活動を行うというスタンスは、やはり上田に大きな影響を与えた。新作『御菓子司 亀屋権太楼』が、2/22~26に「扇町ミュージアムキューブ」で上演。
(注3)Lマガジン
『Lmaga.jp』を運営する京阪神エルマガジン社が発刊していた情報誌。2009年休刊。
(注4)ショートショートムービーフェスティバル
ヨーロッパ企画が2004年から開始した短編映画祭。劇団員や周辺のクリエイターが、1つのお題に沿った5分以内の短編映画を作り、観客投票で順位を決定する。水野美紀や東京03などの著名人も過去に参戦。今回が5年半ぶりの開催となる。