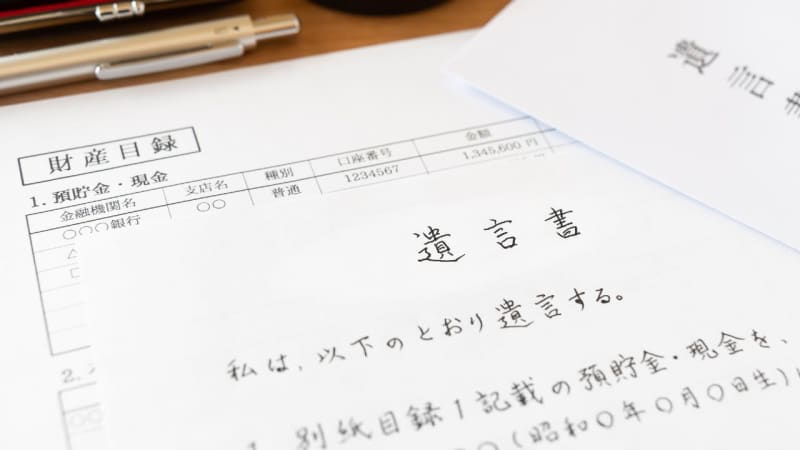
相続の現場では、親がせっかく残した遺言書が役に立たないどころか、苦労をかけた子の人生設計が大きく狂ってしまうといった、厳しい事態がしばしばみられます。具体的な事例から、その原因と対策を見ていきます。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。
「遺留分は請求しないで」…親の思いが子に届かない現実
近年では、さまざまな専門家の啓蒙の結果、ご本人の意思で遺言書を残される方も増えてきました。相続手続きでは、遺言書があればそれが最優先となり、相続人間での遺産分割協議が不要になります。しかし一方で、遺言書があるにもかかわらず、トラブルとなるケースも多くあります。とくに「遺留分」を侵害した遺言書は、相続人から当然の権利として遺留分侵害請求をされることになります。
筆者の事務所では、公正証書遺言作成のサポートのほか、その後の手続きのサポートも行っていることから、「相続」だけでなく「相続のその後」を知る機会もあります。
多くの場合、遺言書は相続人に配慮しながら作成されており、「遺言書があって本当によかった」と思うケースが大半ですが、なかには遺留分侵害額請求がなされ、激しい争いに発展することもあります。
問題が起こる遺言書は、たいてい「私の意思を汲み取り、みんな仲良くすること。遺留分請求はしないように」といった趣旨の記述があります。
故人の思いが盛り込まれながらも、なぜ問題が起こるのでしょうか。いくつかの事例から読み解いていきます。
妹2人は父の遺言書に不満、介護した姉は実家売却へ追い込まれ…
相談者の鈴木さんは70代。3人姉妹の長女です。婿養子を条件に結婚した夫と、自分の両親とともに、ずっと実家住まいをしてきました。
2人の妹はそれぞれ嫁ぎ、実家を離れていましたが、しょっちゅう実家に顔を出すなどして交流は盛んでした。
ところが、母親が60代になってすぐ亡くなり、厳格な父親が残されました。すると、2人の妹は実家から足が遠のき、すっかり父と疎遠になってしまったのです。その後、父親の介護が始まりますが、妹たちからはサポートはもちろん、父親の様子を心配する言葉もありません。そのため、鈴木さん夫婦で父親の生活すべてを支えることになりました。
父親はそんな妹たちにいら立ちを隠さず「遺産のすべてを長女夫婦に相続させる」という趣旨の公正証書遺言を残しました。
父親が亡くなったときは90歳を過ぎており、遺言書作成からおよそ20年が経過していました。鈴木さん夫婦は、それほどの長い間介護を続けたことになります。
父親は6人きょうだいの長子の長男で、下には弟が2人、妹が3人います。父親の時代は家督相続の風習が残っており、長男である父親が当然のごとく全財産を相続したのですが、それでもきょうだいとは多少の揉め事があったようです。父親が早々に遺言書作成を決断したのは、自身の相続の経験もあったと聞きました。
ところが、父親の1周忌の前に、妹2人から弁護士を通じて遺留分の請求がなされました。
公正証書遺言には、
「自宅の土地、建物を含めた財産の全部を長女と養子の長女の夫に相続させる。」
付言事項に、
「長年同居し、面倒を看てもらった長女夫婦に感謝している。先代から苦労して守ってきた土地は、売ることなく長女夫婦に維持してもらいたい。二女、三女はこの父親の意思を理解し、遺留分は請求しないこと。今後も姉妹仲よくすること。」
と、書かれていました。
しかし2人の妹には、父親の気持ちは届かなかったようでした。
長年の介護のため、父親の預貯金はほとんど残っておらず、鈴木さんが相続した財産は自宅不動産のみでした。また、鈴木さん夫婦はすでに年金生活となっており、妹2人に支払うだけの金銭的なゆとりがありません。結果、妹2人への支払いのため、長年住み慣れた自宅を売却することになりました。
転居先は小さな中古の賃貸マンションで、これまでのようにペットも飼えず、かわいがっていた大型犬を泣く泣く手放すなど、思い描いていた生活と大きくかけ離れたものとなってしまいました。
両親と没交渉の長男、母親の死後に堂々「遺留分」を請求
60代の佐藤さんは、3人きょうだいの長女です。きょうだい構成は、1番目が長男、2番目が佐藤さん、3番目が妹です。両親と折り合いの悪かった長男は、大学を卒業後すると実家を離れ、その後はほとんど没交渉となっていました。
両親が高齢となり介護が必要になると、独身の佐藤さんは離職して介護を一手に引き受けました。結婚して新幹線の距離に暮らす二女は、月に数回通って佐藤さんを手伝っていました。
先に父親が亡くなり、続いて母親が亡くなりましたが、母親は自筆の遺言書を残していたため、佐藤さんと妹は家庭裁判所に検認手続きを申請し、検認を受けました。
自筆証書遺言には、
「自宅は長女、預金は二女に相続させる。」
付言事項に、
「介護してくれた長女・二女に感謝している。長男は遺言の内容を理解し、請求をしないこと。これからはきょうだい仲よく助け合うように」
と、書かれていました。
ところが長男は、この内容を一笑。当然のごとく遺留分請求をしてきました。
佐藤さんきょうだいは、まだ「長男は跡取り」という意識が残る世代ですが、兄は大学生卒業後、そのまま両親とも妹たちとも疎遠になっています。佐藤さんの両親も兄に頼ることはあきらめ、ずっと長女の佐藤さんを頼ってきたのです。
佐藤さんは施設入居を拒否する両親の介護のため離職してしまい、いまはパート収入しかありません。遺産の預貯金はごくわずかで、兄へ遺留分を支払うには、やはり自宅の売却しか方法がないため、頭を抱えています。
「苦労した子へのねぎらい」「きょうだい仲よく」親の思いは届かず
同様の事例は枚挙にいとまがなく、いずれも「きょうだい仲よく」「遺留分は請求しないこと」といった付言事項があることも、ほぼ共通しています。
亡くなった方の意思や気持ちは汲み取れますが、遺留分を侵害されている人にはさっぱり響かないようで、遺留分の請求がなされるケースが大半です。
また、このような相続トラブルになる場合、遺産のほとんどが自宅不動産で、それなりの価値がある物件であることも共通しています。
遺言書を残し、自宅不動産を相続させる人を指定したものの、遺産の大部分が自宅土地のため、遺留分の請求がなされると、不動産を売却するしか方法がないのです。
遺留分対策の具体的なスキーム
では、これらのようなケースで対策を立てるには、どうしたらいいのでしょうか。
遺産にそれなりの現金があればいいのですが、無理なら、生命保険などを準備し、遺留分相当の現金を渡せる用意をしておくことが望まれます。
それもむずかしい場合は、相続発生前、老朽化した自宅建物を建て直して建築費の借入をする、賃貸併用住宅にする、といった方法があります。借入をすれば資産を圧縮でき、賃貸併用住宅で家賃収入が確保できれば、遺留分の原資になります。
もし不動産を手放す決断ができるなら、相続発生前に売却し、自宅と賃貸物件とに分けて持ち替えておく方法もあります。それにより、借入のマイナスを利用する・土地をコンパクトにする・賃貸物件の評価減を組み合わせる、等により、評価を下げて遺留分も減らすことができるのです。
上記の事例のような事情がある場合の相続対策は、遺言書だけで終わりにするのではなく、遺留分対策まで視野に入れた対策が必須だといえるでしょう。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

