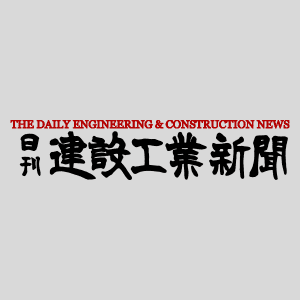石川県の能登、珠洲、輪島各市町の計3カ所で佐藤工業が進めていた能登半島地震による河道埋塞、県道の応急復旧が16日までに完了した。発災から1カ月半を経て一連の作業に一区切りを付けたが、被災地の復旧・復興に向けた取り組みはこれから本格化する。同社震災対策統括の谷口慎一土木事業本部副本部長は「富山発祥の企業として北陸の方々の笑顔を取り戻すのが使命だ」と力を込める。
佐藤工業は元日の発災当日に富山市の北陸支店に現地対策本部を設置した。1月6日には能登町内で土砂崩れによって埋塞した山田川の応急復旧に着手。地震によって高さ約100メートルの崖が崩れ、川の蛇行部に土砂やなぎ倒された樹木が堆積。当時は水位が約3メートル上昇し民家側に越水していた。バックホウで約7000立方メートルに及ぶ堆積物の除去を進め、2月1日までに水位を平常レベルに戻した。
1月7日に啓開作業を始めた珠洲市内の県道285号高屋出田線は当初予定した延長10・3キロの区間のうち、同中旬には6・3キロ地点まで啓開作業が完了。同地点の崩落規模が大きかったことや周囲にある集落の孤立状態がほぼ解消していたことから、国土交通省北陸地方整備局の判断で作業はいったん終えることになった。
高屋出田線の啓開現場に投入していた資機材は、1月18日中に輪島市内の県道269号滝又三井線の啓開現場に移動させた。すぐさま体制を整え、現地調査に取りかかった。
「孤立集落の解消に向けて交通確保は重要な役割であり、迅速に対応した。応急復旧ではスピード感が求められていた」と谷口氏。富山県内の実家で強い揺れを体感した同氏は、発災後は北陸支店に常駐して震災対応の指揮を執る。
県道269号滝又三井線では、輪島市三井町長沢の県道1号との交差点から西方向に4・8キロを担当。主に6カ所で土砂崩落や路面損傷があり、近くの滝又地区が孤立していた。現地調査では余震が続く中、倒木が重なり泥でぬかるんだ道を歩いて進んだ。ドローン撮影の写真などを組み合わせ、山間部の崩落状況を把握した上で、同20日から啓開作業に入った。
地滑りなどが広範囲で発生した2地点は土砂を撤去せず、流れ込んだ土砂を乗り越えるように約75~80メートルの仮設道路をそれぞれ整備。砕石を敷いてセメント改良を施し、脇を大型土のうで固めた。2月15日に地滑りで倒れかけた木々を作業員が伐採し重機で撤去。翌日に北陸整備局の検査を経て啓開を完了した。
現場代理人を務めた北陸支店土木事業部土木部の三野栄作作業所長は、「堆積した土砂の処理に特に苦労した」と振り返る。1日の作業中に数人ほど自宅の様子を見に訪れる住民たちからもらう激励や感謝の言葉が、心の支えになったという。一連の応急復旧には同社と協力会社合わせて一時最大29人が従事した。ベテラン職員と30代前半までの若手たちが組んで作業することで「災害対応の技術伝承につながった」(三野氏)側面もあるという。
応急復旧に当たり、佐藤工業はICTを積極的に活用した。まず衛星電話と衛星通信サービス「スターリンク」を導入して通信環境を整備。打ち合わせでは360度カメラを使い、東京の本社とリアルタイムで現場の状況を共有しながら施工方法を決めていった。二次災害を防ぐため、崩れたのり面に傾斜計を取り付けて数値を遠隔監視するシステムも導入。異常値を検知した場合はメールで警報が届くようにした。ドローンは現場の現状把握に加えて出来形管理にも利用し、被災エリアの日々の変化や作業の進み具合を確かめた。
応急復旧に着手した1月前半は能登半島内の道路事情が渋滞などで特に悪く、現場関係者にとって日々の通勤が大きな負担となった。職員らが滞在する富山県高岡市などから珠洲市の現場まで車で片道約4時間半、最長で6時間ほどかかった日もあったという。
労働環境を改善するため、同社は1月18日に石川県穴水町根木地区に「穴水対策基地」を開設。オフィスカーや宿泊用キャンピングカー、簡易シャワー、水を使わないバイオマストイレなどを配備した。谷口氏は「少しでも体を休められる環境を整えることで仕事と休息のめりはりがつき、職員や作業員らのモチベーションを維持できた」と話す。
同基地のある根木地区では、住民らの組合が管理する簡易水道で断水が続いていた。区長から相談を受けた同社が設備業者を手配して漏水箇所を修復し、1月中に断水を解消。被災地でのさまざまな支援ニーズへの対応でも、建設各社の総合力が発揮されている。