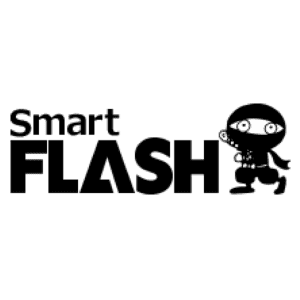嫉妬の対象になることは恐ろしいことである。隣人の悪意あるまなざしは端的に居心地の悪いものであるし、自分の幸福を後ろめたいものにするだろう。
いかに隣人から妬まれないようにするかという問題は、とりわけ小さなコミュニティでは生き死ににもかかわる、とにもかくにも抜き差しのならない関心事であった。
閉じた社会状況では、持つ者は自らの富や幸運をおいそれと見せびらかすわけにはいかない。隣人の嫉妬は、我が身の破滅へとつながる道である。
この点を明快に論じたのが、アメリカの人類学者ジョージ・フォスターである。以下では、フォスターの「嫉妬の解剖学」という論考をもとに、小さなコミュニティにあって、人々がどのように嫉妬を恐れ、それを回避してきたかを見ておくことにしよう。
まず、農耕社会のような閉じたシステムにあっては、人々の損得はゼロサムゲームになる傾向が強いという。つまり、生産の拡大や経済成長といった資本主義的な観念とはほとんど無縁なため、ある人物、ある家族の利益は必然的に誰かの損失にそのまま結びつきやすい。
そのようなコミュニティでは、人々は隣人からの制裁を恐れるあまり、他人より多く持つことを望まない。他人より多く持つことは、それだけで妬みや憎悪の対象になりかねないからだ。
それでは、隣人の嫉妬をどのようにして避けることができるだろうか。フォスターは、私たちが隣人の嫉妬を恐れ、それをなんとか諌めようとするとき、その行動にはおよそ4つの戦略があると言う。
(1)隠蔽
最初の戦略は「隠蔽」である。つまり、妬みの対象になりそうなものを隣人の目につかないところに隠すというものだ。
たとえば、ツィンツンツァンというメキシコのある町では、子どもを持つことは妬みの対象になるため、妊婦は腹部をきつく締め上げ、妊娠の事実をできるだけ隠そうとするという。
また、いくつかの部族には、夫が産みの苦しみを模倣する「擬娩」と呼ばれる風習があるらしい。これもまた、人々の視線を妻や子から夫へと移すためのある種の隠蔽戦略ではないかと、フォスターは指摘している。
これは私たちの日常行為を振り返ってもよく分かる。たとえば大学業界では、自分の就職や異動について、内定段階では家族などのごくごく親しい人以外には公言しないほうがよいという不文律がある。
これは、競争や嫉妬が激しい研究者コミュニティにあって、どこからか話を聞きつけた悪意ある誰かが、自分の成功を妨害する(たとえば怪文書のようなもので)ことを避けるためであろう。
もちろん過去にそういうことがあったに過ぎず、最近ではそのような妨害工作はないと信じたいところだが、なぜかいまだに律儀に守られている慣習である。これもまた、他人の嫉妬を避けるための幸福の隠蔽であると言える。
(2)否認
しかし「隠蔽」がつねにうまくいくとは限らない。隣人は悪意あるまなざしでたえずこちらをうかがっている。うまく隠したつもりでも、こちらのふとした仕草や噂を通じて、火種は人々の口の端を流れていく(嫉妬者は、引っ越しや不自然な沈黙といった何気ないヒントからも他人の成功やライフチャンスを勘繰るものだ)。
隠蔽に失敗するとき、次なる戦略として繰り出されるのが「否認」である。これはいわば他者からの称賛やお世辞に対して「いやいや大したことないですよ」と謙遜する、日常的にもごくごくありふれたやりとりのことである。
つまり、他人の嫉妬を喚起するものの価値をあえて否定したり低く見積もることで、妬みを和らげようとするのだ。「優秀なお子さんですね」と言われれば、「いやいや、うちの子は本当に落ち着きがなくて……」といった具合である。
生態人類学の分野でも、部族社会がどのように妬み感情をコントロールしているかが注目されている。南アフリカのカラハリ砂漠に住むブッシュマンについての報告によれば、ブッシュマンたちは狩猟で大きな獲物を得ると大きな喜びに包まれるが、獲物を射止めた張本人の狩人には謙虚さが求められ、この歓喜の輪に加わらない。
獲物を射止めた狩人には、謙虚で控え目な態度が要求される。大物を仕止めた狩人は、キャンプに帰ってきても、黙って、誰かが話しかけるまで坐っており、「今日はどうだった」と尋ねられても、静かに、「ほんの小さなやつを見かけただけさ」と答えるものだという。(掛谷誠「「妬み」の生態人類学──アフリカの事例を中心に」大塚柳太郎編『現代の人類学1 生態人類学』至文堂、1983年、236頁)
これも自身の手柄を「否認」することによって、妬みの発生を抑制しているものと考えてよいだろう。自分の成功を誇示しすぎないことが、とりわけ小さなコミュニティにおいてはいかに重要であるかが分かる。
(3)賄賂
ただし、こうした「否認」によっても嫉妬者はなかなか見逃してはくれず、こちらをひきつづき注意深くうかがっている。「隠蔽」や「否認」によってうまく妬みを抑えられないときには別の戦略が必要になる。
それが「賄賂」である。これは、競争に敗北した者の失望感を和らげる象徴的な分け前のことである。勝者は嫉妬者にちょっとした分け前を与えることによって、妬み心を相殺しようとするわけだ。
たとえばヨルダンの宿では、宿泊客が何かを褒めようものなら(たとえば「素敵なカップですね」というように)、主人は「よかったらお持ちになってください」と言わなくてはならない。こうすることで主人は客の嫉妬心を抑制することができると考えられているからだ。
いうまでもなく、このやりとりにおいて、客のほうは主人の申し出を辞退することが期待されているのだが、ここではきわめて高度なコミュニケーションが行われている。
私たちの社会でも、結婚式で新婦が投げるブーケや、旅行先で購入するお土産にもそのような分け前としての機能が認められる。そうした特別な機会を享受していない相手の嫉妬を避けるための同様の仕掛けが、社会のあちこちに認められるだろう。
ついでに言えば、日本ではあまり見かけないが、レストランでチップを払うという慣行も、少なくともその起源にあっては、ウェイターの嫉妬を抑えるための分け前であったとフォスターは分析している。飲食物は典型的に妬みの対象であり、チップを渡すことで安心してそれらを楽しむことができるのである。
(4)共有
これらいずれの戦略も十分に機能しないとき、最後の拠り所となるのが「共有」である。つまり、上記のいずれの戦略も功を奏さないとき、嫉妬を避けようとすれば、分け前のレベルをはるかに超えて自らの財や幸福をシェアするしかない。
たとえば、ラテンアメリカの農村コミュニティでは、マヨルドーモ(現場監督のような人)が定期的な祝祭を主催する。富を余分に持つ者は、宴会を催して、そこで食べ物や飲み物、花火などを派手に供することによって、コミュニティ内の不均衡をもとの水準に戻そうとするのである。
これは、いわば余分な富の破壊にほかならない(P・デュムシェル/J・P・デュピュイ『物の地獄──ルネ・ジラールと経済の論理』織田年和・富永茂樹訳、法政大学出版局、1990年、21頁)。
彼はこれによって莫大な借金を背負うこともあるが、これは自分の暮らし向きを悪くすることで、裕福でない隣人の嫉妬を避けていると考えられるだろう。
ここまで隣人の嫉妬に対する恐怖と、それを回避するためのいくつかの戦略について概観してきた。そこには多かれ少なかれ、私たちがふだん何気なく行なっている振る舞いも含まれていたはずだ。
だが、じつは嫉妬恐怖の話にはまだ続きがある。つまり、嫉妬される恐怖のほかにも、あるいはそれ以上に恐ろしいことがあるのだ。
フォスターは、隣人に嫉妬されることの恐怖のほかに、2つの恐怖について言及している。
●自分が嫉妬していると他人に思われる恐怖
●自分が嫉妬していることを自分で認める恐怖
こうした恐怖は、フォスターが対象にした閉じた農耕社会に限ったものではなく、むしろ現代社会にも多分に通じるところがある。いずれにせよ、嫉妬への恐怖は果てしなく続くことになる。
※
以上、山本圭氏の新刊『嫉妬論 民主社会に渦巻く情念を解剖する』(光文社新書)を元に再構成しました。私たちはなぜ嫉妬に狂うのか、政治思想の観点から考察します。
●『嫉妬論』詳細はこちら