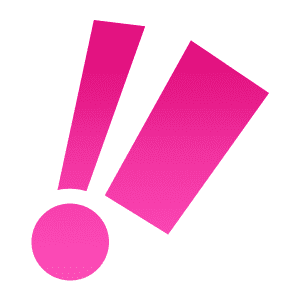町田そのこのベストセラー小説を『八日目の蝉』の成島出監督が映画化した『52ヘルツのクジラたち』が、3月1日から劇場公開。幼少期から虐待を受け、高校卒業後に3年もの間義父の介護を強いられた貴瑚(杉咲花)は、トランスジェンダー男性の安吾(志尊淳)に出会い、どん底の状態から救われるがーー。貴瑚の“痛み”を全身全霊で請け負った杉咲の芝居に圧倒されるが、彼女が本作で貢献したのは、それだけではない。脚本制作の準備段階から、映画が作られ、観客に届くまでの各セクションに携わっているのだ。俳優・杉咲花のものづくり、その現在地に迫る。
■“脚本づくり”で得た新たな視点
――杉咲さんは本作への出演が決まったのち、長い期間、脚本の改稿作業にも関わったと伺いました。当初から変わらなかった“核”、あるいは対話の中で新たに核になっていったものについて教えて下さい。
杉咲:私は、人は一人一人かけがえのない人生を生きていて、誰もが生まれてきたことを祝福されるべきだと思っています。制作陣の皆さまと価値観を擦り合わせていくなかで「ひとりでも多くの観客が居場所を見つけられる物語にしていくためには」ということを確認していく時間だったようにも感じます。
――ある種、作品全体を俯瞰(ふかん)で見た演出的な視点でもありますね。杉咲さんの中で、“潜る”や“生きる”といった演者の主観的な感覚とのバランスはどのように両立されていたのでしょう。

杉咲:言葉にするのはなかなか難しいですが、脚本打ち合わせの際は「自分が作品を受け手として観ていたらどう感じるのか」という思考が働きます。しかし台本に落とし込まれ現場に立つときにはそうした時間(受け手側の思考)とは切り離され、演じる役柄として身体に反応が起こることに素直でいるような感覚です。
――今回、初期段階から作品に関わったことで、以降のご自身の表現に対する変化はありましたか?
杉咲:今年(2023年)は『52ヘルツのクジラたち』以降お芝居をしていなくて、自分にどんな変化が生まれているのかは正直まだわかりません。ただ、物語が固まっていくまでの過程に参加させていただいたことで自分の視点にはなかった気づきが本当にたくさんありました。多種多様な方々のご意見を伺えたことで、自分自身の価値観も更新されていった感覚があります。
■“気づき”が生まれる作品に関わっていたい
――貴瑚はさまざまな搾取をされてきた人物ですが、傷ついた人物であっても無意識的に他者を傷つけてしまう可能性があるということを本作は描いていますよね。『市子』や『楽園』など、表層的ではない人物像、つまり人物の善なる部分とそうでない部分の両面を描いた作品に杉咲さんは出演してきた印象がありますが、惹(ひ)かれるポイントなのでしょうか。

杉咲:自分は人の欠損といいますか、完全ではないところに惹(ひ)かれる部分がある気がしています。失敗や反省は誰しもが経験することで、そのうえでどんな変化をしていくのか。そういった姿が描かれるような作品に、現実を生きる自分自身も勇気をいただくことがあるんです。
――杉咲さんが以前おっしゃっていた“見る者に気づきを与える”効果を内包している点も、重要なファクターかと感じます。
杉咲:この仕事を始めたころは、物語を娯楽として楽しんでいる感覚が強かったんです。けれど成人して選挙に参加できるようになったり、コロナ禍など社会の大きな変化を経験するなかで、自分がどんな視点で社会を見つめているか徐々に理解をしはじめて、この先自分はどのように生きていきたいかを問われている感覚が強まってきました。そうなると、なにか世の中に対してアクションを起こしたい気持ちになりますし、実際に署名などで参加することもあるのですが、変化はなかなか実感できなかったりして。それでも無力ではないことを信じて、行動し続けることの大切さをいまも感じているのですが、その他にも、自分の生活を通してたった1mmでもいいから変化のきっかけになるものを探したいと思ったときに、それはやっぱり、作品に関わることだと思ったんです。

もちろん、物語が誰かにとっての安らぎや感動、癒しであることの必要性は感じています。しかしそれと同時に、その中のたった10秒でもいいから、小骨のような引っかかりが生まれる作品に関わっていたい気持ちがあって。やっぱり、生活していると自分のすぐ近くに広がっている光景で精一杯になってしまいますし、そこから一歩出た場所のことを“外側の世界”のように他人事として捉えてしまいがちですが、映画に描かれているような、さまざまな境遇を持つ人たちも自分たちと同じように人との関係に悩んだり励まされたり、お腹を空かせたりしながら朝がやってきているはずで。そういうことに実感を抱くことが出来たなら、ほんの少しだけ世界の見え方が変わるのではないかと思うんです。
だからこそ、何よりもまず自分の生活をおろそかにしないこと、そして世の中に対して敏感であること、それを自分がどう受け止めているのか知ろうとすることが大事なのではないかと思っています。
■「現場に行ったら丸腰で立っていたい」
――脚本をブラッシュアップする作業の参加にとどまらず、『エゴイスト』でLGBTQ+インクルーシブディレクターを務めたミヤタ廉さんを紹介されたり、成島監督はもちろん撮影後も宣伝チームと話し合いを重ねたりと、杉咲さんはさまざまな形で尽力されてきたと伺っています。

杉咲:今回こういった関わり方をさせていただいて、現場に行って演じることだけが物語に責任を持つことではない、と感じました。脚本打ち合わせに参加するといっても「ここは絶対に変えてください」ということではなく、一意見として自分が違和感を覚えたことを共有して、それを受けて制作側の意図を知ることであったり、「確かに精査していく必要があるかも」というやり取りが生まれることが、作品にとって健康的な時間になるのではないかと感じています。それは労力がいることでもありますが、その時間を必要なものとして受け止めてくださる制作陣の方とご一緒できたことは、本当に幸運なことでした。
――そのうえで現在の杉咲さんが思う“いい芝居”とは何なのか、とても気になります。

杉咲:矛盾かもしれませんが、「いかに表現しようとしないか」がいいお芝居につながるのではないかと思っています。物語のなかで息づく人物を表現するには、たった一瞬だけ目の前で起きていることを“真実”として捉える必要性があるのではないかと思っていて。もちろん机の上で思考を巡らせる時間も大切だと思うのですが、現場に行ったら表現の欲望を手放して、丸腰で立っていたい。それができる瞬間は自分にとってはかなり貴重で稀(まれ)なことですが、出来ることならずっとそんな表現ができたらと思うし、出口を決めず自分のコントロール下から離れたとき、初めて辿り着けるような表現をいいお芝居と言えるのではないか、と、いまは思っています。
(取材・文:SYO 写真:松林満美)
映画『52ヘルツのクジラたち』は、全国公開中。