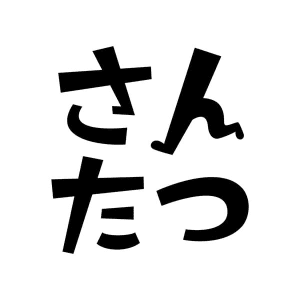大河ドラマ『光る君へ』で、その存在感で視聴者にとって大きな印象を残しているのが、毎熊克哉さん演じる謎の男・直秀である。
史実には残っていない、散楽一座のひとりである彼は、藤原家に盗賊に入るなど、謎の多い男になっている。それでいて主人公まひろのサポートをしてくれる彼は、『光る君へ』の物語に欠かせない存在となりつつある。
そんな彼が、第八話「招かれざる者」で語ったのが、「都の外でも暮らしたことがある」経験。
いまは京で散楽を演じている彼は、「丹後や播磨、筑紫」で暮らしていた、というのだ。
まひろは自分が見たことのない海を、彼が見たことがあると聞いて、自分も見てみたい、と語る。
ひとり向かった須磨で、海を眺める光源氏
……ここで『源氏物語』の話に入ると、実は『源氏物語』は宮中を中心とした王朝貴族物語である割に、存外「都の外」が舞台として登場する作品である。
『源氏物語』に出てくる、「都の外」の物語。その筆頭が、直秀が暮らしたことがあるという「須磨」だった。
『源氏物語』の主人公である光源氏は、朧月夜(おぼろづきよ)とのスキャンダルを契機に、須磨で蟄居(ちっきょ)することを決める。
よく誤解されるのだが、光源氏はスキャンダルが起きたから須磨に「流刑になった」というわけではないのだ。光源氏は政敵である右大臣家の娘と恋愛してしまったがために、光源氏の立場を弱くしてやろうと目論んだ敵方が、天皇謀反の噂を流そうとしたのだ。そこで光源氏は自ら反省の意向を示すために、須磨で謹慎することに決めるのである。須磨という場所は、自ら向かったといっても過言ではないのだ。
しかし紫の上という妻も京において、ひとり向かった須磨。そこでは京都ではなかなか見られない海も眺めていた。それこそ、直秀が語ったように。
須磨で長く住むとなると、ひとりでいるのに耐えられない、と源氏は思った。
しかし一方でこんなひどい住居に紫の上を連れてくるわけにもいかない。源氏は「ひとりでよかったんだ」と思いなおすことにした。
実際に住んでみると、京と須磨で違うところは多々ある。
「源氏の君なんて、まったく知らない」という庶民が普通にいる。そんなことすら、源氏にとっては初めての経験だったので、とても面白かった。
あるとき、煙がただよってくる。
「おお、これが『古今和歌集』で
須磨の海岸にいる漁師が、塩を焼いている。風がとても強いので、煙は思いもしない方向へたなびいてしまった……(それと同じで、女性は誘惑に負けて違う男性の方へ向いてしまった)
須磨の海人の塩焼く煙風をいたみ思はぬ方にたなびきにけり
(『古今集』恋四、七〇八、読人しらず)
と読んでいた、あの漁師が塩を焼く時の煙かな?」
と源氏は思った。が、実際はうしろの山で柴に火をくべているところで出た煙だった。
珍しくて、思わず歌を詠んだ。
山で住んでいる庶民が、小屋で焚く柴のように……故郷の恋人の便りもしばしば来てほしいなあ
山賤(やまがつ)の庵に焚けるしばしばも言問ひ来なむ恋ふる里人
季節が冬にうつり、雪の嵐が吹きすさぶ頃。空もぞっとするほど寂しい。源氏は琴を演奏し、従者の良清に歌わせ、大輔が横笛を吹いて、みんなで音楽を奏でた。源氏が心を込めて琴を演奏すると、ほかの楽器担当は演奏をやめ、みんなで涙を拭った。
〈原文〉
かの御住まひには、久しくなるままに、え念じ過ぐすまじうおぼえたまへど、「我が身だにあさましき宿世とおぼゆる住まひに、いかでかは、うち具しては、つきなからむ」さまを思ひ返したまふ。所につけて、よろづのことさま変はり、見たまへ知らぬ下人のうへをも、見たまひ慣らはぬ御心地に、めざましうかたじけなう、みづから思さる。煙のいと近く時々立ち来るを、「これや海人の塩焼くならむ」と思しわたるは、おはします後の山に、柴といふものふすぶるなりけり。めづらかにて、
「山賤の庵に焚けるしばしばも言問ひ来なむ恋ふる里人」
冬になりて雪降り荒れたるころ、空のけしきもことにすごく眺めたまひて、琴を弾きすさびたまひて、良清に歌うたはせ、大輔、横笛吹きて、遊びたまふ。心とどめてあはれなる手など弾きたまへるに、他物の声どもはやめて、涙をのごひあへり。
(『新編 日本古典文学全集21・源氏物語(2)』より原文引用、訳は筆者意訳)
須磨へ行ったことがないはずの紫式部がどうして描写できたのか?

『源氏物語』には、この後も須磨や明石の描写が続いている。
それにしても、「古今和歌集で読んだ塩の焼いている煙かと思いきや、うしろの山で柴に火をくべている煙だった」という描写なんて、すごく臨場感があり、どのようにして取材したのだろう?と私は以前から気になっていた。
おそらく紫式部は須磨へ行ったことがないはずなのだ。当時の貴族の娘のなかで、親の転勤などもないのに須磨に行く機会はほとんど存在しないと言ってよい。しかし紫式部は光源氏の物語の舞台として須磨や明石を選び、実際に海辺を光源氏に歩かせている。いったい、どのように想像していたのだろう?と不思議に思っていた。
一説には、九州へ転勤になっていた夫から話を聞いて書いたのではないか、と言われている。たしかに九州から戻ってくるとき、須磨を通っていても不思議ではない。夫の話をもとに想像をふくらませて書いたというのもおかしくはない。
しかし、この須磨の描写を読んでから、『光る君へ』を見ると……「もしかしたら直秀から聞いた話をもとに想像を膨らませたのかもしれない」なんて思えてくる。もちろん直秀は架空のキャラクターであるし、現実にはいないが、それでも光源氏が自分を知らない庶民に対して新鮮な気持ちを抱く場面などは直秀の面影が見えるかのようだ。
『源氏物語』は、須磨、宇治など、京都ではない場所の風景描写もとても魅力的だ。紫式部自身がどの程度その土地を歩いていたかはわからないけれど、それでも都の外に出たことのない京の貴族たちに「須磨の海って、どんな場所なのだろう」と想像を掻きたてさせたことは間違いないのである。
ぜひこれを読んだ方も、須磨や明石に行った際は、海を眺めてみてほしい。紫式部の想像した海辺のさびしい冬の雪の景色を、見ることができるかもしれないから。

文=三宅香帆 写真=PhotoAC、さんたつ編集部
三宅香帆
書評家・作家
書評家、作家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院卒。著書に『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『(萌えすぎて)絶対忘れない! 妄想古文』他多数。