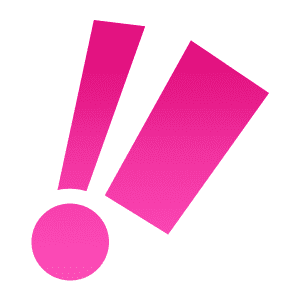見上愛が初の映画単独主演を務める松居大悟監督の最新作『不死身ラヴァーズ』より、ポスターと予告編が解禁され、主題歌情報が発表された。
本作は、高木ユーナによる同名漫画(講談社「別冊少年マガジン」所載)の映画化。主人公・長谷部りのを本作が初の映画単独主演となる見上愛が飾り、りのの運命の相手役の甲野じゅんを、佐藤寛太が務める。
長谷部りのが“運命の相手”と信じて追いかけるのは、両想いになった瞬間、この世界から忽然と消えてしまう甲野じゅん。2人は人生の中で何度も出逢い、その度にりのは「好き」と伝え、両想いになり、じゅんが“消える”という出来事を繰り返していく。それでも諦めないりののどこまでも真っすぐな「好き」が起こす奇跡の結末とは――。
解禁された予告編映像は、中学生の長谷部りの(見上)が、運命の相手だと信じる甲野じゅん(佐藤)へ好きという思いを伝える場面から始まる。しかし、両思いになると甲野じゅんは、りのの前から忽然と姿を消してしまう…。
その後も、甲野じゅんは、時に高校生として、時に車椅子に乗る青年に姿を変えて、再びりのの前に現れる。その度に何度も彼に恋をして「好き!」と思いを伝え続けるりのだが、親友の田中(青木柚)やバイト先の花森(前田敦子)に、気持ちを否定されてしまう。
やがてりのは大学生となり、甲野じゅんと再び出逢うことになる。最後に「今日という日は、もう一生来ないから…」という甲野じゅんと、「消えたっていいよ。私が消さないから…」というりののセリフの意図とは?
あわせて解禁されたポスタービジュアルは、予告編映像のラストで2人が肩を寄せ合うシーンを切り取ったもの。全力で「好き」を伝えていくも、両思いになると消えてしまう甲野じゅんを前に、「じゅんくん、消えないで…」と語るりのの、切なさ溢れる仕上がりになっている。本音を言い出しにくい今の時代だからこそ、「好き」という気持ちを真っすぐに伝える主人公の姿に、きっと胸を打たれるだろう。
また、本作の主題歌に、スカートが書き下ろした新曲「君はきっとずっと知らない」が決定した。スカートは劇伴も担当する。
監督の松居大悟は、「消えながらも突き進むラブストーリーには、透き通るようなメロディが流れたらいいな」と思い、本作の主題歌と劇伴の制作をスカート・澤部に依頼。しかし、澤部は作中に既成の楽曲があることを知り、「主題歌は映画のためにも、自分がやらないほうがいい」と一度断ったという。
そんな澤部に対し松居監督は、すごく映画のことを愛してくださっている感じがして信じられたからこそ主題歌を担当してもらいたいとより強く思ったと明かす。結果、映画音楽から主題歌の全てを澤部が担当することになった。
澤部は「りのでありながら、りのになりすぎず、物語を包めるような曲を書くのはとても気の張る作業でした」と振り返りながら、「結果的にすこし不思議で噛み応えのあるポップ・ソングを投げることができて今(というか曲ができてからずっと)、私は本当に嬉しい気持ちでいます」とコメントを寄せている。松居監督が託した思いによって、生み出された“噛み応えのある楽曲”にも注目したい。
映画『不死身ラヴァーズ』は、5月10日より劇場公開。
※松居大悟監督、スカート・澤部渡のコメント全文は以下の通り。
<コメント全文>
■松居大悟監督
消えながらも突き進むラブストーリーには、透き通るようなメロディが流れたらいいなと思っていました。登場人物の心情を追い抜くことなく、追いかけることなく、並走しながら景色が広がるような。
そんなことをイメージして、スカート澤部さんの歌声やメロディに憧憬を描いて、お願いしました。
澤部さんは打ち合わせ時に、劇中でりのが歌う既成の楽曲があることを大事に思ってくださって、「主題歌は映画のためにも、自分がやらないほうがいい」と言っていて。その言葉を受けて、変ですけど、そう考えていただける澤部さんにぜひ主題歌もやってもらいたいなと思いました。
作ってもらえないかな、どうかなとソワソワしてましたが、結果、映画音楽と主題歌の全てを澤部さんに手がけていただきました。そして、とってもいいんです!
何かをわかることではなく、わかったふりすることではなく、わかろうとすることに光が当たるような作品になった気がします。
■スカート・澤部渡
(松居監督のコメントにもありましたが)『不死身ラヴァーズ』のラッシュを観た時、りのが歌っている劇中曲こそこの世界の主題なのでは?と考えてしまい、実際にその曲の方が相応しいのではないか、と提案してしまったぐらいなのですが、監督から「その曲がエンディングだと、りのの物語になりすぎる」と言われた時に腑に落ちたのでした。りのでありながら、りのになりすぎず、物語を包めるような曲を書くのはとても気の張る作業でしたが結果的にすこし不思議で噛み応えのあるポップ・ソングを投げることができて今(というか曲ができてからずっと)、私は本当に嬉しい気持ちでいます。