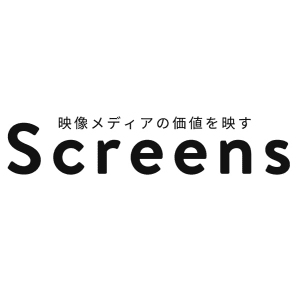原田泰造主演の土ドラ『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』(東海テレビ・フジテレビ系、毎週土曜23:40~)の第1話見逃し配信の再生回数が、1週間(1月7日~1月14日)で約89万回再生(TVerとFOD無料の合計値)を記録。2022年1月放送の『おいハンサム!!』初回の約78万回再生を超え、東海テレビ制作のドラマ初回放送としては歴代1位の再生回数(※配信数はビデオリサーチにて算出)となった。
【動画】『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』TVerで配信中!
本作の主人公である昭和の“おっさん”が新しい“常識”と出会い、少しずつ変わっていく本作。テレビにおいても「放送」や「配信」など、生活者がテレビコンテンツを楽しむ選択肢が増え、従来の視聴スタイルから変化が起きている。本作と重ね合わせながら、『おっパン』のプロデューサーである松本圭右氏にインタビュー。テレビマンとして考える放送と配信のこれからについて伺った。

松本圭右氏
■ターゲットに向けたリリースを意識
松本氏は東海テレビに入社後、報道部でニュースを担当。その後、ドラマ制作部へと異動となった。当時、東海テレビは“昼ドラ”を制作。先輩プロデューサーのもとでドラマ作りを学んだ。
単発ドラマでプロデューサーデビュー後、昼ドラでは様々なことを経験。現在、45歳の松本氏は「自信と挫折を繰り返しながら、なんだかんだと20年やらせていただいています」と自身の経歴を振り返った。
そんな松本氏が手がけているのが『おっパン』である。LINEマンガで連載中、脚本家の藤井清美氏に教えてもらったことをきっかけにドラマ化へと動いた。藤井氏は本ドラマの脚本を担当している。

改めて、松本氏にどんな作品なのかを問うと「常識に囚われた堅物の昭和のおじさん・沖田誠(原田)が、ある青年との出会いによって、自分の常識を(現代に合わせて)アップデートしていきます。アップデートする理由のひとつが、愛する家族のことを理解したいし、傷つけたくないという思いなんです。本作は、多様性というテーマのもと、LGBTQから、推し活、オタク活動など、趣味嗜好も取り扱っていますが、根本は人と人との結びつきの物語です。自分としては、おじさんが成長するロールプレイングドラマ、という印象で作らせていただいています」と述べた。
原作者の練馬ジム先生には、長文のメールで思いを伝えドラマ化が決定。松本氏は「原作では、言語化できていなかった感情、モヤッとしたものを明快に見させていただきました。答えというよりも、“どうしたらいいんだろう”と思えるきっかけをもらえたんです」と熱く語る。
東海テレビ制作のドラマ初回放送としては歴代1位の再生回数だった本作。新たに実施した施策はあったのだろうか。
「地上波テレビは一度しか流れませんが、配信があると、見てもらえる土壌が増えますよね。作り手としては、多くの人に見ていただいた方が嬉しいので、リリース作りを意識しました。放送前のリリースは4つに分け、原作ファン、ドラマファン、キャストファンなど、すべて違うターゲットに向けて作りました」

キャスティングも光った。「主演の原田さんをはじめ、FANTASTICSの中島颯太さん、東啓介さんなど、“この人が出ていたら見る”というファンを持っていらっしゃる方も多かったので、事前及びその俳優さんが注目される回の前には、告知だけではなく、キャストの声も届くリリース作りを意識しました。また、視聴者が感情移入できるポジションにいて、ファンも多い富田靖子さんと松下由樹さんは、デビュー作が一緒で、ガッツリお芝居をするのは40年ぶりだったそうなんです。せっかくなので、リリース用に対談を組ませていただきました。そうしてたくさんの入り口を設け、どこから入っても面白みを感じていただけるリリース作りを意識しましたね」。
とはいえ、内容が伴っていないとここまで結果を出すことができない。ドラマ作りにおいて意識したことはなんだったのだろうか。松本氏は「こういったドラマに陥りがちなのですが……」と前置きしたうえで、こう教えてくれた。
「『説教臭いドラマにだけはしないようにしよう』と言っていました。“こうあるべきだ”という見え方になった瞬間、原作の良さがなくなるし、見ている人たちも肩に力が入って楽しめなくなると思ったんです」
そしてもうひとつ。クランクイン前にキャストへ向けて、あることをしたと教えてくれた。それは“手紙”だった。
「主要レギュラーの方にはお手紙で『こういう企画で、なおかつこういうキャラクターのつもりです』と事前にお伝えさせていただきました。必ずしもその通りにしてほしいわけではなく、作り手としての思いを伝え、あとはお任せします……というかたちなので、そういう意味では、同じ方向を向いてくださったなと思います」
手紙は昼ドラ時代から実施していることで、先輩のやり方を真似たという。「手紙を書きながら、この企画をなぜやったのか、このキャラクターをどういうつもりで作ったのか、もう一度再確認できますし、たとえお渡ししなくても、手紙を書くことに意味があるなと思っています」と仕事をするうえでも、良い作用になっていると明かした。
■“変わる”ことを厭わない世代が作る今後のテレビ
もはや配信でドラマを見るのは当たり前になってきた昨今。制作者として、どんなことを感じているのか。
松本氏は、昭和とは生活様式が変わり、昔のように父親がビールを片手にナイター中継を見る……という時代は二度とないかもしれない、と語る。
「その中でどうやって“選んでもらうメディアになるのか、選んでもらえるソフトを作るのか”ということしかないと思います」
もちろん「自分で探さなくても触れられる」というテレビの良さもあるが、いずれはそういう見方すらもされなくなるかもしれない、と松本氏。「あえてテレビをチョイスしてもらえるものを作らないといけない、というのは、 危機感ではなく、今後あるべき姿としてイメージしています」と未来を見据えた。
ここで、ふと疑問が湧いた。まだ配信がなかったテレビの時代を知る松本氏にとって「変わること」に躊躇はなかったのか、ということだ。新しいことへの挑戦は恐怖がつきものであるが、松本氏は歩みを止めない。

「たとえば、主人公の誠はバブル期に片足を突っ込んでいる世代ですが、当時の成功体験もあるので、なかなかそこから抜け出せなかったと思うんです。(過去の誠のように)頑なに変わらない人が周りにいると、“自分は変わらなきゃな”と律することができる、というのはあるかもしれません」
続けて「“変わっていくのが当たり前”というのは、私のような40代前半〜中盤世代の強みかなと思います」と松本氏。「同世代を見ても、“こうでなければいけない”と思っている人間が誰もいないので、変わって当たり前だし、そこに乗るか乗らないかだけだと思うんですよね。今のテレビ業界を苦難とも感じていないですし、“そうなるよな。じゃあどうしよう”と、すぐに頭を切り替えられたのは大きいと思います」。
松本氏が、今回の現場で初めて行ったという「当事者キャスティング」にも触れておきたい。原作には登場しない、誠の娘・萌(大原梓)の大学の友人役に、車椅子ユーザーの俳優・田﨑花歩を呼んだのだ。
「ふだん生活をしていても、車椅子の方や白杖を持った方っていらっしゃるじゃないですか。でも、ドラマは、美男美女で作られた美しい世界になりがち。本当の“世界の美しさ”ってそういうことではなくて、いろんなことをひっくるめたリアルな美しさだと思うんです。そこをちゃんと描きたいな、と」
ドラマ的に車椅子であることの理由はない。ただ、そんな友達が大学にいる世界観でこのドラマを作りたかった、と松本Pは語る。
「田﨑さんは、小さい頃、ドラマや舞台を見るのが好きだったけど、ドラマの世界には健常者しかおらず、選択肢として(俳優になる)想像すらしたことがなかった、とおっしゃっていました。すごく重い言葉だなと思いましたね。見せる側が意識していなくても、『あなたたちには無理ですよ』と伝わるような作り方をしていたんだと思ったんです。今後、こうしたキャスティングを続けることで『私にもそういう道があるんじゃないか』と思ってくれる子供たちが1人でも増えれば可能性は広がるし、そういう時代を作っていかなきゃいけないな、と思いました」
終盤に向けて盛り上がっていく『おっパン』。見どころを伺うと、こんな答えが返ってきた。
「こういう人には“こうであるべき”みたいなカテゴライズされた答えなんて1つもなくて、それぞれの対話でいろんな物事が見えてくるドラマになっています。『人と人とのつながりって、めんどくさいけどいいよね』というところを感じてもらえたら嬉しいですね。最後、誠と彼を毛嫌いしていた家族が、一致団結して友達のために頑張るストーリーラインもあるので、沖田家の可愛らしさと頑張りを最後まで見届けていただけたら幸いです」
最後に、テレビマンとしての“今後”についても問うた。

「配信を含め、ものすごく贅沢で楽しい時代だと思うので、その中で選んでもらえるメディアとして生き残れるように頑張りたいです。どんなかたちであれ、面白いものを作れば、そこにはお客さんがいらっしゃると思うので、最後の最後までお客さんに対してだけは誠実にものづくりをやっていきたいです。本当は『おっパン』のような企画が通らない時代が来るのが一番いいなと思っていますね。会社に企画書を出したときに『何を当たり前のことを言ってんだ』と言われる時代になったら、本当の意味で良いのかな、と。せっかくメディアの世界にいるので、お父さん世代も含めて、みんなが生きやすい世の中を作れるといいなと思っています」