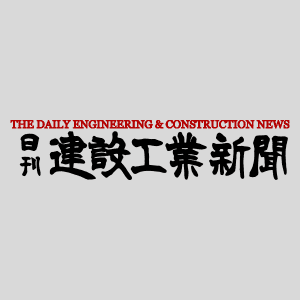土木学会(田中茂義会長)は14日、首都直下地震が発生した場合、被害規模が最悪のケースで1001兆円に上るとの推計結果を発表した。直接的な建築物や工場などの資産被害に、交通インフラや生産施設などの被害が経済活動に発災後約20年間及ぼす影響を加えた。耐震性強化など防災・減災対策を実行した場合の被害の軽減効果も試算。道路や港湾、漁港、建築物の対策に21兆円以上投じることで被害規模が369兆円縮減できると見込む。
土木計画学研究委員会に設置した小委員会が「2023年度国土強靱化定量的脆弱(ぜいじゃく)性評価・報告書」としてまとめた。小委員長を務めた藤井聡京都大学大学院教授は同日に東京都内で会見し「被害の深刻さを受け止め、適切なインフラ投資により被害が軽減できるということを認識してもらいたい」と呼び掛けた。
土木学会が首都直下地震の被害規模を試算するのは、「『国難』をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書」としてまとめた18年6月以来になる。今回の報告書では被害規模試算方法の前提条件を見直した。新たに東日本大震災後に得られた最新のデータや知見を反映したところ、前回試算した778兆円(資産被害47兆円、経済被害731兆円)から223兆円拡大し、1001兆円(同47兆円、同954兆円)に上った。経済被害試算954兆円のうち、道路寸断や生産施設損壊による被害規模は909兆円、港湾被害の交通寸断で45兆円と算出した。
首都直下地震に対する防災・減災を実行した被害の軽減効果もまとめた。公的支出19兆円程度を含めた21兆円以上の事業費を投じ道路や港湾、漁港、建築物の耐震強化策を実行した場合、被害規模を約4割、金額換算で前回報告書に比べ122兆円多い369兆円縮減できるとした。
発災後、復興にかかる期間も最大で23・9年から18・5年へと5年強の短縮効果を見込む。
土木学会は今回の報告書で全国の1級河川109水系を対象に洪水被害規模や被害軽減効果を初めて試算。気候変動による流量増加を加味した洪水の被害規模は537兆円(同280兆円、同257兆円)とし、堤防やダムの整備、河道掘削など計40兆円のインフラ投資による被害軽減効果を257兆円と算出した。
国内最大級の被害規模が予測される南海トラフ地震の試算結果は政府の検討状況を見てまとめる。