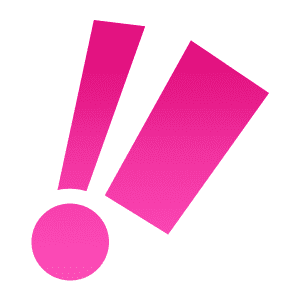「“GTO”グレート・ティーチャー・オニヅカが帰ってくる!」――第一報が発表されるとSNSを中心に大反響と歓喜の声を巻き起こした、反町隆史主演『GTOリバイバル』(カンテレ・フジテレビ系/4月1日21時)。約26年ぶりに鬼塚英吉役を演じる反町にとっても思い入れの強い作品ということで、熱い思いを語ってくれた。
◆何度もあった復活オファー 令和になって実現した2つの理由とは?
1998年の夏に放送された連続ドラマ『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作。元暴走族の高校教師・鬼塚英吉が、破天荒な行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
放送当時、大掛かりなロケーションや予想を裏切るストーリー展開、そして、破天荒な教師・鬼塚役にぴったりな反町の情熱的で力強い演技が話題を呼び、全12話の平均視聴率(世帯)は関東地区で28.5%、最終回は35.7%(ビデオリサーチ調べ)と、高視聴率を記録。また、反町自身が作詞し、歌いあげた主題歌「POISON~言いたい事も言えないこんな世の中は~」も大ヒットするなど、ドラマ史に残る人気を集めた。
今回復活する新作では、鬼塚が問題だらけの高校に教師として赴任。SNSでの誹謗中傷やさまざまなトラブルなど、ますます生きづらさを抱える令和の高校生と対峙し、鬼塚流の熱血授業を繰り広げる。
反町によると、この26年の間に何度か復活オファーはあったそう。しかし、「過去の作品をまた作るというのは俳優としてどうなんだろう?と。もっと違う役、もっと違う新しいものをやりたいという思いがありますから、前向きにとらえられないというか、どこか不安を感じ、またいいタイミングがあればという気持ちでいました」と振り返る。
そんな中、今回の復活に至った心境の変化を尋ねると、2つの理由があると語る。「1つは、僕自身、娘が2人いまして。学校、社会、大人に対して向ける彼女たちの“子どもながらの目線”というものが、当時24歳で鬼塚英吉を演じた僕自身の目線よりも、もうちょっと違った目線というか、深く感じられることが多くありました。そしてたまたま、僕が歌った『POISON』が、YouTubeなどで“赤ちゃんが泣き止む”と話題になった時に(笑)、改めて歌詞を読み返してみたんです。すると、“なんかいいこと言ってるな”っていうのが正直あり、これを今の時代に置き換えた時にどうなんだろう?と思ったんです。そうしたら、“あれ? もしかして、今の時代でももっと通用すんのかな?”という思いが生まれたんです」と明かす。
また「ちょうどトム・クルーズが『トップガン マーヴェリック』を久しぶりに復活させた時で、なんでこの人はたくさん代表作がある中で『トップガン』を今復活させたのかなって正直思ったんです。その時に、作品の内容もそうなんですけども、俳優としてのトム・クルーズの生き様に共感できたんです。すごいことだなって」と『トップガン マーヴェリック』でのトム・クルーズの姿からも大きな刺激を受けたという。「過去にお話を頂いた時は、“今はちょっと…”となりましたが、“今だったらできるな”って自分の中でつながったんですよね。ただ演じるだけじゃなくて、何かを訴えたいな、何かを伝えないなっていう“何か”がなければできないじゃないですか。今だったら鬼塚英吉が話せる何かがあるかなと自分なりに感じたのも、きっかけになりました」。
反町が本作で伝えたいこととは何だろう?「愛情ですね。生徒に対する愛情です」ときっぱり。「子どもたちは尊敬している先生はいるのか、先生から愛情をもらっているのか、先生は子どもたちのことを本当に親身に考えてくれているのかなど、社会のニュースや出来事に、“これはないよ”と感じることがものすごく多くて。鬼塚英吉は当時から生徒の目線に立って愛情表現をしてきたキャラクターなので、そこをこの令和の社会でも変わらず出していきたいなと強く思って臨みました」。
◆98年版生徒キャストの思いに感激

26年ぶりに『GTO』を復活させるにあたり、制作陣とは綿密な打ち合わせを重ねた。「台本も決定稿に至るまで準備稿は12稿までになりました。スタッフそれぞれが考える『GTO』の全てが一致するまでには、やはりそれなりの時間がかかりました。でも、26年前とは脚本家さんも制作陣も違ったので、そこのすり合わせが大事でしたね」と振り返る。「僕が最初から最後までこだわったことは、当時観ていただいた方に『これがGTOだよね』『これが言いたいんだよね』と思ってもらうということ。楽しみにしてくださっていた方に裏切りがないような形で演じたいし、そういう本を作りたい」とも。
今回の出演にあたり、過去の映像を観返したという反町。役作りとして何か特別に気にかけたことはないと話す。「今回はみんなで脚本をいろいろ作り、打ち合わせを重ねていく中で、自分の中に鬼塚の言葉やキャラクターが徐々にしみ込んでいくところがありました。なので、現場に立ったときには普通に『あ、この感じだな』というものがあったので、無理しているところはなく、26年前と変わらない自分がいました」。
本作には、26年前に生徒役を務めた池内博之、山崎裕太、窪塚洋介、徳山秀典、小栗旬、さらには鬼塚の親友・冴島役の藤木直人らが再集結することも大きな話題に。現場の雰囲気を聞くと、「しゃべんなくても当時のような雰囲気をすごく感じました。男同士だし余計な会話があるわけではないんですが、なんか懐かしいなっていうのを皆さん感じていたんじゃないかなと思います」との答えが。「意外と山崎くんがいろんなことを覚えていて。僕は過去のことは忘れっぽいというか、 “え? そんなことあったっけ?”という感じなんです(笑)。みんなでグループLINEを作ったんですが、池内くんが当時のスケジュール表を送ってきて、“なんでこんなの持ってるの?”ということがあったり」と笑顔。「みんなが個々に『GTO』という作品に対して、すごく愛情も思い出も全部背負いながら26年間いてくれたんだなっていうのが一番うれしかったです」。
◆50歳を迎えても鬼塚も反町も熱さは変わらない

反町は昨年50歳を迎え、今年は俳優デビュー30周年という節目の年を迎える。「自分が演じてきた役もそうですし、1つ1つの積み重ねが自分自身を作ってきていると感じています。作品や役というのは出会いだと思うんですが、今回の作品のように、言いたいことを言えたり、令和のこの世の中にメッセージとして伝えたいことを作品を通して伝えられる、それはすごく自分にとって価値のあることだと思っています」と俳優業のやりがいを語る。
この30年を振り返ってもらうと、「山あり谷ありというか、流れっていうのは、いい方向にいけば悪い方向にもいくし、悪い方向にいけばまたいい方向にもいく。その繰り返しだと思うんですよね。ずっと流れるかっていったら、この世界は自分じゃどうすることもできないことや、自分の考え1つではどうにかならないところもあったりするじゃないですか」と語る。「そういった部分では、30年間は振り返ってみるとあっという間だったんですが、ただ僕自身、俳優としてどういうふうになりたいかっていうのは、正直そこまであんまりないんです。1つ1つ選択をして自分の仕事に責任を持って向き合うことが、結果として自分という人間がどういうふうに変わっていくかということに繋がっていくと思っているんです。俳優というよりも、人間としてという、そちらに対する意識の方が強いですね」。
26年前は生徒役との年齢差も小さく、兄貴分のような鬼塚と生徒の関係が描かれた。50歳を迎えた鬼塚と生徒には、親子ほどの年齢差がある。「確かに僕もそれは現場で感じていて。今回は娘くらいの感じでもあるので、そこが当時とまたちょっと変わっている部分であり、鬼塚が大人になれた部分でもあります。でも、鬼塚も僕も50歳ですけど、とにかく熱くやるっていうのが『GTO』ですから。そのエネルギーが観てくださる方に伝わって、“あ、この瞬間っていいな!”と思ってもらえるよう、みんなで“熱さ”にこだわって作りました。令和の時代を生きる若い皆さんにも、このドラマが何かのヒントになったり、何かのきっかけになったらいいなと思っています。クライマックスの鬼塚のセリフに、僕が伝えたいメッセージを込めましたので、そこもぜひ観ていただけたらうれしいです」。
令和になってもブレない鬼塚を通して、反町が熱く伝えるメッセージをしっかりと受け止めたい。(取材・文:近藤タイスケ)
『GTOリバイバル』は、カンテレ・フジテレビ系にて4月1日21時放送。