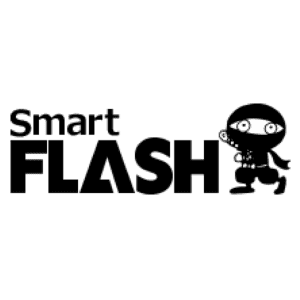沖永良部島の頭上運搬(1963年、写真:コシマプロダクション/アフロ)
ドジャースに入団した元オリックスの山本由伸投手は、2021年10月、オリックスのリーグ優勝の際に出たデイリースポーツの記事で語っている。前年のオフの時に、昔の女性が米俵を担いでいる写真を見て、こう思ったそうだ。
「昔の女の人が米俵を担いでいる写真。担げるの? って思うじゃないですか。コツを知っているから持って運べる。人間にはそれだけの力があるはずなんです。トレーニングしているわけではないのに、生きるためにこういうことができる。じゃあ筋肉じゃない。自分の体の重心の位置を明確にすることが大事。力で持ち上げているわけではなく、うまく乗せている」
そして投げることもまた同じだ、と感じるのだ。
筋肉とか力とか、の話ではなく、生きるために行なってきた身体を使ったさまざまな技法は、運搬手段、交通手段の発達により、必要がなくなったところから失われていった。
女性が米俵を担がなくてもよくなったのは、いかなる意味でも好ましいことだ。過酷な労働から解放されるために、人間は技術を革新し、科学を発達させてきたはずなのである。
そのような時代に生きていてもなお、現在の力や分析で明確に理解できないほどの身体づかいに出会うと、我々はたじろぎ、驚くが、その後、熟考し、その驚きから自らを変える力を得ることも可能なのである。山本投手の話はそういうことだと思う――。
「頭上運搬」は、日本では、伊豆諸島、南西諸島、瀬戸内沿岸、志摩、などで見られたといわれているし、アフリカや東南アジアなどではごく一般的に、今も使われている運搬方法である。手では運べないような重さ、具体的には30キロ以上のものを、何キロにもわたって運搬することができる。
日本国内では、地方にもよるものの、頭上運搬をしていた地域に生まれ育った2020年前後に80歳以上くらいの女性は、頭上運搬の記憶があり、今でも、やってくださいと言うと、できますよ、と言う。
これを読んでおられる方の多くは、頭にものをのせて運んでくださいと言われても、まずできないと思う。やったことがないであろうし、見たことも、おそらくある人の方が少ないだろうし、だから、はなからできないと思われるだろうし、おそらく現実に、できないと思う。
聞き取りでも、頭上運搬を行なっていた人たちは、幼いころから日常的に頭上運搬をしていた。だいたい4歳くらいから、頭の上に薪などをぽんとのせられて、運び始めたことが多く、実際の運び手としての労力が期待される思春期には、すでに頭上運搬に慣れていて、重いものがのせられるようになっていた、という話を聞いてきた。
これは、ものごころつく時期の幼いころから習熟してこそ、そして、できると思う「意識」があるからこその、身体技法なのだろう、と考えていた。誰でもできる可能性はあるが、幼いころから周りがやっているのを見ていて、自分も何かしらを頭にのせていたからこそ、できる、というものであろう、と考えていた。大人になってからやろうとすると、かなりの練習と習熟が必要とされる、と思っていた。
2019年当時、83歳だった、沖縄、石垣島に住むハツエさん(仮名)は、お嬢さん育ちだったので、幼いころは頭にのせて運ぶ必要もなかったし、やったこともなかった。
両親共に戦時中に亡くなってしまったから、戦後、なんとかして兄弟とともに生きていかねばならない。思春期に入ってから初めて、自分の体重より重いような芋を、それまでやったこともなかった頭上運搬で、畑から家までの6、7キロに及ぶ道のりを運ばなければならなくなったのだという。
しかも、彼女は、30キロを超えるような芋の入ったざるを、「自分で」頭にのせていたというのだ。ハツエさんは、自力でまず、たくさんの芋の入ったざるを膝にのせ、そこから耳の脇を通して少しずつ自分の頭の上にのせたのだという。
「耳の脇ぎりぎりで上げていくから、耳がちぎれそうなほど痛かった」
重いものを頭の上にのせた時は、両手を離すことはできず、必ず片手で、ざるをつかんでいた。片手でざるを支え、もう片方の手は、振る。片手だけでも、振らないと、歩けない。
本当は両手を振った方がよいので、軽い時は両手を振るけれど、重たい時は無理だから片手だけでも振る、というのである。手を上げていると疲れるから、時折、ざるを支える手を替える。
誰にも教わっていないし、誰にも教えていない。やらなければならなかったから、やるようになった。
自分たちよりも若い世代(2019年に70代の人たち)は、もう、リヤカーも自転車も使えるようになってきましたし、車もほどなく出てきましたから、頭では運んだことはないでしょう。
何度も言いますが、誰にも教わった覚えはないし、自分も誰かに教える気もなかった。これは、やらなければならない、と思えばできるもの。人間の本能に近いものではないですかね……と、ハツエさんは言うのだ。
戦中戦後の沖縄などのような厳しい非常事態は、もう二度と訪れてほしくない。彼女たちがむりやり重くて熱いご飯や、自分の体重より重い芋を運ぶような時代は、もう来てほしくない。そんな過酷な労働が必要ないように、私たちは運搬道具や車を作ってきたのである。
しかし、彼女たちの言う「何の練習もしていないけれど、やろうと思えばできた」という言葉には、人間本来の身体づかい、というものについての、大いなる示唆が隠されているのではないか――。
※
以上、三砂ちづる氏の近刊『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』(光文社新書)をもとに再構成しました。ある身体技法ができるということはどういうことか、頭上運搬を通して考えます。
●『頭上運搬を追って 失われゆく身体技法』詳細はこちら