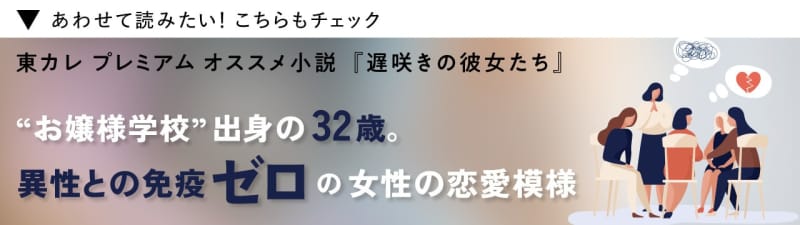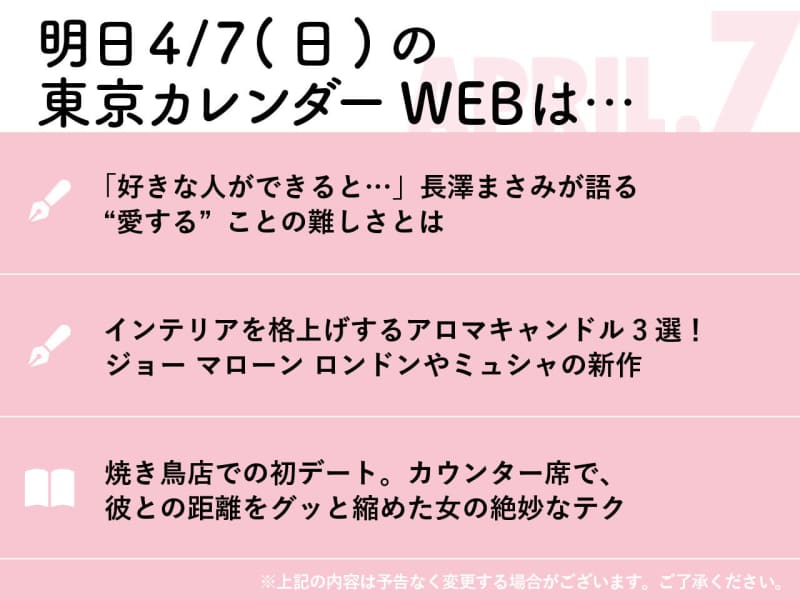前回:「港区に住むなら、絶対知っておくべきコトは…」27歳女が触れてしまった、西麻布の闇
◆
― …とりあえず…普通の家で良かった。
怖いおじさんに黒塗りの高級車に乗せられたというシチュエーションから、薄暗い倉庫に連れていかれてロープで縛られるとかもありえる…?とか、映画で良く見る最悪のケースを妄想して(一瞬だけど)怯えていたので、ここがマンションの一室であることに、私はとりあえずホッとしていた。
とはいえここは“普通の家”とは言い難い。天井は通常の2階くらいまでありそうな程高く壁一面の窓からは東京の街が一望できる。一望できるのだけれど、見えている街や建物、その全てがひどく小さい。つまり超高層階、45階、最上階にある部屋なのだ。
ここに上がるまでのエレベーターの中で、気圧の変化に耳が詰まったし、この部屋にいる今、頭がくらくらする気がする。それが緊張のせいなのか、高い所が苦手な体質のせいなのか分からないけれど、とにかく今、私の心臓はバクバクいっている。
30㎡くらいのワンルームの私の部屋が、3つ、4つくらい入ってしまいそうなリビングに置かれたグレーのソファーに私と愛さんが並んで座らされた。並んでと言っても、ソファーが巨大すぎて、私と愛さんの間は、あと2人程入りそうなくらい離れている。
ここが、愛さんの元夫さん…私たちを連れてきた“タケフミさん”が所有するマンションだということを愛さんが教えてくれた。愛さんはこの部屋に来たことがあるらしい。場所は青山1丁目あたり。
大そうな車に乗せられたのにわずか10分程で到着したことになんだか肩透かしの気分になった。こんなに近いならあんなに仰々しい車で迎えにこなくても…とあの黒塗りの高級車にまで文句を言いたくなるのは、私が愛さんの元夫さんを“嫌な奴”認定しているからだろうか。
「どうぞ」
ソファーの前に置かれたガラスのテーブル(こちらも巨大)の上に、カップ&ソーサーでコーヒーが置かれた。出してくれたのは、ドラマでよく見るお手伝いさんそのもの、制服のような黒い服に白いエプロンをつけた女性だった。
愛さんが、お久しぶりです、と言っていたので、多分愛さんが結婚していた時からいる人なのだろう。私たちをここに連れてきた人は、私たちを待たせたままどこに行ったんだと気になるけれど、とりあえず客扱いはしているつもりらしい。
― コーヒーなんか飲む気にはなれないけど。
それは愛さんも同じだったようで、コーヒーには見向きもしていない。お手伝いさんが出て行くのを待って、愛さんは小さな声で、宝ちゃん、と言った。
「宝ちゃんが私と一緒にいようとしてくれたその気持ちは本当に嬉しいし、ありがたい。でも、私やっぱり、ここに宝ちゃんを連れてきてしまったことを、猛烈に後悔してる。
あの人が私に何を言っても、もし宝ちゃんが何かを言われたとしても、宝ちゃんは答えなくていいから。何も話さず黙っていてね。あの人は次元が違う。人の感情がわからないサイコパスだから。宝ちゃんを傷つけたくないの」
「……サイコパス…」
何で愛さんがそんな人と結婚を…?と思いながらも、私は、はいと頷いた。小さな声でしか話さない愛さんに、どこかに盗聴器でもついてるの?と怖くなりキョロキョロしていると声がした。
「時間がない。単刀直入に話そう」
そう言って入ってきたサイコパス…じゃない、元夫さん…タケフミさんは、スーツを着ていたはずなのに、ネイビーのセーターにベージュのスラックス姿になっていた。時間がないなら着替えるな!と突っ込みたくなったが、当然黙っている。
ソファーテーブルをはさんで私たちの前、窓ガラスを背にして座ったタケフミさんの顔が逆光で暗い…と思っていると、窓ガラスのカーテンが電動で閉まった。座ると閉まるの!?と驚き密かに辺りを伺うと、お手伝いさんがリモコンを押しているようだった。
「…あなたが私に会う必要があるのは、あの子に関わることだけですよね」
切り出したのは愛さんからだった。そうだ、と短くつぶやいたタケフミさんの前に、お手伝いさんがグラスを運んできた。おそらく水であろうそれをグイっと飲んでから、タケフミさんは言った。
「タケルは、中学から海外に行かせる。決定事項だからジャマをしても無駄だと直接くぎを刺しておこうかと思ってね」

あの子、そしてタケル。そう呼ばれたのはきっと、パリで雄大さんが話してくれた、愛さんが離れて暮らしている小学4年生の息子さんのことだろうと、容易に想像がついた。
― 海外に行かせるって…愛さんは今、息子さんと一緒に暮らすために頑張ってるはずでは?
そもそもこのタケフミさんが不倫したことが離婚原因なのに、何かと愛さんに不利な要素を捏造して親権を奪ったと聞いている。それなのにまたも勝手な決定事項を、一方的に通達しているということだろうか。
「…海外…。それは、タケルも納得していることなんですか?」
愛さんは感情を抑えて話しているように見えた。ビジネスモードとでもいうのか、こんなに静かに話す愛さんを初めて見る。
「納得もなにも、アイツが選ぶことではない。私が決める」
― アイツが選ぶことではない?
私には子どもがいないし、偉そうなことを言える立場ではないことはわかっている。でも小学4年生にもなれば、もう十分に自分の意志を主張できるはず。その意志を尋ねて、全てを受け入れずとも、できるだけ尊重するべきなのではないだろうか。
「やりたいかやりたくないか、宝が選ぶんだ。ちゃんと自分で考えなさい」
少なくとも私は、両親にそう言われて育ってきた。特にやりたいことを見つけられず、その選択が自分にゆだねられることが苦痛だった時もあったけど、両親はいつも私の意志を尊重してくれた。大人になった今は、それがとてもありがたいことだったと理解している。
ふいに思い出した両親への感謝に気をとられていると、愛さんが言った。
「…タケルが海外を選ぶならいい。でも行きたくないというのなら、その理由を…あの子の話をきちんと聞いてあげてください。そして望む場所にいさせてあげて欲しい」
「…随分と熱弁するな。まるであの子の気持ちを知ってるみたいだ」
「…」
「月に1度しか会わないお前が、一緒に暮らす私よりあの子の気持ちをわかるとでも?」
「…」
黙った愛さんを、タケフミさんが笑った。そのバカにしたような笑い方には、見ているだけの私でさえムカついてしまう。
「…ああ、これか?」
そう言ってタケフミさんがポケットから何かを取り出し、テーブルの上に置いた。それは、携帯電話だった。愛さんが固まっている。
「オレがあの子に与えた携帯でお前に連絡をとれば、全部バレてしまうからな。だからもう1台買い与えるとは。バカ正直が取り柄のお前が、そんな姑息なことをするとは思っていなかったから油断してたよ」
愛さんは黙ったままで否定をしない。ということは、彼が言っていることが本当なのだろうが、バカ正直とか姑息とか、いちいち失礼過ぎて、嫌な奴レベルがどんどん上がっていく。
「あの子もうまく隠してたよ。お前が買ってくれたものだから、よっぽど大切だったんだな。もう3ヶ月くらいか?でも所詮子どもだ。隠し事には限界がある。見つけてから、この携帯の履歴を全て調べさせてもらったんだが」
「…」
「愛。お前、先月、決められた日以外にもあの子に会ったな?」
― あ。これはマズイ気がする。
誰か助けて、と思わず雄大さんの顔が浮かんで、私は自分の体の横に置いていた携帯を、そっと手に取った。タケフミさんも愛さんもそんな私を気にする様子はなかったけれど…今連絡したところでどうなるの…と思い直し、携帯を元の場所に戻す。
「お前のその感情的な愚かさが結果的に、いつも自分の首をしめる。わかってるだろ?」
「…携帯を渡したのはすみません。ただあの子を取り戻すためにとか…そんな狙いのようなものはありません。半年前に会った時に、海外に行きたくないと…あの子に相談されて。話せる相手がいないと悩んでいたので、それで…」
「契約違反だ」
「…でも。私の思いで海外に行くなと言ったことはありません。それは携帯でのやりとりを見てもらえればわかるはずです。ただあなたにどう話すのがいいのか、悩んだ時に相談にのっていただけで…」
真摯に言葉を選ぶ愛さんの様子にウソがあるとは思えない。でも、タケフミさんの表情は冷たく黙ったままだ。今、何の役にも立てていない自分じゃなくて、雄大さんや大輝くんがついてきていたら何かを変えられたかもしれないと思うと、情けなくなってきた。
― まさかこんなことになるなんて。
私が表参道の愛さんのサロンに到着したのは、今から4時間前のことだった。
◆

「バースデーツアーの開始は15時だから…」
それまでに全身ピカピカにしてあげる、ヘアメイクもね、という連絡を数日前に愛さんからもらい、私は表参道にある愛さんのサロンに午前10時に行く約束をした。
私は自分の家…西麻布から表参道の骨董通りまでって歩けるんだぁなんてのんきに浮かれながら、骨董通りから一本入った通りに建つビンテージマンションにあるという、愛さんのサロンを目指した。
愛さんのサロンは、体質や肌質に合わせてオーガニックオイルの調合を変える、オイルマッサージによる全身トリートメントと骨格矯正を組み合わせたもので、普段は愛さんの他に2人のセラピストがいるらしい。
隣同士の2部屋を借りていて、1部屋はエステ、そしてもう1部屋はネイルサロン。愛さんに体を磨き上げてもらった後、ネイルサロンへ移動した。
会社には派手なネイルでは行けない…という私のためにと、ジェルネイルではなくマニキュアを。ボルドーのネイルに少しだけビジュ―を付けてもらい、明日の月曜日に剥がしてしまうのがもったいないなと残念に思った。
ネイルが乾くまでの間にヘアメイクをと、私のボブの髪を、マニッシュにタイトにまとめてくれた。
ドレスアップは、HARUNOBUMURATAの黒のセットアップに、足元は、ロジェ ヴィヴィエ、ベビーピンクの7cmヒール。今回は、セットアップもヒールも愛さんからの借り物だけど、近々愛さんが私の買い物に付き合ってくれるらしい。
鏡の中の自分は文字通り、“見たことのない自分”だった。宝ちゃんはシュッとした顔立ちだからこういうマニッシュな雰囲気似合うよね、と自分の腕に満足げな愛さんを見ていると私も嬉しくなり、誕生日にこんなにワクワクするのはいつぶりだろうと思った。
「思ったより早く仕上がったから、コーヒーでも飲みに行こう」
大輝くんが迎えに来てくれるという時間まで、あと1時間程あった。近くにコーヒーの美味しい店が…あ、でももうシャンパン飲んじゃってもいいかぁなどと悩んだ愛さんが、とりあえず骨董通りまで出てタクシーを捕まえよう、と言った。
ヒールを履きなれない私の足元はおぼつかず、そんな私を笑いながら、愛さんが腕を組んで歩いてくれた。そして骨董通りまで出たところで、愛、という声がして、呼び止められたのだ。
男の人だ、と思って振り返ると、黒塗りの車の横に、スーツ姿の長身の男性が立っていた。私は男性の衣服に詳しいわけではないけれど、その全てが高級そうに見える男性が、険しい顔で私たちに近づいて来る。…これが、元夫さん、つまりタケフミさんだったのだ。
「丁度、サロンに行こうと思っていた」
「…何のご用でしょう?」
愛さんのその顔が、初めて見る険しさでゆがんでいた。タケフミさんは私を一瞥し、すぐに愛さんに視線を戻して言った。
「話がある」
「突然訪ねてくるなんて、マナー違反では?日曜でお客様の施術がある可能性も高いのに、私の予定を全く気にしないところがあなたらしいですけど」
「お前の予定なんてどうでもいい」
相手の予定をどうでもいいと言い放つその高慢さだけで、嫌な人だと認定するには十分だったのに、タケフミさんは、その嫌な人ぶりを加速させ、“嫌な奴”に到達した。
「お前はもうあの子の母親じゃないんだから、あの子を混乱させるな」
「……母親でなければ、何だというのでしょう?」
愛さんが怒りを抑え、言葉を選んでいるのがわかった。それを気にもせずタケフミさんが返す。
「あの子が生まれてくるために、生物学上必要だった存在だ。“だった”。…過去形だ、わかるな?」
― なんなの、この人?
信じられない返しに私が驚いていると、愛さんは、呼吸を整えるためか、大きくフゥーと息を吐き出してから私を見た。
「私この人と話してから行くから、宝ちゃんは、大輝に連絡してくれる?待ち合わせにはちょっと早いけど、多分あの子、すぐ動けるようにしてるはずだから、すぐ迎えに来てくれると思うから」
ごめんね、と私の手を握りながらほほ笑んだ愛さんの指先が…かすかにふるえていて驚いた。こんな愛さんは初めて見る。
緊張?それとも……恐怖?この人への?と、私がタケフミさんを見上げると、早く立ち去れと言わんばかりに、冷たい目だけで私を見下ろしてくる。
― 蛇。毒蛇。
まるで感情など持たないかのようなその冷たい視線は私を怯えさせた。けれど。
― 大輝くんだったら、どうするだろう?
祥吾から私を守ってくれた時のことを衝動的に思い出し、私は勢いで言ってしまった。
「…私も一緒に行きます」
愛さんが、宝ちゃん!?と驚いた声を上げたが、私もそんなことを言ってしまった自分に驚いていた。でもとにかく、愛さんを1人で行かせたらダメな気がしたのだ。男性は相変わらず表情を変えず、微動だにせず、私を見下ろしたままだった。
「…今日、私の誕生会で、私が主役の日なのに、その、あなたが乱入してきたわけで…困ってます。私のパーティまでに、あなたが時間までに愛さんを帰してくれるか心配ですし、ついていきます、私も、絶対に」
◆

その後、この子どもはなんなんだ、とタケフミさんに言われながら、私はほぼダダをこねる形で愛さんと一緒に車に乗り込んでここに来ることになった。ついてからも別室にいろ、と言われたけれど、あなたが何を言うか心配なので、と食い下がると一緒にいさせてもらえることにはなった。なったのだけど。
― 無力。
愛さんが大ピンチの状態になっても私は何もすることができない。せめてもと、愛さんの側に寄りその手を握ってみたけれど、気休めにもならないだろうなとはがゆくなった。
その時、お連れしました、と女性の声がした。入りなさいと答えたタケフミさんの言葉を待って、先ほどのお手伝いさんの後ろに小さな影が見えた。
― 男の子?
「…タケル」
愛さんが発した言葉に、男の子が小さく、ママ、と言った。お手伝いさんに促され、タケルくんは、タケフミさんの隣に…少し離れたところに座った。
「…なんで、タケルをここに…」
愛さんが誰に問うでもなく口にした。その視線はタケフミさんではなくタケル君に向けられている。ひどく苦しそうなその表情に、私の胸も苦しくなる。
「本宅だと両親もいるし、何かとギャラリーが多くなるだろう。お前を哀れに思った私の情けに感謝してもらいたい」
「…」
― この男、本当に、本当に、腹が立つ……!
まさにサイコパス。このままだと愛さんより先に私の方が怒りを爆発させてしまいそうだ。
「タケル、お前が選びなさい。昨日、お父さんが話したことわかるな?留学するかどうか」
「…」
タケルくんが黙ったままうなだれた。その様子にたえられないとばかりに、愛さんが口を開く。
「…タケル。大丈夫よ、こわいことなんて何もないから。タケルがイヤなことはしなくていいの。…ね?」
タケルくんが泣きそうな顔で愛さんを見た。愛さんの目から涙がこぼれた。それを見たタケルくんが一度うなだれ、しばらく沈黙が続いた。
その小さな拳がぎゅっと握られていることに、このサイコパスは気づいているだろうか?
隣に座っているのに、沈黙したタケルくんの方を見ることもせずに、なぜかこのタイミングで…サプリなのかクスリなのか、錠剤を取り出し飲み始めたその様子に、最も部外者である私が怒りに震えてしまう。
そして、次にタケル君が顔を上げた時、そこに涙の影はなく、自分を奮い立たせるような顔に変わっていた。
「…僕、留学します」
「…タケル…」
愛さんのその声は、弱々しく悲鳴のようだった。
「…ママ、ゴメンね…」
「……いいの、ママにごめんね、って言う必要はないの」
「お父さん、僕留学します。だから…ママをいじめないで…ください」
「……タケル…」
愛さんの言葉に嗚咽が混ざった。
― ひどい。辛すぎるよ
こんな小さな子が、母親を守ろうとしているのに。こんな父親がいてもいいの!?私は、タケフミさんを、強く、強くにらんだ。
「タケル、正しい決断だ。それからもう一つ。お前のママは、もうこの人じゃないと何度も言ってるだろう。一緒に住んで、お前の面倒を見てくれている人にきちんと感謝するように」
タケフミさんの言葉に、タケルくんが、あきらめたように、はい、とうなだれた。その、はい、を聞いた愛さんが、声を殺して涙をこぼす。
― 愛さん!なぜ、反論しないの!?
何も言わない愛さんに対して、私は出会って以来初めての苛立ちのようなものを感じていた。そして、思わず口にしてしまった。
「…あなたのやり方は…違うと思います」
サイコパスがこちらを見た。
「部外者が口をはさむんですか?」
ぎろり、とにらまれたけれど、勢いのまま言った。
「……タケルくんが本当は何を望んでいるのかを、きちんと聞いてあげてください」
私はこの時。
私のこの発言が…佐々木宝・28歳の誕生日を粉々に…最悪なものにしてしまうことを、知る由もなかった。
▶前回:「港区に住むなら、絶対知っておくべきコトは…」27歳女が触れてしまった、西麻布の闇
▶1話目はこちら:27歳の総合職女子。武蔵小金井から、港区西麻布に引っ越した理由とは…
次回は、4月13日 土曜更新予定!