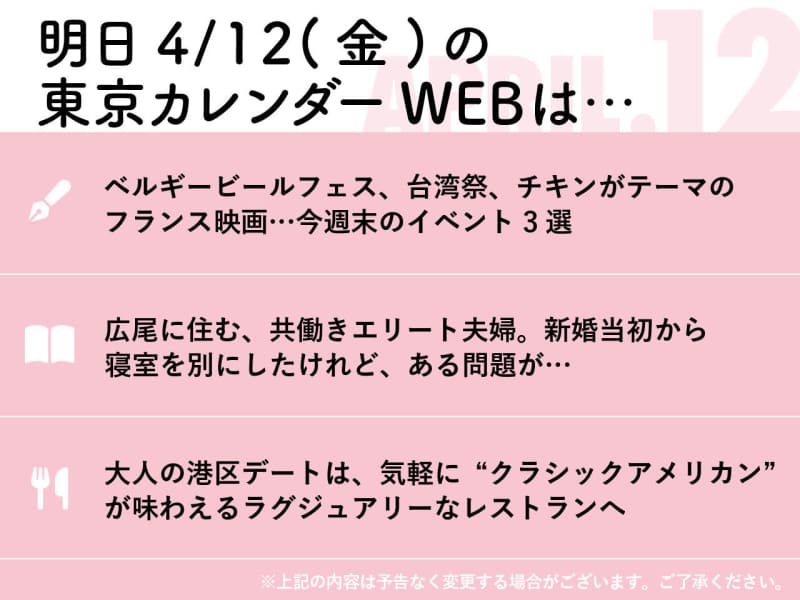人生は、何が起こるかわからない。
日常が歪み、愛情が枯れ、永遠を誓った結婚が“離婚”という名の終わりを迎えることもある。
だけど、恋の終わりのように「さようなら」の一言では片付かないのが離婚だ。
正しい離婚の方法。あなたはちゃんと知っていますか──?

Vol.1 夫が家を出ていった
「今日ね、花奈ってば幼稚園に行きたくないってゴネて大変だったのよ」
父親なのだから、昼間の子どもの様子が気になるはず。そう信じて疑わない楓(かえで)は、帰宅した夫の光朗に、毎晩こうして娘の報告をしている。
21時半。すでに娘は眠っていて、ダイニングには夫婦2人だ。
「クラスが替わったばかりの4月なんだし、しょうがないよ。明日は僕が花奈を送っていくから、楓はゆっくりして」
光朗は愚痴とも取れる楓の報告を聞きつつ、いたわりの気持ちも忘れない。
こうして2人で子どもの話をしている時、楓はつくづく思うのだった。
― あ〜、この人と結婚してよかった。
8歳上の夫とは、結婚してもうすぐ5年になる。いつだって光朗は楓の話にしっかり耳を傾けてくれるし、記念日や誕生日のプレゼントも欠かさない。
結婚前から専業主婦を希望していた楓が、頭の中に描いていたそのまんまの日常がいまここにある。3年前にはこの北参道のタワーマンションを購入し、生活には何の不自由もない。
それになにより、光朗がいい年の取り方をしていることが、妻として誇らしかった。
今年で42歳。すっかり“オジサン”と称して差し支えない年齢だが、お洒落をすることが好きな光朗は、ママ友たちから「ご主人、素敵ね」と言われることもしばしば。
付き合っている時にはすでに不動産コンサルティングの家業を継いでいて、数年前からは異業種の事業にも取り組み始めて成功を収めている。
優しく、ルックスも良く、経済的にも豊かな夫は、楓の自慢なのだった。
「明日は天気もいいから、幼稚園まで歩いて行こうかな」
そう言いかけたところで、光朗は思い出したように、話を切り出した。
「そうだ。事後報告で悪いんだけど、オフィスの近くに部屋を借りたんだ」
「えっ?部屋ってなんのための?」
光朗からの唐突な報告に、楓の声は意図せず裏返った。
「あはは。なんて声を出してるの」
あまりにも仕事が忙しいため、オフィスの近くに部屋を借りた。そうすれば、ちょっと休憩時間に休んだり、また遅くなる時は泊まったりすることもできる…と、光朗はさらりと理由を説明する。
「そんなに忙しいの?わざわざ部屋を借りるほど?」
確かに、最近仕事が忙しいようで、帰ってくるのは21時以降になることがほとんどだ。
「心配しなくていいよ。40越えたあたりから、体力衰えてさ」
部屋をもう一つ借りるくらいなら、はじめからオフィスの近くに住んでも良かったのに。と、楓は思う。
光朗のオフィスは有明にあり、自宅を購入するときにはベイエリアも候補に挙がったのだ。けれどその時、「もっと娘の教育環境がいい場所に住もう」と提案したのは、光朗の方だった。
仕事で疲れている光朗を、追い詰めたい気持ちは微塵もない。楓は、ふと思い出したそんな経緯を振り切ると、ねぎらいの言葉をかけた。
「わかった。体の方が大事だもんね!無理しないで頑張って」
◆
サツキの花が咲き誇る、5月の公園の帰り道。
花奈にぎゅっと手を掴まれて、楓は我に返った。
「ねえ、ママってば!パパって今日帰ってくる?」
「うーん、どうだろう。パパ、お仕事忙しいみたいだから、お家帰ったらLINEで聞いてみようか?」

1ヶ月前の夜、「部屋を借りた」と報告を受けて以降、光朗は明らかに変わった。
しばらくは、2日に一度程度のペースだった帰宅は、いつのまにか3日に一度に。次第にさらに間が空いていき、今では週末に帰ってくればまだまし、というレベルになっている。
それでも最初の方は、LINEのやりとりも今までどおり頻繁にあった。いや、頻繁というのは楓からのLINEであって、それに対しての返信がちゃんと返ってきたという意味だ。
そして、今日は土曜日なのに、光朗は自宅にいない。
花奈と2人の休日を持て余した楓は、近所の公園を散歩しカフェに立ち寄り帰る途中だが、心がざわざわとして落ち着かなかった。
― 3日前に送ったLINE、返ってこなかったし…。どうしたんだろう?
電話をしても、出たためしがない。
妻には言えない悩みがあるのかもしれない。不安がない、といえば嘘になる。
― もしかしたら、私に言えない重病が見つかったとか?
― 仕事がうまくいってないとか?
あらぬ妄想が次から次へと湧き上がる。
「はぁ…」
深いため息をついた時、背後からポンと肩を叩かれた。
「やだ、大きなため息。幸せ逃げちゃうよ?」
振り向いた先にいたのは、楓の5歳下の妹・麻美だった。「遊びに行く」という連絡を昨日もらっていたことを、すっかり忘れていた。
慌てて麻美を家へと招き入れた楓は、急いでロイヤル コペンハーゲンのカップを取り出し、コーヒーマシンにカプセルをセットする。
「コーヒーでいいよね?」
けれど、その問いに答える前に、麻美は無邪気に尋ねてくるのだった。
「あれ、お義兄さんはお仕事?」
「あ、うん…」と口ごもっていると、花奈が横から口を挟んだ。
「ねえ、ママ、パパにLINEは?いつ帰ってくるか聞いてよ」
花奈の様子を見て、麻美は察したようだ。
「なに?お義兄さん帰ってきてないの?出張…とか?」
「う、うん…それが…。花奈、Netflixでも見る?」
楓は娘に配慮すると、1ヶ月前からの経緯を麻美に打ち明けはじめるのだった。

「実は…1ヶ月前に仕事の休憩用に部屋を借りてから、わざわざ帰ってくるのが面倒になっちゃったみたいなの」
「面倒って。たかだか有明からここまでって、車で40分もあれば着くけど」
麻美の指摘に、楓の心は鬱々と沈んでいく。
「何かあったのか心配なんだけど、電話もでなくて…」
「お姉ちゃんって、能天気というか。なんというか…」
何か言いたげな妹から目線を逸らした先のテーブルの端に、朝とってきた郵便物の束が放置されていた。楓は、それを引き寄せ、無言でダイレクトメールや封書を仕分ける。
「だって、疑う理由がないんだもん。仲良くやってたし…。本人と話せてないし」
これは楓の本心だった。
けれど、次の瞬間。楓はふいに手を止めた。
手にした封書に、「楓へ」という表書きがあったからだ。
そしてその字体には、見覚えがあった。
「これ…」
封書を手にフリーズしている楓に、麻美が気づく。
楓は手に持った封筒を指でこじ開けるように開封し、中身を取り出し、開いた。
途端、楓の頬につーっと一粒の涙が流れ落ちる。
「お、お姉ちゃん、大丈夫?」
おろおろとしながら問いかける麻美の声が、遠い。
「どうして…?」
そう小さくつぶやきながら楓は、愛する夫の名前がすでに書き込まれている緑の紙──離婚届を、まじまじと見つめた。
◆
週が明けた。
封書の中で折り畳まれた離婚届は、捨てることも破くこともできないまま。唐突すぎて、光朗に連絡を取ることもためらっていた。
幼稚園に花奈を送った後、1人で家に戻りたくなくて、楓はカフェに立ち寄った。
1人になりたくてやってきた場所だが、少し離れたところに幼稚園のママ友の姿を目にする。
― たしか、晴子さんだったかな。声、かけないでいっか。
楓は、気づかないふりをしながら窓際の席に座る。
幼稚園では、専業のママが多い中、彼女は送迎を実母に助けてもらいながら、フルタイムで働いているらしい。どのママ友のグループにも属さず、楓も深く話したことはなかった。
視線を外していたはずなのに、なぜかお互い目が合った。
「もし差し支えなければ一緒にいい?」
向こうから楓の方にやってきた。
「ええ、もちろん」と答えると、晴子はカップを持って移動してきた。
「いつもうちの娘が花奈ちゃんの話ばかりするの」
話してみると、晴子は口数多く、とても楽しい人だった。聞きかじったとおり、仕事があるので、幼稚園にはめったに来れないという。また、想像以上に幼稚園ではママ同士のコミュニティーが出来上がっていて、時々困ることがある、とも言った。

「私、みんなと境遇が全然違うのよ。フルタイムで働いてるし、バツイチだし。保育園に入れておけばよかったかもって、今更ながら後悔してるの」
「やだ、困ったら相談して。花奈と一緒にお迎えして預かることくらいできるし」
晴子との思いがけないお茶の時間に、楓の心はにわかに緩んだ。
なんでもない普通の会話が、ものすごく久しぶりに感じる。
ここ最近は、光朗が家から出て行ったことがママ友たちにバレるのでは…とビクビクしっぱなしの生活で、幼稚園の送迎も逃げるように済ませていたから。
けれど、人は自分と同じ傷を持つ人間に、心を開くのかもしれない。
あれだけ周囲にバレたくないと思っていた今の状況を、楓はなぜだか晴子には聞いてほしいと思った。
さして親しくもないこともあるだろうが、晴子が思ったよりも感じのいい人で気を許したこと。そしてなにより、先ほど晴子の口からでた「バツイチ」という言葉を聞き逃してはいなかった。
少しのためらいの後、楓は意を決して打ち明ける。
「私も、幼稚園のママ友たちには言えない事情が出てきてしまって…。最近、幼稚園行きたくないんだよね…」
夫から離婚を切り出されたことなんて、たかがママ友から打ち明けられたら、普通は困ってしまうだろう。
言った瞬間に、晴子に悪いことをした…という後悔の念が湧いたが、晴子の反応は予想とは違うものだった。
大げさな同情も、当たり障りのない慰めの言葉もなく、あっけらかんと言い放つ。
「は?いきなり、離婚届?ない。ないわー」
「やっぱ、ない?」
楓が聞くと、「ない。ない、ない!ありえない」とないないづくしで返す晴子。
思わず、楓はぷぷっと吹き出した。
「ありがとう。その反応、めちゃくちゃ嬉しい」
「でも、仲がいいと思っていたのに、いきなり離婚届じゃ楓さんもびっくりしたよね。晴天の霹靂、というか」
「ええ。だから、理由を聞きたい。それを聞いて、私が改善することで元に戻れるならそうしたい、って思う」
楓は、自分の口からでたその言葉に、自分自身でハッとした。
― そうだ。ポロッと漏れた、これが本音だ。私はただ、幸せだった元のあの生活に戻りたいんだ。
ようやく自分の気持ちが整理できはじめた楓の前で、晴子は自身の体験も交え語り始める。
「私の場合はね、ケンカが多くなって、相手が離婚をほのめかし始め、最終的には調停起こされちゃった。結局、財産分与の割合決めて離婚したのは1年半後」
「そういう感じなんだ…。私、ケンカとか全然なくて。むしろ、自慢の夫だったというか…。なのに、『突然驚かせて申し訳ありません。よくよく考えての決意です』と付箋が貼ってある離婚届がいきなり届いて…」
楓の話をひとしきり聞き終えた晴子は、こめかみがピキピキと筋走り、イライラした様子を隠せない様子で言った。
「付箋?妻のことバカにしてんの?娘のことをどうするとか、家をどうするとかって何もないわけ?」
驚く楓の手をぎゅっと握り、晴子は前のめりになった。

「楓さん。ぜったいに、ぜっったいに、簡単にハンコなんて押しちゃダメよ!」
子どもを育てるにはお金がいる。仕事をしていない専業主婦がそれなりに稼げるようになるには時間がかかる。
だから、元に戻れるならそのほうがいいし、もし無理ならできる限りのお金をむしりとってから別れるべき…というのが、晴子の意見だった。
「でもね、楓さん。これだけは言わせてもらえる?」
「なに?」
「はっきり言って、ご主人…ううん。その男、クズよ…」
「えっ?」
晴子は鼻息荒く、言い放った。
目下トラブルの渦中にあるとはいえ、人の夫を「クズ」と言い切る晴子の物言いに楓は面食らってしまう。
だって、今こんな目に遭っているのは、自分のせいだと思っていたから。夫が出て行った理由はわからないが、こうなってしまった以上、すべて自分に原因があると楓は思っていたのだ。
「クズって…彼、決してそんな人じゃないの。私、これまで何の不安もなくて…」
なんとなく居心地が悪くて光朗をかばってみるものの、楓は意外なことに気がつく。
心が、少しだけ軽い。
「自分のせいだ」というモヤモヤを晴子が否定してくれたおかげで、楓の心がふわっと軽くなったのは確かなのだった。
― 晴子さん、優しいな。こんなに親身になって怒ってくれるなんて。
目の前に、夫婦間の困難を乗り越えた人がいる。逆境に打ち勝って、力強く子どもを育て生活している。その事実に救われた気がした楓は、晴子に「話を聞いてくれてありがとう」と小さくお礼を伝えた。
けれどそれに対して、晴子は大きなため息をついて頭を抱える。
「ああ、ダメだ。楓さん、あなたお人よしすぎる。甘すぎるよ」
「え?」
「別れたくないんでしょ?今手元にある離婚届、どうするつもりなの?ご主人になんて返事するつもり?」
「それは…まだわからないけど、ゆっくり向き合わなきゃいけないって思ったよ」
「楓さん。ただ渋っているだけだったら、そのうち調停おこされて、話し合いで財産分与の割合を決めて離婚だよ。相手にいいようにされるその前に、対策とっておかないと」
「対策…って言われても…」
光朗と元に戻りたい。そのことにすらたった今気づいた楓にとって、晴子の言葉はまるで聞いたこともない外国語のようだった。
そんな楓を見かねた晴子は、しばらく押し黙ったかと思うと、まっすぐ楓と視線を合わせて、力強く宣言する。
「いいわ、楓さん。私が全部教えてあげる」
その熱く燃える晴子の眼差しに楓は、夫の帰りを待つだけの日々が遠のいていくのを感じた。
▶他にも:妻とはできない男たち:「実は、奥さんとずっとしてない…」33歳男の衝撃告白。エリート夫婦の実態
▶NEXT:4月18日 木曜更新予定
専業主婦は絶句した。離婚ってこんなにお金がかかるの?