
徳島県の美波町国民健康保険美波病院は、県南部の医療を支える公立病院だ。4月5日、本田壮一院長(65)は一般外来で診察を担当した。疲労を感じるのは、午前中に14人もの患者が来たからだけではない。前日の4日早朝から当直に入り、そのまま病院に泊まった宿直明けだからだ。
この日の仕事はこれで終わりではない。昼食を急いで済ませ、車に乗った。午後は2人の患者宅を回る訪問診療へ向かう。病院に戻ったのは午後2時。そこからさらに10人の一般外来患者を診た。仕事はまだ終わらない。製薬会社の担当者から薬品の説明を受けるなど、院長としての務めをこなし、帰路についたのは午後9時。38時間後に解放されたことになる。明らかに医師が足りていない。
しかし、実は徳島県は「人口10万人当たりの医師数」が2022年末で全国1位だ。医師が潤沢なはずの県で、なぜ60代の院長が激務をこなしているのか。実態を調べていくと、この地域だけでなく各地で共通する課題に行き当たる。(共同通信=別宮裕智)
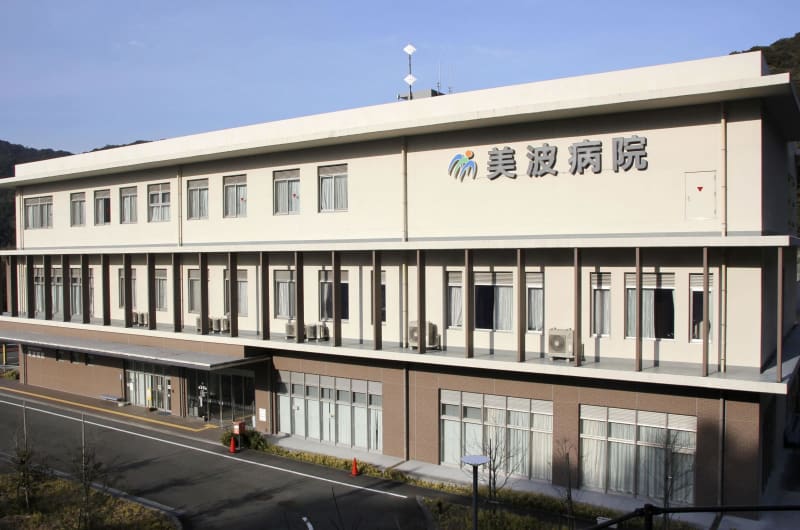
▽「外来の診察しているのに、救急の対応まで」
美波病院は入院ベッドが50床ある。ただ、常勤の医師は本田院長を含め60代の2人だけだ。ほかは非常勤医師の応援に頼っているものの、とても足りない。本田院長はこう説明する。
「入院患者の診療のためには、常勤が6人は必要」
日によっては、一般外来の診察中に救急の患者が来ることもある。医師が足りていれば一般外来と別の医師が担当できるが、美波病院では兼任になる。

本田院長は笑いながらこんなエピソードを語る。「診察していて『救急対応回します』と院内に連絡したら、救急対応も自分だった」。全然笑えない。
医師も常に健康とは限らない。インフルエンザにかかれば休まざるを得なくなり、ほかの医師の負担はさらに重くなるため「罪悪感で心苦しい」
加えて、4月からは働き方改革関連法に基づき、医師の時間外労働(残業)に上限規制が導入された。
「1人当たりの働ける時間が制限されると、人手不足の病院はますます追い込まれる」
非常勤の医師が当直中に救急車で患者が搬送されたものの、対応できず、規模の大きい病院に再搬送することもあった。夜間の呼び出し体制も敷けない。技師も不在のため、エックス線などの急な検査に対応できない。
院長の悩みは尽きない。
「無理になんとか保っているが、地域医療として今の体制でいいのか」
念頭にあるのは今年1月の能登半島地震だ。徳島県は、南海トラフ巨大地震のリスクがある。災害医療の経験を積むため、能登にDMATを派遣したいが「通常業務だけで本当に手いっぱい。派遣する余裕がない」

▽「東京に行けるなら…徳島には残らない」
美波病院の状況を見ていると信じられないが、厚生労働省によると、徳島県は人口10万人当たり医師数が首位だ。しかも最新の結果である2022年末だけでなく、2016年末から首位を維持している。
医師の輩出を担ってきたのが、本田院長の母校でもある国立徳島大医学部。1943年2月に県立徳島医学専門学校として誕生した。戦後の新制大学制度への移行に伴い、1949年に徳島大医学部となった。「旧7帝大」などには及ばないものの、意外と古くからある。
それでも医師が不足する原因の一つは、県外流出だ。
学生が医師の国家試験に合格すると2年間の初期研修があるが、その時点で県外に出てしまう。2024年度は初期研修で県内に残る医師が卒業生全体の3割しかいなかった。
理由として、県外出身者が多いことが考えられる。2023年度に徳島大医学部に進学した112人中、県外出身者が78人を占めた。例年、初期研修で徳島に残るのは県外出身者の1割、県内出身者でも7割となっている。
危機感を抱く徳島県は、医師確保対策として2024年度当初予算案に1億6千万円を計上している。具体的には①徳島大学医学部への入学者のうち、修学資金を貸与する代わりに、県内に9年間勤務してもらう枠組みを12人から17人に増やす②県外の大学へ進学した徳島出身の学生は奨学金で経済的に支援し、県内に9年間勤務してもらう③徳島大学へ入学した県外出身学生のうち、県内で研修した場合に一時金を支援する―。
それでも、学生側の受け止めはいまひとつのようだ。徳島市出身で徳島大医学部3年の男子学生は勤務先をまだ決めていないという。
「東京に行けるとなったら、大体の人が徳島に残らないと思う。奨学金など目先のことでなく、地元の魅力が増さない限り、地方に人は集まらないのでは」

▽県内に残った医師は徳島市に集中
課題は県外流出だけではない。高齢化もある。徳島県の医師の平均年齢は54・2歳。全国で最も高い。さらに、県内の医師の多くが県庁所在地である徳島市に集中しているという偏在の問題が大きい。
徳島大は学外に医師を派遣する病院を持っており、医師を偏在なく配置する重要な機能を担っている。地域の需要と医師のキャリア形成をマッチングしながら配置できるという利点がある。
しかし、近年は医師が都市圏の人気のある病院に就職し、異動せず固定化する傾向が強い。

徳島大医学部の赤池雅史教授(医療教育学)は「医師に限らず、若い時は都会に行きたいのでしょう」と述べた上で、医師の偏在の理由をこう見る。
「地方では若手医師の勤務先として大学病院がかなりのウェイトを占めていますが、経営に余裕がないので、若い人に十分な給料を出せていない。地方で良い仕事をしても正当な対価を得られていない違和感が、若い人たちには強いのではないでしょうか」
徳島県の対策については、経済的支援は大きいと指摘する一方、制度で「9年間縛りつける」リスクに懸念を示した。
「30代半ばから50歳くらいまでが医師として臨床での第一線なので、9年後に県外に出してしまったら『せっかく大事に育てたのに何をやっているのか』という話になる」
徳島大の西岡安彦医学部長はこう語っている。
「母校のメリットは長い医師人生の中ですごく大きいものがある。出身大学が同じであれば、何歳になっても仲間。キャリアを長いスパンで考えてもらい、出身大学のある地域に残る選択肢を考えてもらえたらありがたい」
