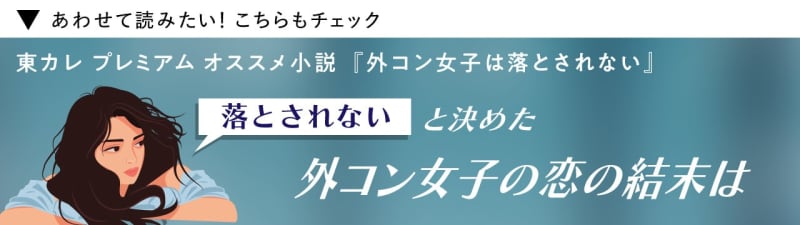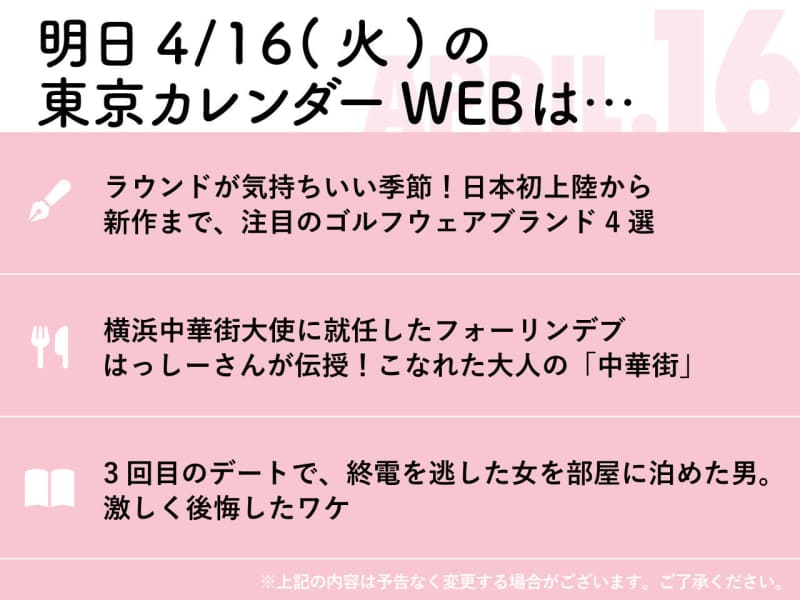◆これまでのあらすじ
人気女性誌のWeb媒体で、コラムの編集をする優斗(34)。怪我によるリモートワークが明けて出社すると、半年前に別れた元恋人・まど香と遭遇する。フリーモデルからライターへと転身することになった彼女の教育を任された優斗は…。
▶前回:新人女性に仕事を教える34歳男。指導中の「ある言葉」が災いし、最悪なムードに…

Vol.7 察して欲しい男と、察するのが苦手な女
編集部の一角、応接スペース。
僕は、向かいの席に座るまど香の頭上に、視線をさまよわせている。
原稿を納品してもらうため、ワードプレスを使った手順を、まど香にレクチャーしていたところだ。
しかし、たった今、こんなことが起きた。
◆
「副編集長…私からもいいでしょうか?」
「…は、はいっ」
重みのあるまど香の声は、暗に「物申したい!」という意思をほのめかしていた。ついさっきまでの和やかな雰囲気が一転、空気がピリつく。
衝立を挟んだとなりの応接スペースからも談笑が消え、サーッと静まり返る。誰もが彼女の次の言葉を待った。
その間…恐らく1分。
1秒ごとに、沈黙が重圧を増していく。
これが漫画だったら、天井近くに「シン…」という文字がでかでかと浮かんでいるに違いない。フォントでいうなら、適度な崩しの中に重厚感のあるHGP行書体がしっくりくる。
僕がこんなことを考えているあいだも、まど香はジッと押し黙っている。
― う~ん、この状況で…言いにくいことって…。やっぱりアレしかないよなぁ。
ふと彼女に視線を戻すと、僕が先に口を開いた。
「あのさ、僕が…何かアウトなこと…いや、不適切なこと…言っちゃったのかい!?」
繊細な話題だからと身構えて、言葉を選んだ結果。逆におかしな語尾になった。
― おいおい…僕、今なんて…?気持ち悪っ!あぁ…。
顔が熱い。きっと、耳まで赤くなっている。
まど香は、まるで不思議な生き物を見るかのように目をみはっている。
そして、ノートパソコンのキーボードのあたりに視線を落とすと、フルフルと肩を震わせ始めた。
― ちょっ、えっ、泣かせ…ちゃった?マズいって、どうしよう…。
「あの、ごめ…」
「…す、すみません…私、耐えられ…ません!」
僕の謝罪の言葉をさえぎると、まど香はクルッと体の向きを変えた。肩だけでなく、背中も上下に震えている。
コントによくあるたらいが落ちてくるシーンそのままに、“ハラスメント”という文字が頭の上にガンッ!と降ってきた。
労働時間の短縮を強いる「ジタハラ」や、リモートワーク中の行きすぎた干渉「リモハラ」、不機嫌な態度で周囲の人に気を使わせる「フキハラ」…。
多様化するハラスメントの数々にうっかり該当してはいないだろうかと、Z世代との接し方に頭を悩ませるX世代、Y世代は多い。
― あ、この区切り方もエイジハラスメント…エイハラなんだっけ?いずれにしても、三橋さん…すみません。僕、またやってしまったみたいです…。
心の中で産休中の前副編集長・三橋さんに謝ると、数ヶ月前の記憶が鮮明に蘇ってきた。

あれはまだ、アウトドア雑誌の編集をしていたときのこと。
後輩の男性社員から、ちょっとした相談を持ちかけられた。
「林さん、カメラマンの臼田さんって怖くないですか?修正依頼しにくいんですよ」
「う~ん、こだわりのある人だからね。だけど、仕事は丁寧で、納期も絶対に守ってくれる信頼できる人だよ」
「…そうですか?素っ気なくて、僕なんか目も合わせてもらえないんですよね」
「あぁ、僕も最初はそうだったなぁ。でもまぁ、そう言わずにさ。コミュニケーションを取って、いい関係性を築いていけば、もっと仕事の依頼もしやすくなるって。僕もフォローするから、連絡してみてよ」
期待を込めて激励したつもりでいたのだけれど、この“頑張って感”がいけなかったらしい。プレッシャーをかけられた、パワハラだ…と報告された後、上司からやんわりと注意を受けた。
正直に言うと、あのやり取りのどこがダメなんだと今でも思う。これじゃあ言葉を選ぶどころでは済まない。選びに選んで厳選しないと何も言えなくなる。
― はぁ…。やりにくいよなぁ。
僕は、ひとりため息を漏らすのだった。

それでもアウトドア雑誌の編集部には、まだどこか体育会系の名残りがあった。
だから、畑違いの女性向けWeb媒体へ異動してきてからは、これまでの何十倍も言動には気をつけてきたつもりだ。
入社当時からお世話になっている三橋さんとは、よくこんな話をした。
「“頑張れ”とか、“もうちょっとやって欲しい”的な気持ちを伝えたいときは…そうねぇ。“いつもよくやってくれてありがとう”から入って、“ここって、こうできる?”みたいな提案に持っていくのはどう?」
「そうですね…はぁ…。ハラスメントの種類って、こんなに多様でしたっけ?仕事を頼むにしても、えらい回りくどい言い方をしなくちゃいけないなんて。難しいな…」
◆
僕は、さまよわせていた目をまど香のほうに戻す。
― 無意識のうちに、まど香にもプレッシャーを与えていたのかな。
三橋さんだったらどうするかを指針に、もう一度、彼女と向き合う覚悟を決めたのだ。
それを察したかのように、彼女もこちらに向き直る。
そして、なぜか思い切り吹き出した。
「ぷっ…あははははっ!うそ、どうしよう…止まらない…ふふふ」
「…何で?何で…笑ってるのっ!?」
「すみ…すみません。だって、林さんが…あ、副編集長が…もうっ!」
まど香は大きく息を吐き、呼吸を整えるとひと言付け足した。
「そういうとこ、全っ然変わってないんですね」
まさか、このタイミングで“そういうとこ”を突きつけられるとは思いもしなかった。
― そう…いうとこって言った?
突然“そういうとこ”に出くわした僕は、口がポカンと開いたまま、言葉だけがどこかへ行ってしまった。
今、まど香に言われて改めて気づいたことがある。
僕の“そういうとこ”は、“変わってない”とセットらしい。
何かしらの欠点があるとわかっていながら向き合うこともしていない。“そういうとこ”の内容が見えないから、直しようもないと開き直っていたのも事実だ。
「ふぅ…。落ち着きました、すみません」
自分の不甲斐なさにがっくりとうなだれる僕を前に、彼女はひとしきり笑ってスッキリした様子だ。
― でも…今なら違和感なく聞けるんじゃないか…?
僕が口を開きかけたときだった。

「副編集長…さっきの続き、いいでしょうか?」
今度はまど香が切り出す。
「あ…あぁ、うん。どうぞ?」
もとはといえば、彼女の話の途中だった。僕は、自分の言葉を引っ込めて聞き役にまわる。
「あの…もっとストレートに言ってもらいたいんです。“ここはこうしたほうがいい”って」
― えっ、パワハラとか…そういうんじゃなかったの?
僕が拍子抜けしているあいだにも、まど香は続ける。
「もちろん、指示の出し方が難しいのはわかります。だけど、私はライターとしてしっかり書けるようになった先に、自分の本を出版したいとか、イベントをやりたいとか…いろいろ考えていて。とにかく、すごくやる気があるんです」
「いや…、うん。わかった…井原さんがそういう気持ちでいてくれるのはすっごく嬉しいよ。ただ…」
「ただ?何でしょうか」
「今ってほら、いろいろ…厳しいところがあるから」
そこに悪意の欠片なんてなかったとしても、相手がハラスメントだと受け取ればそういうことになる。ひとつの言葉が自分の首を絞め、社内での立場を危ういものにするのだ。
― ビビるだろ、普通…。
「それって、相手によるんじゃないですか」
僕の心の声を読んだかのように、彼女がつぶやく。
「相手による…?」
「ハラスメントの類って、明らかにアウト!なものも多いけど…。結局は、相手がどう受け取るかが重要だと思うんです」
そうは言われても、ガイドラインってものがある。僕は言葉を探しながら、まど香の話に耳を傾ける。
「例えば…頑張れって言われると重荷に感じる人がいれば、スイッチが入る人もいる。なら、その人に合わせた言葉をかけるのも時には必要なことなんじゃないかって」
まど香は「そんな簡単な話じゃないかもしれないけれど」と言いながら続ける。
「私みたいなタイプは、はっきり言ってもらった方がいいんです。回りくどい言い方だと、本当に求められているものがわかりません」
「なるほど…」
「いわゆる“察してよ”って、いうのが苦手で…透けて見えると途端に気持ちが萎えてしまうんです」
僕だって、察する能力は高くない。そのくせ、ハラスメントがどうとか言い訳をして、人には察することを押しつけて、安全な場所にいようとしていたのかもしれない。
「“そういうとこ”…副編集長の言葉を選びすぎて、本音が伝わりにくいところ。私が察するのがヘタなところと、しっくりこなかったのかもしれませんね」
「へ…?それって、仕事の…話?」
「えっと、私が言いたいのは…仕事は中途半端にしたくないってことです。言える範囲で厳しめに。よろしくお願いします」
「はい…できる範囲で精進します」
ようやく和やかな雰囲気が戻ってきて、ホッとする。すっかり冷めきったコーヒーカップをテーブルの中央に寄せたまど香は、帰り支度を始めた。
「ごちそうさまでした。お時間を作ってくださり、ありがとうございます」
「こちらこそです。じゃあ井原さん、今週中にあと1本よろしくお願いします」
「あ、あと…さっきは笑ってしまってすみません。ちょっと言い方が面白かったというか。副編集長もあんなふうに慌てることがあるんだなって…。おかげで言いたいことを言えました」
「いや、あの語尾は自分でもなかなか変だと思ったよ」
◆

それから1ヶ月。
彼女が執筆する発酵調味料のレシピは、徐々にPV数が伸びてきている。
試しに人気記事にあるトマト麹を作ってみたら、洋風のスープとよく合って、コクが増してめちゃくちゃ美味しい。
― すごいなぁ、まど香。書くだけじゃなくって、いろいろ読んだり作ったり、勉強してるって言ってたもんな。
彼女からの“そういうとこ”をきっかけに、僕も物事の伝え方について、改めて試行錯誤している。
「ガイドラインは絶対に必要だけど、目の前の相手に合わせることも大事だよな…うん」
この日の仕事を終え、カバンを手に席を立とうとしたときだった。
「林さんっ、よかった…間に合って!はぁ、はぁ…」
走ってきたのか、息を切らせているのは―。
▶前回:新人女性に仕事を教える34歳男。指導中の「ある言葉」が災いし、最悪なムードに…
▶1話目はこちら:早大卒34歳、編集者。歴代彼女に同じセリフで振られ…
▶NEXT:4月22日 月曜更新予定
仕事終わりの優斗のもとへ、走ってやって来たのは…?