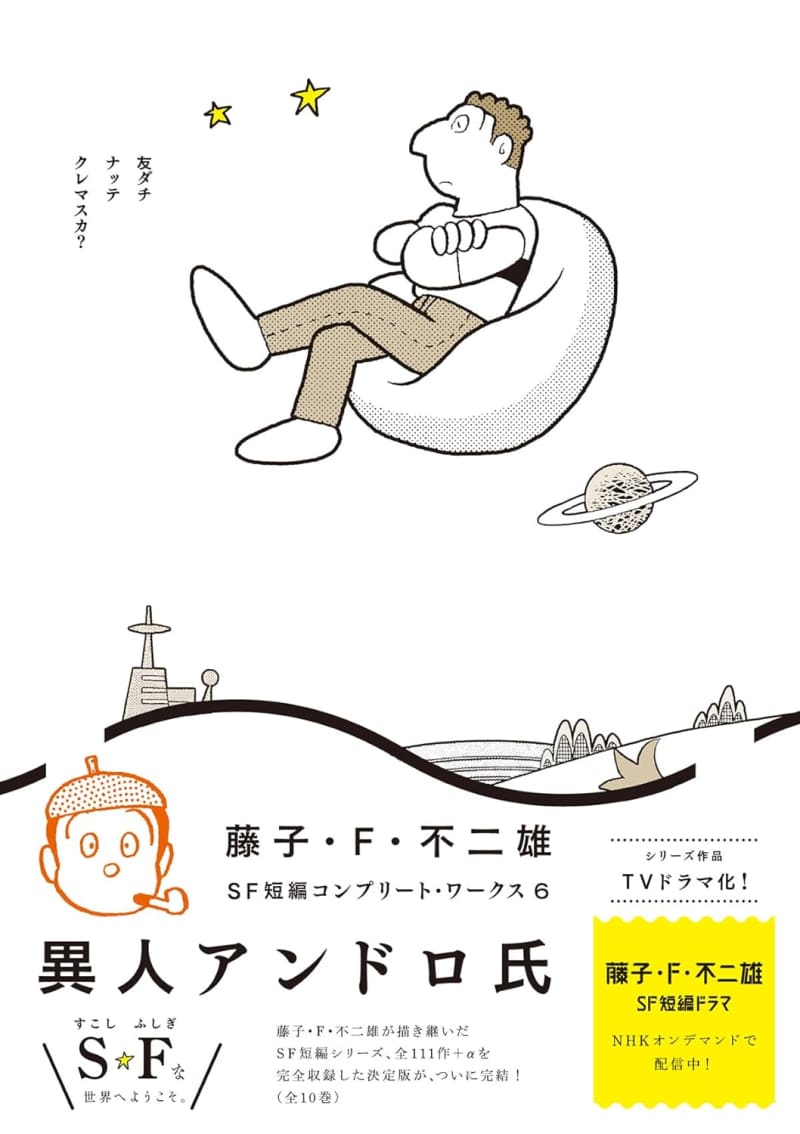
「藤子・F・不二雄SF短編ドラマ」のシーズン2が、NHK BSでスタートした。本日4月14日に放送される第2夜は『マイシェルター』(初出:『月刊スーパーアクション』1983年7月号)。原作は、核戦争の危機が叫ばれるなかで、一介の市民がどのように生き残れるかという問いを、「核シェルター」を通して描いた作品である。
軽く時代状況を整理してみる。本作が発表された1983年は、アメリカとソ連による核軍拡競争がピークを迎えており、世界でおよそ6万発もの核兵器が存在していた(4年後の1987年に約7万発という歴史上最多数を記録し、そののちは米ソ間の条約などによって徐々にその数を減らしていく)。それゆえに、核に対する不安や拒絶の声は、1962年のキューバ危機に並ぶほどの盛り上がりを見せており、同時代の漫画の世界でも、『北斗の拳』(原作:武論尊・作画:原哲夫、1983年連載開始)や『飛ぶ教室』(ひらまつつとむ、1985年連載開始)など、核戦争後の世界を描いた作品は少なくなかった(またこの2作は、じっさいに核シェルターを作中で登場させている)。
藤子・F・不二雄にとっても、「核」は珍しいテーマではない。SF短編を見ると、映画マニアの青年が核戦争の危機をサークル仲間たちに熱弁する『ある日……』や、巨人・ガ壱號が広島・長崎に飛来したB29から原爆を回収し、サンフランシスコとロサンゼルスに投げ込むというウルトラCの展開が炸裂する『超兵器ガ壱號』はとくに記憶に残るものだろう。
『マイシェルター』は、居酒屋での会話からはじまる。おやじさんにマイホーム建設の夢を語り、節約のために酒席を早々に切り上げようとする中年サラリーマンの主人公。するとそこに「あまり飲めないんです」と自分の酒を勧めてくる、ひょろっとした眼鏡の男性。マイホーム購入まではもう一歩という段階に迫り、悩みが解消されそうと語る主人公だが、その予定地を聞いた男性は、「都心に5メガトンの核爆弾が落ちた場合は焼けてしまう」と地図を見せながら主人公に語る。バカバカしいと一笑に付す主人公だが、男性は現在(1983年当時)における核戦争の危機を強調し、核シェルターのパンフレットを主人公に渡す。そして帰宅後、主人公は眠りにつくが……。
パンフレットの説明では(原作では4分の3ページほどを使い、シェルターの見取り図が示される)、シェルターは核戦争やM8の地震にも十分耐えうる強度を持ち、10名までは収容が可能であるという。主人公の家族構成は妻と中学生くらいの息子、小学生くらいの娘の4人で、その点は問題ない。では、シェルターがあることで、「核戦争が起きたけどうちの家族は無事でした。とっぴんぱらりのぷう」となるのだろうか?
『マイシェルター』では、主人公が見る夢と現実の往還が幾度も描かれる。本作における夢は、いわば「もしこうしたら」というシミュレーションの役割を果たしており、それにより核の危機を前にした、主人公の行動や倫理観が試されることとなる。
具体的に説明しよう。まずはシェルターではなく、マイホームを買ったとしてのシミュレーションがあらわれる。新築の家を前に、歓声をあげる一家。しかし、それもつかの間。周囲は核戦争の果実と思わしき炎に包まれ、一家の歓声は悲鳴へと一変する。これが第一の悪夢であるが、夢から覚めたのち、核戦争への懸念を改めて感じた主人公は、セールスマンから渡されたパンフレットに入念に目を通し始める。
そして第二の夢以降は、実際にシェルターを購入したらどうなるかというシミュレーションが、家族とのやり取りを通して表現されることになる。内部を案内したときの家族の反応は? 狭いシェルターのなかでどのように日々を過ごす? 家族以外にシェルターに入れるのだとすれば誰になる? 家族とのやり取りのなかでは、いずれも主人公の行動や言動は家族から好ましい反応を受けることはなく、実生活にシェルターを持ち込むことの難しさが読み取れる。
ただここで立ち止まってもいられないので、家族の理解が得られたとする。そして無事シェルターが購入でき、その後に起きた核戦争で、一次災害(爆風の直撃)は避けられたとする。しかし繰り返すが、それで「とっぴんぱらりのぷう」となるのだろうか?
ここで示唆を与えるのは、『ズッコケ三人組』シリーズで知られる那須正幹の短編小説『The End of the World』である。『マイシェルター』と同時期にあたる、1984年に発表された本作においては、迫りくる核戦争を前に、シェルターに移動した家族3人の「その後」のできごとが描かれる。
地上で核戦争が起き、地下8メートルのシェルターに入ってからおよそ3ヶ月。当初の予測に反して、地上の放射能は一向に減ることなく、そのいっぽうで、シェルターのなかでの生存可能日数のカウントダウンは止まらない。今後の不安に加え、せまいシェルターのなかでのストレスで両親はけんかを繰り返している。やがて身体に異変が起き、死を迎えようとする両親。その原因としては、飲料水が放射能によって汚染されている可能性が語られるが……。
つまり、爆風という核兵器の最初の関門は避けられても、その次には放射能という見えない敵が現れる可能性が示唆される。そして、那須の示す問題は、身体へのダメージという次元のみにはとどまらない。
「シェルターといっても、完璧じゃない。せいぜい二か月くらいの耐久性しか考えてないのかもしれないね。いや、核戦争を起こしておいて、そのうえ生きのころうと考えていたことじたい、まちがっていたのかもしれないな」
これは放射線障害(と明確に名指されるわけではないが、ほぼ確実にそうだろう)によって死を迎えようとしている父親が、息子である「ぼく」に対して口にしたセリフだが、このセリフは前半と後半で、大きく意味が二分される。前半ではシェルターで生き残ろうとすることの物理的な問題が示唆されるが、後半で示唆されるのは、「自分たちだけが生き残っていいのか」という、倫理的な問題である。
『マイシェルター』でも同様に、シェルターの問題は物理的なものから、次第に倫理的なものへとシフトしていく。主人公は最後に、核戦争での爆風で大やけどを負ったシェルター外の人たちを、シャットアウトできるかどうかという問いを突き付けられる。人の生死を決めるボタンを前にした、主人公の決断は……。
家族の説得はできたとする。シェルターに入り、一次災害は避けられたとする。放射能の影響も避けられたとする。シェルター生活でのストレスも不問とする。倫理観は麻痺して何も感じなくなったとする。……しかし、それでもまだまだ、希望にはほど遠い。放射能が消滅してシェルターを出たとして、そこには何が残っているのだろうか? 藤子・F・不二雄の過去作を参照しても、核戦争後の世界は「地球の全表面はキノコ雲に包まれた」(『どことなくなんとなく』)「草一本残らないという状況」(『カンビュセスの籤』)など、もはや人間が住むことが不可能な環境であることが示唆されており、結局、シェルターなどはあくまでも、一時しのぎの手段でしかないことが予期されるのではないか。
では、シェルターが希望の箱舟(言い忘れていたが、セールスマンから紹介されるシェルターには「箱舟」という名前が付けられている)にならないとすれば、人類にはどのような手段が残されているだろうか。おそらく、それは二通りにわけられる。一人ひとりが「反核」という声をあげ、核の危機を未然に阻止するか、もしくは「苦しい時の神頼み」として、人智を超越した存在に助けを求めるかである。
本作のラストでは、この二つの選択肢が、どちらもありうるというような形で示される。未読の読者のために詳細は伏すが、より作中の時代が、人類の終末期に近づいた『カンビュセスの籤』や『宇宙人』では、人類の暮らす世界は、自身たちの努力による改善は不可能な状況にまで追い込まれる。つまり、この二作においては、「神頼み」しかもはや選択肢はなく、主人公たちは一心にそれにすがろうとする。それと比べれば、『マイシェルター』には読後感の苦さはあるとはいえ、まだどこか希望を感じさせる。
とはいえ、本作の発表から40年あまりを経た現在の状況を鑑みると、そうした希望の萌芽を無条件に受容することはできないだろう。ウクライナ戦争やイスラエル・ガザ戦争、また台湾有事への懸念など、ふたたび「核」をめぐる危機はアクチュアルになりつつある。ドラマにはノスタルジックに藤子・F・不二雄の世界を振り返るのみではなく、どのように現在進行形の脅威として「核」に向き合うかという問いへの、今だからこそできるアプローチを期待したい。

