
世界的パーカッショニスト・加藤訓子氏の4月26日に発売される新作『kuniko plays reich ll』のプレス発表&試聴会が4月12日(金)に行われた。
『kuniko plays reich ll』は、加藤氏のLINN Records デビューアルバム『kuniko plays reich』の続編で、ステーヴ・ライヒの往年の名曲から近年の作品を4曲厳選して収録した新作である。

同試聴会では加藤訓子氏のほか、ゲストにオーディオ評論家の山之内 正氏が登場し、モデレーター古川雅紀氏 (株式会社リンジャパン)とともに、アルバムコンセプト、聴きどころなどを語った。


加藤訓子本人たっての希望で、新アルバムの全曲を省略なく聴いた。使用したオーディオシステムは全てLINN。新しいモノラルパワーアンプ「KLIMAX SOLO 800」と昨年から話題のスピーカーシステム「360-PWAB(Passive with Aktiv Bass)」をいう錚々たるラインアップ。
モデレーターを務めた古川雅紀氏は下記のように加藤氏を紹介した。
「加藤訓子さんは、KUNIKOソロ名義で、ひとりで全パートを演奏して多重録音をしています。オーバーダビングしてクオリティをギャランティするにはひとつひとつの音素材のクオリティが高くないと成立しません。加藤訓子さんがLINN Recordsからリリースされたのは2011年、LINNというひとつのオーディオのブランドが運営しているレーベルが録音をしてハイレゾファイルとフィジカルメディアでリリースしました。LINN Recordsもハイレゾリューションがストリーミングに取り組んでいこうとしていた時期だったこともあり、オーディオのフィールドでも話題になりましたが、その後の加藤訓子さんのリリース作品を聴いても、思いつきでやっているのではないことが分かります。そして今回、KUNIKO 名義でLINN Records 7作目の、ライヒ作品3作目の『kuniko plays reich ll』に至りました。」
加藤訓子氏は次のように語った。
「ライヒ作品は海外から演奏家を呼ぶことが多いのですが、日本発のライヒを、ということで演奏してきました。今回は電子オルガンの演奏<フォーオルガンズ>のほか、ヴィヴラフォンによる<ピアノ・フェイズ>、鍵盤打楽器のためのオリジナル作品<ナゴヤ・マリンバ>、<マレット・クァルテット>というやってみたかった曲を多重録音で収録しています。ここまでの経緯で若手プレーヤーとの共演からの発見もあり、私自身納得のいくように取り組みたいと思ったものを勉強し、ひとりコツコツと録音を重ね作り上げていきました。ライヒの1960年代から2000年代まで、時代も作風も異なる、彼の作曲法を追いかけるような4つのラインアップがここに結実しました」
山之内 正氏と加藤訓子氏は1曲1曲に対し聴きどころを解説した。

トラック1 <フォー・オルガンズ>ライヒ1970年作曲
山之内「オルガンとマラカスという、発音原理が異なる楽器で演奏されています。オルガンの音は持続音なので音量が変化しないことが特徴的です。音の立ち上がりだけでなく、音が切れる/消えることでリズム、ビートが生まれます。音の長さが少しずつ変わることで緊張感のあるリズムが生まれ、微妙な変化が生まれていくのが聴きどころです。」
加藤「オルガンの鍵盤を離すと、リズムが生まれます。打楽器で生まれる打点のようになるわけです。ライヴでは若手プレーヤーがオルガンパートを担当しましたが、この録音ではオルガンパートも自分で演奏しました。」
トラック2 <ピアノ・フェイズ>ライヒ1967年作曲/2021年
加藤「ピアノ2台のための曲で、マリンバでも演奏されるヴァージョンがありますが、今回私はヴィヴラフォンで演奏してみました。スティーブにデモを送ったところ、音が短すぎるのでペダルを踏んでほしい、とのこと。ピアノ譜ではスタッカートだったので、短くするものと思い込んでいましたが、スティーヴは、打音したときのはじく音だけでなく、ホールに響く音も含めて音を作りたいと考えていたのかなと思いました。そんな思惑も汲みながら音の響きを瞬時に作りつつ、ひとつひとつのフェイズを作っていきました。その組み合わせで違うパターンが生まれ、展開していくのを聴いてください。」
山之内「ライヒはリズムだけでなくハーモニーも重視していることが分かります。最初の『Kuniko Plays Reich』も感動的でしたが、作曲家本人が大事にしている部分を訓子さんが表現していますね。今日のようなオーディオシステムで聴くと、少しずつ違ったフェイズになっていくのがよく分かります。短い音符が生む緊張感が時間が経つの忘れるくらい面白いです。」
トラック3 <ナゴヤ・マリンバ>
山之内「旋律が日本的ですよね。その特徴的な旋律と動きのあるリズムの組み合わせがききどころです。」
加藤「ライヒ作品は地名がつく曲名が多いんです。<ナゴヤ・マリンバ>はしらかわホールの開館を記念して名古屋由来で作られました。実は、私は同じ愛知県の豊橋の出身なので、名古屋というタイトルを聞くとドキドキしてしまうのです……(笑)。この曲の旋律は日本を意識した音階だと誰もが感じると思いますが、由来は有名なロックのフレーズだそうです。日本音階を畳みかけるように演奏していく、1小節を2回繰り返したら、熟す前に次のパターンに行くという手法です。そのフレーズを分解してみると、ベースとアフタービートが見事に組み合わされています。日本的なみやび、着物などのカラフルな織りが見えてくるようなイメージが、最後は上へと上がっていくように、仕上げたいなと思いました」
トラック4 <マレット・クァルテット>
山之内「2台のマリンバ2台のヴィヴラフォンのクァルテットで、聴きどころとしては旋律がとても豊かなことです。これがスティーヴ・ライヒの作品か、と思うくらいです。時代時代でそれぞれ特徴がありましたが、この曲が最後にこのアルバムのまとめとなっていて、良い選曲だなと思います。」
加藤「シンプルな一小節をひたすら続けて、少しずつシフトしていってひとつの世界観を作り上げるスティーヴ・ライヒの手法が、40年ほどかけて進化していることが、この曲を聴いて分かっていただけると思います。例えば最初からカノンであるとか、最初からディレイがかかっているなどの構成で作られていて、1小節や4小説単位でコード進行していったり、フレーズ間、強弱が複雑に作られています」
プレス発表&試聴会に訪れた者たちは4曲全曲に静かに耳を傾けていた。単調なリズムが繰り返されていたかと思うと、それが少しずつ変わっていき、ひとつのコスモスが作り上げられる。リズムは心臓の鼓動のようでもある。小さな刺激で少しずつ血流に変化が生じる身体のイメージから、銀河の動きのようなダイナミックさにまで昇華していくようだった。3曲目の<ナゴヤ・マリンバ>の色彩感、4曲目の<マレット・クァルテット>のメロディックさなど、ライヒの楽曲は年を追うごとに豊かさを増していた。
モデレーターの古川氏は次のように語った。
「演奏家として冷静でなおかつノリや勢いで弾き飛ばすのではなく、適確にコントロールしてフェーズのシフトを生み出すことに驚かされます。この『kuniko plays reich ll』というアルバムの構成は、スティーヴ・ライヒの時代を追った曲の構成になっていてアルバム全体でひとつの交響曲のようにもになっていると思います。」
加藤訓子は今年2024年、3カ所でライブ・コンサートも予定している。そのプログラムは、この『kuniko plays reich ll』と、昨年、一昨年に若いプレーヤー達とのセッションから作り上げた『Drumming』とで構成された内容だという。アルバムを聴くのみならず、アスリートのように演奏する加藤訓子のライヴ・パフォーマンスもぜひ鑑賞いただきたい。
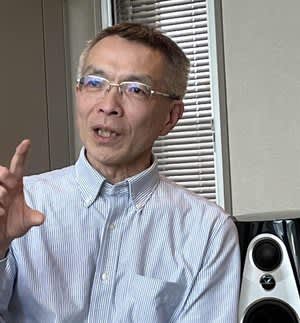
■『kuniko plays reich ll』SACDハイブリッド盤(CKD712)
4月26日 LINN Recordsよりリリース/ナクソス・ジャパンが日本国内販売
収録曲
Four Organs (1970)
Piano Phase ver. for vibraphone (1967/2021 世界初)
Nagoya Marimba (1992)
Mallet Quartet (2009)
■『kuniko plays reich ll DRUMMING LIVE』
6月28日 彩の国さいたま芸術劇場
8月25日 ロームシアター京都
9月13日 愛知県芸術劇場にて
問い合わせ先:芸術文化ワークス事務局 info@npo-artworks.org
演奏プログラム
Four Organs (1970)
Piano Phase ver. for vibraphone (1967/2021)
Nagoya Marimba (1992)
New York Counterpoint(1985)
ーInter Missionー
Dramming(1970ー71)
Part I、II、III、IV

