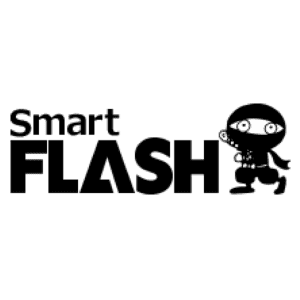「いまでも、誰かの青春の1ページに『会いたい』があることを、とてもうれしく思っています」(澤田知可子)
CDの売り上げ枚数が過去最高を記録し、コンビニや飲食店では有線放送がBGMだった1990年代。僕たちを救ってくれた「名ボーカリスト」のヒット曲誕生秘話!
「この曲はあなたに歌ってほしくない!」
1990年冬、沢田(現・澤田)知可子が4枚めのアルバム『I miss you』のレコーディングをおこなっていた最中のこと。ヒットメーカーとして知られる女性アーティスト・Aが、鬼の形相でスタジオに飛び込んできた。室内は一瞬にして凍りつき、レコーディング作業が止まった。
「岩永ってディレクターはどいつ? 誰?」
トーラスレコード(現・ユニバーサルミュージック)入社3年めのディレクター・岩永浩二は、Aの迫力に気圧されながらも、恐る恐る手をあげた。
Aは岩永の前に立ち、堰を切ったようにまくし立てた。
「冗談じゃないわよ! 私との約束をどうして守ってくれないの? デモテープのままアレンジしてって頼んだでしょう。世界観を変えないでってあれほど言ったのに! 絶対に許さない! この曲はもう歌わせない!」
鳴り響く怒号、平身低頭の岩永。スタジオは修羅場と化した。Aと面識のあるアレンジャーの芳野藤丸(AB’S)が間に入った。
「まぁまぁ、A、もういいだろう」
「岩ちゃん(岩永)も、気にするなよ」
Aの怒りは一向に収まる気配はない。すでに、深夜0時を過ぎていた。Aの言葉の刃は、知可子にも向けられた。
「あなたのせいではないけど、このプロジェクトはおかしい!」
Aの罵詈雑言は40分以上続き、知可子はこの日の夜、急性胃炎になり緊急入院した。
知可子は学生時代からAの音楽が好きで、カラオケでも歌ってきた。デビューして2年と少し経って、ようやくAに新曲を2曲、書き下ろしてもらえる機会に恵まれた。まだヒット曲のない知可子にとって、Aというブランドをまとえるのは、千載一遇のチャンスでもあった。しかも、それらはシングルカットが予定されていた。
岩永はデモテープを受け取る際、Aから指示を受けていた。
「アレンジもしてあるので、このとおりに作ってください」
ギター1本で作られたデモではない。リズムやコード進行、全体的な音の構成がわかる音源だった。Aは楽曲を提供する相手が、どんなに実績のあるシンガーだったとしても、「アレンジの変更は厳禁」というルールを課していた。その不文律を破ったのが、26歳の岩永と、まだヒット曲を持たない知可子だった。Aが怒るのも無理はなかった。
「私があこがれていたAさんを怒らせてしまったという申し訳ない気持ちから、胃に穴が空いてしまいました。Aさんが怒っている姿を見るのも、かなりショックでした。事務所のスタッフも、みんな岩永さんを責めていました。『なんてことをしてくれたんだ!』って。私も同じ気持ちでした。これを境に、人間関係がぐちゃぐちゃになってしまったんです」
岩永には、約束を反故にしてアレンジを変更した理由があった。Aから届いた新曲は、佳曲ではあるが、知可子の次のシングルとしては“弱い”と感じるものだった。それだけではない。そもそも、Aに曲を発注したのは岩永ではなく、知可子の事務所の瀬戸豊香社長だった。岩永と瀬戸、そしてAとの間で、楽曲のイメージの共有ができていなかったことが、問題を大きくした。
その後、話し合いを重ねたが、Aの怒りが収まることはなく、Aが書いた2曲はシングルどころかアルバムにさえ収録されず、お蔵入りになった。数百万円のレコーディング費用が無駄になった。
数日後、知可子は退院したが、レコーディングの期日は残り少なくなっていた。心の傷は残ったまま、アルバムの歌入れ最終日を迎えた。
午後10時過ぎ、スタジオに最後の曲の歌詞が届いた。送り主は作詞家の沢ちひろで、曲のタイトルは『会いたい』。岩永は歌詞をプリントし、「お前、これを読んで泣くなよ」と知可子に手渡した。知可子は歌詞を一瞥して驚愕する。そこには、自身の思い出と重なるエピソードがつづられていた。
「岩永さんにあの話をしたことはなかったのに、どうして知っているの?」
知可子は高校卒業後、埼玉県交通安全協会に就職した。浦和警察署内で、運転免許の更新手続きをおこなう業務を担当していた。
「このままの生活でいいのだろうか?」
そんな思いを抱えながら、同僚の女性たちが集う新年会に参加した。知可子にカラオケの順番が回り、十八番である杏里の『悲しみがとまらない』を歌った。透明感のある伸びやかな歌声は、居合わせた客の心をつかみ、大きな拍手と歓声が上がった。やがて若い男性が知可子に近寄ってきた。
「すみません。来週の成人式で、この曲(『悲しみがとまらない』)を歌ってくれませんか? 僕らのブラスバンドの演奏で」
知可子は快諾し、成人式の舞台で歌を披露した。すると今度は、ジャズミュージシャンから「ウチのバンドでボーカルをやってくれないか」と誘われ、ライブ活動を開始する。知可子は歌手になりたかったわけではなかったが、自然と歌の世界に導かれていった。
22歳。知可子はOLとして働きながら、毎週火曜日、ライブハウス「PotatoHouse」(さいたま市南浦和)で歌っていた。知可子がボーカルを務めるジャズバンドは、杏里の『オリビアを聴きながら』や荒井由実の『卒業写真』などのヒットソングをレパートリーにしていたため、人気があった。
ある日、常連客の女性から問われた。
「あなた、将来の目標はあるの?」
「天職を見つけて転職しようと思っています」
「じゃあ、あなたにとっての天職は何? 思い切って歌で人生、勝負してみなさいよ」
その言葉は、知可子の胸に深く突き刺さった。知可子にはあこがれていた3歳年上の男性がいた。バスケットボール部の先輩で、高校卒業後、実業団でプレーしていた。
「その先輩は練習が終わったあと、私がライブで歌う『オリビアを聴きながら』を聴きたいからと、毎週、ライブハウスに来てくれていました。ライブが終わったあとは、私が彼を自宅まで車で送っていました」
その日も知可子は先輩を横に乗せ、車を走らせながらあの言葉のことを伝えた。
「常連のお客さんから、『歌で勝負しろ』って言われたんです」
「おい、俺がお前のファン第1号だぞ! でも、そう言ってもらえるのは素敵なことだと思う。夢を追いかけるのは尊いことだから、一生懸命がんばれよ!」
知可子は幸福感に満ちていた。尊敬する先輩に背中を押してもらえたことが、何よりうれしかった。
1週間後、その先輩は交通事故で亡くなった。絶望が知可子を支配した。理不尽な運命を呪った。
「いつか絶対、この人のぶんまで私は輝いてやる。夢をかなえて、歌手にならなきゃいけない」
知可子は、沢から届いた『会いたい』の歌詞を手にして驚いた。「バスケット」や、「あなた」が「死んでしまったの」。自らの体験と重なるものだった。そして、偶然の一致だったが、自らの思い出がよみがえり、先輩の笑顔が頭をよぎった。目頭が熱くなり、気持ちが沈んでいく。
「私、人が死んじゃう歌は、歌いたくない……」
歌入れの最終日。ここで知可子が泣いてしまったら、歌入れそのものが難しくなってしまう。そう考えた岩永は、あわてて知可子をマイクの前に立たせた。
「もう時間がないから、仮歌を歌ってみよう」
「うーん、もう1回、練習しとこう」
「はい。お疲れさま。もう録れたから帰っていいよ」
一見、不可解な岩永の発言と行動には意味があった。
「私が亡くなった先輩を思い出して、歌が重くならないように、『仮歌』『練習』と言って歌わせていたんです」
岩永にとって『会いたい』は特別な歌だった。西麻布の交差点近くのカフェで、沢と詞の打ち合わせをした。岩永がコンセプトを説明すると、沢は顔を曇らせた。
「人が死ぬ歌を、私が書くの?」
岩永は自分なりの答えを沢に伝えた。
「人が究極に『会いたい』と心から願うのは、どんなに願っても会えない人。だから、亡くなった人に『会いたい』と願う歌を書いてほしい」
沢と岩永は計38回、歌詞の修正を繰り返して完成させた。曲は岩永が学生のころから敬愛しているチューリップの財津和夫、アレンジは岩永のチームに欠かせない芳野。詞、曲、アレンジ、すべての出来に満足していた。
岩永はレコーディングの最後の作業を終えると、愛車を走らせてお台場へ向かった。夜が明けるころ、海が見える場所に車を停めた。カーステレオに、30分前に完成した『会いたい』のカセットテープを入れた。
「やった! やっとできた!」
この歌は、必ず、大ヒットする――。自信は確信に変わった。
岩永は、会社にあった音源を一度に10本ダビングできる機械を使って、『会いたい』のプロモーション用のカセットを1500本作った。その大半は、自宅近くの団地やマンション、一軒家の郵便受けに、岩永が投函してまわった。
「何を感じたか、感想をください」と手紙を添えた。
だが、反響といえば、会社に「すごく感動しました」というFAXが計3通届いただけだった。それでも岩永は、その3通に勇気をもらった。
知可子はAの怒りを買い、予定していた次のシングルの候補曲を失った。そのため、急遽、アルバムからシングルを切ることになった。すると、さわやかなポップス調の『Live On The Turf』が、日本中央競馬会(JRA)のCMソングに起用されることになった。知可子が当時を振り返る。
「競馬場で7万人の観客の前で歌うイベントも決まって、レコード会社も、この曲で勝負だ! いけるぞ! という雰囲気になりました」
そこに「待った」をかけたのが岩永だった。岩永は、『会いたい』をシングルとしてリリースしたいと提案した。レコード会社の会議で熱弁を振るったが、参加者全員に反対された。Aとのトラブルが表面化したことで、岩永の立場は弱くなっていた。それでも岩永は、折れることなく何度も声を上げた。
「きっと、『会いたい』は沢田知可子の代表曲になります。必ずヒットします。お願いします」
岩永にとって『会いたい』は、絶対に当たる1等の宝くじだった。知可子の未来のためにも、「土下座する勢いで」(知可子)、上役たちに懇願した。岩永は覚悟を決めた。
「この曲を最後に、私は沢田の担当を外れます。さまざまな混乱を招いた責任を取ります。最後のお願いです。『会いたい』をシングルにしてください!」
岩永の熱意が会社の上層部を動かし、『会いたい』をシングルにすべきかどうか、トーラスレコード全社員、約50人による投票がおこなわれた。その結果、シングル化に賛成票を投じたのはわずかに3人。ひとりは岩永本人。もうひとりは宣伝部の男性社員。そして、五十嵐泰弘社長だった。社長の鶴の一声で、シングル化が決まった。
果たして、『会いたい』は8枚めのシングルとして6月27日に発売され、その1カ月後に、JRAのCMソング『Live On The Turf』がリリースされた。ほぼ同時期にアルバム曲が2枚シングルカットされる、異例の事態となった。
柳葉敏郎と賀来千香子が出演するJRAのCMは、話題にこそなったが、知可子の曲はオリコンチャート最高75位に留まった。ノンプロモーションだった『会いたい』も沈黙。2枚のシングルは期待に反して不発に終わった。
「沢田、たいへんなことが起きているぞ!」
1990年9月、プロモーターから自宅に電話がかかってきた。知可子は、「ついに会社との契約が切られるのか?」と首をすくめた。すでに、『会いたい』を発売して3カ月が過ぎていた。
「あのな、『会いたい』が有線放送で40位圏内に入ってきた。これはラストチャンスだ。秋から会社もプロモーションに力を入れていく。落ち込んでないで、希望を持てよ!」
独り歩きを始めた『会いたい』は、有線のリクエストを中心に支持を集め、翌1991年には、全日本有線放送大賞の「最多リクエスト曲賞」を受賞。オリコンチャートも最高6位まで上昇し、130万枚を売り上げた。同年には、念願だった『NHK紅白歌合戦』にも出場した。
岩永の予言は的中し、『会いたい』は知可子の代表曲となり、日本の音楽界のスタンダードナンバーとして歌い継がれている。
「澤田知可子という歌手を育ててくれたのは、岩永さんと沢さんの2人です。いまでも年間50カ所以上、コンサートをさせていただけているのも『会いたい』に出会えたからこそ。いまでも、誰かの青春の1ページにこの歌があることを、とてもうれしく思っています」
さわだちかこ
1963年生まれ 埼玉県出身 1987年『恋人と呼ばせて』でデビュー。2022年、名前の表記を「澤田知可子」に。最新ベストアルバム『うたぐすり~Best Selection』が発売中