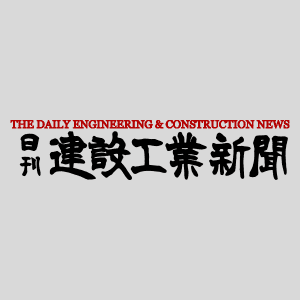◇低調な地籍調査も課題に
能登半島地震の発災から4カ月が過ぎ、被災地では応急復旧からインフラの本復旧、復興まちづくりに向けた取り組みが本格化しつつある。一方で被災家屋の公費解体が思うように進まないなど、課題も顕在化してきた。煩雑な手続きや難航する権利関係の確認など、過疎化が進む地域で個人財産を行政が処分する公費解体の難しさが露呈した。
こうした状況の打開に向け、岸田文雄首相が4月23日に官邸で開いた復旧・復興支援本部の会合で家屋解体を加速するよう関係閣僚に指示。現地で進捗管理などを行う態勢をこれまでの約100班から600班以上に増やし、石川県などと連携し取り組みを強化する。
地震に伴う大規模火災で一帯が焼失した石川県輪島市の観光名所「朝市通り」。大半の家屋が焼け落ちた光景は今も変わらず、損壊した建物の多くが手付かずのまま。被災地の復旧、復興に多くの関係者が懸命に取り組んでいるものの、4カ月余りが過ぎる中、公費解体が進まない被災地では「復旧、復興が進んでいない」といった不満も漏れる。
震災対応に当たってきた同市災害対策本部の広報チーム担当者は「人手不足による苦労が大きい」と振り返る。4月から他自治体の職員を同市職員として併任する中長期派遣職員も加わり、人員を拡充しながら早期の復旧・復興を目指す。
3月1日の発災2カ月で復旧から復興フェーズに変わったと位置付け、坂口茂市長が市民に向けてメッセージを発出した。市民参画型で幅広く意見を吸い上げながら復興まちづくり計画を作成し、今後3年で復興を実現するとの方向性が示された。
「何をどう進めるか、まだまだ見えていないところはあるが、市民の多くは地元に残って働き、暮らし続けたいという思いが強い」と同担当者。生まれ育った輪島市には伝統文化もあり、復興を成し遂げたい--。「みんながそういう思いを持って業務に当たっている」と語気を強める。
石川県が1日発表した人口推計によると、震災で甚大な被害を受けた6市町から他の自治体への転出者が発災3カ月で計2750人に上った。3月だけでほぼ半分を占める。人口流出に歯止めをかけるためにも、具体的な復興の道筋を早急に示す必要がある。
「創造的復興プラン(仮称)」の策定を進める県は、5月下旬までに最終案をまとめる。2年後、5年後、9年後と段階的な復興ビジョンを明示し、次代を担う若者や民間の力も活用しながら、地方の課題解決モデルとなるプランを打ち出す考えだ。
土地の権利の根幹となる地籍が確定していないことは、今後の復旧・復興に大きな影響を及ぼす--。東京大学大学院の布施孝志教授は、地籍調査の進捗率の低い能登半島地域の課題を指摘する。「地籍調査を進めることは当然だが、現時点での情報から、いかに早急に復興につなげるかも測量業の役割だろう」と訴える。