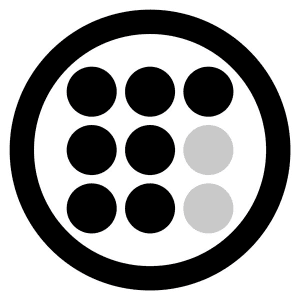野球コーチング論を研究…筑波大・川村卓教授が必ず学生にする“質問”とは
野球界では競技人口の減少が叫ばれるようになり、少年野球でも子ども、そして保護者がチームを“選ぶ”時代になった。怒声・罵声の禁止や保護者会をなくすなど、あの手この手で選手を集めるが……。令和の時代に“選ばれる”チームとはどのようなものなのか。筑波大学体育系教授で、同大学硬式野球部監督を務める川村卓先生は「“コンセプト”が大事です」と語る。
野球コーチング論の研究を行う川村先生は、研究室での学生への指導とともに、毎週1回の「ほしぞら野球教室」を開いたり、大学のある茨城県つくば市の「春日学園少年野球クラブ」に大学院生を派遣したりするなど、育成世代のチームを見つめてきた。指導する学生たちには、必ず次の質問をするという。
「高校野球の監督になったとして、夏の大会で20番目のベンチ入り選手を、すごく頑張ってきた下手くそな3年生にするか、将来確実にレギュラーになる1年生にするか、どちらを選びますか?」
この質問で重要なのは、どちらを選ぶのが正しいかではない。野球チームも多様化していく中、必要なのはチーム理念にブレがないこと。迷わずに、どちらかを選べるコンセプトづくりが大切なのだという。
「正解はないんです。行動を含めて、チーム理念に沿っているかというのを軸にしないと。コンセプトを決め、ブレがなく選ぶんだったら周りも批判しようがありません」

春日学園少年野球クラブは「春日ビジョン」を掲げ人気チームに
実際に、学生を派遣している春日学園少年野球クラブでは、「週末1/4ルール」(土曜、日曜の午前か午後のいずれかを練習に充てる)や「父母会設立なし」「怒声罵声の禁止」といった“春日ビジョン”と呼ばれる理念を掲げ、コーチはその理念のもと指導を行う。
「学生たちにも、『そこのコーチをしているのならば、(チームの)理念に沿って行動をしなさい』と言っています。自分の本意ではない部分があったとしても、コンプライアンスに引っかかるようなものではない限り、チームの理念に沿う指導を、と伝えています」
春日学園少年野球クラブでは、2022年時点でチーム部員は70人を超え、そのうち10人が県外から通う人気チームになっている。「指導のブレがないこともメリット」と話す保護者もいた。
多様な価値観が認められる現代。野球をする理由も、甲子園に出ることやプロ野球選手になることのみではなくなった。昨年のドラフト上位候補だった岩手・花巻東高の佐々木麟太郎内野手が、米スタンフォード大に進学するケースもある。
少年野球では“パパコーチ”が指導を行うチームも多いが、コーチが入れ替わるたびに指導のブレ、方針のズレが起こっていては長くは続かない。「今の時代だからこそ、『チームがどういう風になりたいか』をはっきりさせたほうがいいと思います」。選ばれるチームには必ず“理念”がある。(川村虎大 / Kodai Kawamura)
・練習体験で泣き出した子ども「サインがない」 行動力引き出す“自由以前”の習慣