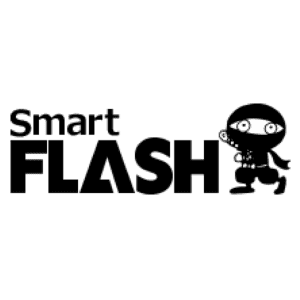「ギャンブル依存症は家族やまわりの人も傷つけた」と話す青木さやか
ドジャースの大谷翔平の元通訳、水原一平被告による違法賭博問題をきっかけに、さまざまな依存症が注目を集めている。
青木さやかは名古屋で過ごしていた20代のころ、友人に誘われてパチンコを始めた。芸人を目指し東京へ出てきてから、その距離がぐっと近くなった。
「名古屋時代は友達と一緒に行って、『勝ったほうが食事おごりね』くらいの遊び感覚で、全然コントロールできていたと思います。それが、東京に出てきたくらいから一人で行くようになって……。そうなると一緒に帰ったり、『もうやめとけよ』と言ってくれたりする人もいなくなりました」
26歳で上京したときには、お笑いの仕事はほとんどなかった。
「当時は、タバコの臭いがついてもいいフリースとかを着て、開店から閉店まで毎日、パチンコを打っていました。昼食は、休憩札をもらって30分間。立ち食い蕎麦を食べて、すぐ席に戻って打ってましたね」
2020年、青木は「婦人公論.jp」の連載エッセイで、若いころにパチンコ店に通った日々について綴った。
《東京に出てきてからも、なかなかパチンコがやめられず、借金がかさんでいった。お願いだからパチンコをやめてくれ、と言っていた、当時の彼氏には「もうやめた」と嘘をつき、バイトに行くと言ってはパチンコに通った》
このエッセイに、読者から大きな反響があった。
「多くの人から、ネット上に『ギャンブル依存症』と書かれていて驚きました。正確には、私が依存症かどうかはわかりません。当時、医師の診断を受けたわけではないからです。ただ、ギャンブルにハマりすぎていた、ということは確かです」
SNSには「自分もパチンコがやめられません」という当事者からの悩みや、家族がギャンブル依存症である人からのメッセージも届いた。
「『あなたみたいな人は許せない』と、すごい剣幕のメッセージがくるんです。戸惑いましたが、ギャンブル依存症は当事者だけでなく、家族やまわりの人も傷つけていることを初めて知りました」
青木のもとには、ギャンブル依存症への啓発活動などのオファーが舞い込んだ。仕事を通して理解を深めると、自身について腑に落ちることが多くあった。
「一日で20万円負ける日もありました。そんなときは『よし、明日取り返そう』と。バイトでは稼ぎが少ないから、ギャンブルに賭けていました。消費者金融さんなどからの借金は、100万円を超えました」
青木がパチンコから距離をおくことができるようになったのは、芸人としてブレイクし、仕事が分刻みで入るようになったからだった。
「とにかくスケジュールを入れることで、パチンコから離れることができました。売れていなかったら、今でもやめられていなかったかもしれません。
今、動物愛護活動に力を入れているのも、どこかで『ギャンブルに意識を向かわせないために』という側面もありますね。パチンコを『やめられた』のではなく、『やめている』という感覚です」
ドジャースの大谷の元通訳・水原容疑者がギャンブル依存症であったことに注目が集まる今、青木は思うことがある。
「ギャンブル依存症から抜け出すきっかけに『底つき』というものがあるそうです。たとえば、自らの行動によって社会的地位や家族を失ったりして『人を傷つけた』と感じたときに初めて、依存症から回復するプログラムに取り組もう、と決意される方が多いといわれます。もしかしたら、底つきを経験するということは、新しい人生を歩むチャンスなのかもしれません」
青木も、パチンコ台と向き合っていたあのころとは “違う人生” を、日々歩んでいる過程なのだ。
●専門医に聞く依存症からの回復
高知東生の主治医を務めた依存症治療の専門家、国立精神・神経医療研究センターの松本俊彦医師に聞いた。
※
依存症の背景には、本人が気づいていない “心の痛み” があります。それは、「自分は無価値だ」「誰からも必要とされていない」「消えたい」という、虚無感や孤独感です。
そんな痛みから意識を逸らすために、あたかも誰かに強いられるかのように、やめられない、止められない行為がエスカレートしていきます。
その結果、他人には言えない “秘密” を抱え込んで、ますます孤独に陥り、対象への依存を深めていくのです。
依存症は、完治することはありませんが、回復することはできる病気です。回復までは、七転び八起きのプロセスです。再発や失敗は、回復に不可欠な要素といってもいい。
それには、安心して失敗を話せる支援者と、非難されない安全な場所が欠かせません。まずは、依存症専門医や、自助グループに繋がることが必要なのです。
取材/文・吉澤恵理(医療ジャーナリスト)
写真・久保貴弘
ヘアメイク・林達朗