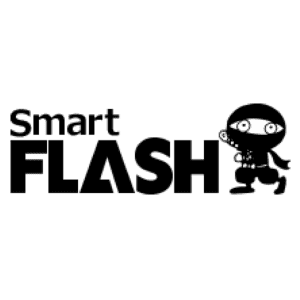「痴漢OKの子がいるんだ!」などと正当化してしまう(漫画・津島隆太氏)
ドジャースの大谷翔平の元通訳、水原一平被告による違法賭博問題をきっかけに、さまざまな依存症が注目を集めている。
津島隆太氏が描いた漫画『セックス依存症になりました。』(集英社)は、主人公の “津島隆太” が、交際相手からバリカンとハンマーで暴行される衝撃のシーンから始まる。
「フィクションですが、僕の実体験をもとにしています。ハンマーで殴られているうちに自尊心が底をついて、1カ月くらい不眠と摂食障害に悩まされました。
その期間、街を歩いていると風の音が女性の喘ぎ声に聞こえたり、路上でセックスが繰り広げられているような幻聴や幻視に襲われるようになったんです」
初体験は18歳。相手は、中学時代から片思いしてきた憧れの女性だった。
「一生尽くそうと思っていたその彼女に裏切られ、一時は自殺も考えました。その後、一種の復讐心から出会い系を始め、数多くの女性と出会い、セックスをするようになりました。自分はデビューもできない漫画家アシスタントでしたが、新しい女性をゲットするときだけは、心の安穏が保たれていたんです」
女性と出会い、オトすまでがゲームのような感覚になっていたという津島氏。本命の彼女、セフレ、ワンナイト……と、1週間でローテーションできないほど多くの女性と交わった時期もあった。セックス自体も過激になっていった。
「彼女を、乱交パーティに連れて行こうとしたこともあります。相手に時間や場所を選ばせず、生理中だろうが公園だろうが、セックスを求めました。ある芸人さんが多目的トイレでしていたことも、僕には理解できる気がします」
セックスに支配された生活に変化があったのは、ハンマーで暴行を受けた40歳のとき。それでも出会い系をやめられず、精神科を受診した。当初の診断は「鬱」。処方された抗鬱剤の副作用で、勃起障害になった。
「なのに、自分の意思とは無関係に、性欲が頭から離れないんです。セックスをできないストレスで、発汗し、呼吸困難になるほどの動悸もありました。医師にそのことを告げると、『セックス依存症かもしれないね』と、トラウマを解消するための心理療法を受けることになったんです」
津島氏に思い当たる過去の記憶はなく、むしろ、それを理由に依存症を正当化することに嫌悪感すらあったという。
「ですが、6カ月のプログラムの1カ月を終えたころ、心理療法で、小学生になる前から父に口淫をさせられていた記憶が蘇ってきたのです。日常的に、目に火花が散るほど殴られてもいました」
虐待を受けて「自分はいらない人間だ」と刷り込まれると、津島氏のようにセックスで女性を過剰に支配しようとしたり、女性の場合は売春に走るケースがあるという。
「その後、医師の紹介で自助グループに参加し、自分の体験を話してきました。ただ、現在は参加していません。漫画を描いている僕がグループにいると、ほかのメンバーに不安を与えてしまいますから」
日本では、津島氏のようにメディアに顔を出して、セックス依存症であることを公表している人はほかにいない。
「芸能人が薬物などで捕まれば、まず依存症が取り沙汰されるのに、わいせつ事件の場合は『変態』で片づけられてしまいます。一方、依存症者の側も、『相手も喜んでいる』『痴漢されて感じている』などと、歪んだ認知を持ち続けている人が多数います。今は、漫画を通じて、セックス依存症について広く知ってもらいたいと思っています」
●専門医に聞く依存症からの回復
高知東生の主治医を務めた依存症治療の専門家、国立精神・神経医療研究センターの松本俊彦医師に聞いた。
※
依存症の背景には、本人が気づいていない “心の痛み” があります。それは、「自分は無価値だ」「誰からも必要とされていない」「消えたい」という、虚無感や孤独感です。
そんな痛みから意識を逸らすために、あたかも誰かに強いられるかのように、やめられない、止められない行為がエスカレートしていきます。
その結果、他人には言えない “秘密” を抱え込んで、ますます孤独に陥り、対象への依存を深めていくのです。
依存症は、完治することはありませんが、回復することはできる病気です。回復までは、七転び八起きのプロセスです。再発や失敗は、回復に不可欠な要素といってもいい。それには、安心して失敗を話せる支援者と、非難されない安全な場所が欠かせません。まずは、依存症専門医や、自助グループにつながることが必要なのです。
取材/文・吉澤恵理(医療ジャーナリスト)