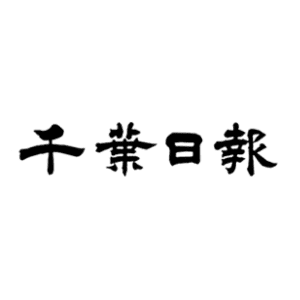「名前を覚えたからな」「SNSでさらす」―。こうした利用者からの不当な要求や行為「カスタマーハラスメント」(カスハラ)が社会問題化し、市民と接することの多い自治体の間でも対策に乗り出す動きが出始めている。近年、小売やサービス業界を中心に従業員の名札や、公共交通機関の運転者の氏名表示をやめる動きが広がっているが、千葉県内でも被害を防ぐため自治体職員の名札を変更するケースが出てきている。(デジタル編集部) フルネーム→名字のみに いすみ市は昨年9月から、市職員の名札をひらがなで名字のみ表記するよう変更した。職員名はこれまで漢字を基本としたフルネームだったが、名札から名前を知られてトラブルになった他県の事例を踏まえた。市総務課は「不安を感じる職員がいるので事前に対処することにした」としている。
市職員であることを明らかにして利用者に安心してもらう目的がある名札だが、一方で名札から名前を知られてトラブルになったケースも少なくない。
職員のプライバシーを保護するため、船橋市では本年度から名字だけに変更。利用者とトラブルになった際に「名前は覚えたからな」「SNSでさらす」などと脅迫を受けた経験のある職員もいるという。千葉県でも4月から、名字のみに変更し顔写真の掲載も取りやめた。新しい名札は所属と名字に加え、名字のふりがなとローマ字表記を追加。同時に視認性が高く読みやすいフォントに切り替えた。 動画投稿繰り返した男性に無許可撮影禁止の判決も 裁判所が「カスハラ」ともいえる行為を禁止する判決を下した例もある。船橋市役所で職員の動画を無断で撮影し、インターネットへの投稿を繰り返した市内の男性に対し、千葉地裁は2020年、市の訴えを認め無許可撮影を禁止する判決を言い渡した。
判決などによると、男性は16年4月~18年12月、庁舎内で職員らを無断で撮影し、動画投稿サイト「ユーチューブ」に「船橋市および千葉県警の実態」などのタイトルで動画65本を投稿。動画内では「おまえらみたいなばかを映す義務がある」などと職員を侮辱する発言を繰り返した。
判決で裁判長は、男性の1回の訪問につき、市が平均2時間半の対応を余儀なくされ、男性と来庁者とのトラブルもあったと指摘。男性は「憲法に保障された知る権利の行使だ」と主張したが、「権利行使として認められる限度を超え、業務に及ぼす支障の程度が著しい」として、市の訴えを認めた。 職員の46%が過去3年間に被害 厚生労働省は昨年9月、うつ病など精神障害の労災認定基準を改正し、カスハラ被害を新たに追加。民間だけでなく、公務員が被害者となるケースもあるため、人事院は今年2月、国家公務員がカスハラを受けた場合、公務災害(労災)と認定できるよう指針を改正した。
全国の自治体で働く職員らでつくる「自治労」が2020年、全国各地の自治体などで働く人を対象にした実態調査では、回答した1万4千人のうち、約46%が過去3年間にカスハラを受けたと答えた。迷惑行為では、「暴言や説教」が約64%、「長時間のクレームや居座り」「複数回に及ぶクレーム」が約60%と目立った。
中には「SNSやネット上での誹謗中傷」「職員や職場の写真の公開」といった行為も挙げられた。カスハラは増加傾向にあるとみられ、被害を受けた職員の約6割は「出勤が憂鬱(ゆううつ)になった」と回答し、休職に至るケースもある。自治労はこうしたカスハラを予防するため、各自治体で措置すべき事項をとりまとめた予防・対応マニュアルを作成している。
県北西部の自治体職員は「利用者から『訴えるからフルネーム教えろ』『お前の顔と名前覚えたからな』と言われることは良くあり、写真を撮られたこともある。名札だけでも名字になれば少しは安心だが、やりとりを録音できるなど安心して仕事ができる体制を整えてほしい」と訴えた。