「私の口、もしかして臭うかも…」そんな悩みを抱えたことがある人、多いのでは?しっかり歯磨きもして歯医者さんにも行っているのに、なぜか臭う気がする。その原因は、もしかしたら食習慣にあるのかもしれません。今回は、口臭専門外来の櫻井直樹歯科医師による著書『口臭を気にする女、気にしない男』(英智舎)から、口臭を防ぐ食習慣について少しだけご紹介します。

実は、驚くほど多くの人が口臭で悩んでいる!
お口の臭い(=口臭)は非常に難しく、デリケートな問題です。よほど親しくない限り、他人はなかなか口臭を指摘してくれません。しかし、それとなく態度で示されたりすると......これはかなりショックです。
「自分との距離を空けられる」「顔をそむけられる」「話をしている時にイヤな顔をされる」......このようなきっかけから口臭が気になり始めたら、毎日がとてもつらいものになってしまうでしょう。
実は、驚くほど多くの日本人が、この口臭の悩みを抱えています。男女1万人を対象にした日本歯科医師会のアンケート(2016年)によれば、自分の口臭が気になった経験が「ある」と答えた人は、なんと全体の8割にもなります。
このように多くの人が悩んでいる口臭ですが、正しい対処方法が広く知られているとは言えません。スマホで「口臭 対策」などと検索すると、専門家から見ればかなり疑問を感じる記事がたくさんヒットします。実践したら、かえって口臭が悪化しそうなものまであるのは本当に困ったものです。
口臭対策で大事なのは予防。生活習慣の改善が重要!
そもそも口臭は症状であり、病気ではありません。原因は別にあります。そしてその原因は大きく分けると、病的要因と生理的要因の2つです。
病的要因であれば、口臭の原因となる病気が存在します。それを治療し、治癒することで、症状である口臭も消えるというわけです。
しかし、その病気が存在しない場合は生理的要因となるため、医師や歯科医師には打つ手がないのです。口臭外来を訪れる患者さんのほとんどは、虫歯や歯周病ではありません。なぜなら、かかりつけの歯科医院でさんざん歯のクリーニングをしてもらっても効果がなく、口臭が気になると訴えても「気のせいです」と言われ、行き場をなくした末に訪れているからです。
口臭を消すために必要なのは、口内殺菌のような治療ではなく、静菌(口腔内細菌叢=口の中に存在するさまざまな菌の集団のバランスを整えること)を軸とした、口臭が出ないようにする予防です。
口臭の原因を取り除く取り組みとは、例えば食事の内容を変えたり、早寝早起きを心がけたりすること。太陽の光を浴び、適度な運動をし、ストレスを溜めないなど、生活習慣の改善です。いわば医師ではなく、患者さんの仕事とも言えるでしょう。
朝ご飯を抜くと口臭が強くなる⁉️
農林水産省の食育に関する調査(2019年)では、ほぼ毎日朝食を取っている人は82.5パーセントと、ほとんどの人が朝食を食べていると報告されています。ただ、20代男性だけを見ると、約3割が食べていないのだそうです。理由は「朝早く起きられない」「朝は食欲がない」というものが半数近くを占めていました。
私は口臭治療を行う際、「生活習慣調査表」と称する表に、1日の飲食生活を1週間分記入し、持参していただいています。それを見ると、朝食を取っている患者さんは3割にも届きません。なかでも男性は朝食を取っている人が少なく、取っていたとしてもパンだけ、コーヒーだけという内容でした。女性もやはり朝食を取っている人は少なく、5割にもなりません。つまり、口臭がある人は朝食を取らない傾向にある、と言えるでしょう。
人は日中、交感神経優位で活動して、夜は副交感神経優位に切り替わり、睡眠・消化吸収を行っています。このシステムを自律神経が受け持ち、交感神経と副交感神経のバランスで調節を行って、内臓や血管などの働きを24時間休まず自動的に調節しています。
このバランスが結構崩れるのです。
朝の交感神経優位への切り替えは食事、運動、光で行われますが、なかでも食事は大事です。もし1日2食にしてしまうと、夜8時に食事したとして昼ご飯まで16時間の空腹時間を乗り越えなければならなくなります。当然、低血糖で頭が働きません。そこで血糖値を無理やり上げるために、アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌されるため、食欲がわかないのです。
朝から食事を取れないのは、常に交感神経優位だからです。これでは自律神経のバランスが崩れ、情緒不安定な状態を引き起こしてしまいます。具体的にはイライラしてキレやすく、不安で何事もネガティブな感情に振り回されることになるのです。
朝の食事には「噛むことで脳への血流を上げる」「血糖値を上げてエネルギーを補給する」という、2つの覚醒効果があります。多くの人は食事が精神的な影響を与えることを知りません。体調はともかく、朝抜いたところで通常通りの動きができるし、昨日と変わらない景色に見えるからです。
しかし、塵も積もれば山となる。毎日の積み重ねがエネルギーの歯車を壊し、不安感情を煽り、口臭を強くしてしまうのです。
本文は『口臭を気にする女、気にしない男』(英智舎)より一部抜粋・編集しています。
画像提供:Adobe Stock
著者メッセージ
『口臭が気なる女、気にしない男』は、大きく分けると口腔、腸内環境、心理の三部構成となっています。この3つの知識がないと口臭治療は成立しないからです。口臭を気している人ほど歯や歯ぐきはピカピカで、口臭測定をしても数値が出ない人がほとんどです。とはいえ、いつも無臭であるわけではなく、時々とんでもない口臭が出ることがあるのです。本書は、そんな口臭のジレンマを解決する一冊です。
書籍紹介
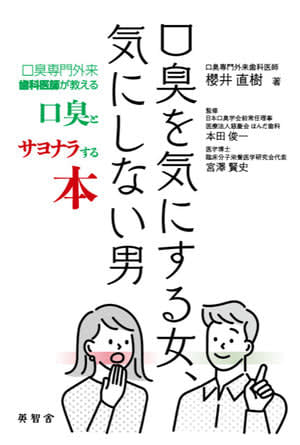
口臭に悩むあなたにお伝えしたいことは次の3つです。
1、口臭は多かれ少なかれ、誰にでもある
2、1日の体調の変化でも、出たり出なかったりする
3、いつも口臭がしているというのは、思い込みである
本書の目的は、口臭をコントロールできるようになることです。
私は歯科医師として、10年以上にわたり口臭外来で、延べ1000人以上の患者さんを診察してきました。その結果、口臭の悩みを解決できる人とできない人の違いは、「正しい知識を知っているか・知らないか」「その知識に基づいた行動をしているか・していないか」の2つだけだと感じています。
この本を読んでもらえれば、口臭を止めるために必要な知識と行動が分かります。
あとはやるかやらないかだけなのです。
著者紹介
櫻井 直樹 (さくらい なおき)
歯科医師、医療法人社団桜樹会 さくら歯科クリニックあおば 理事長。歯科医師として小児から高齢者まで幅広い臨床経験を持ち、30 年で 20 万人以上の治療と指導に関わる。 また口臭外来では、口臭に悩む患者さんに行うカウンセリングが評判を呼び、来院者数は 1000 人を超えている。ほんだ式口臭治療認定歯科医院日本口臭学会会員、歯科医師臨床研修指導医、臨床分子栄養医学研 究会認定指導医、国際顎頭蓋機能学会 FELLOW、日本顎咬合学会認 定医。日本心理学会認定心理士、キャリアコンサルタント、NLP トレーナー。 日本口臭学会前常任理事。医療法人慈慶会ほんだ歯科。 医学博士。臨床分子栄養医学研究会代表。

