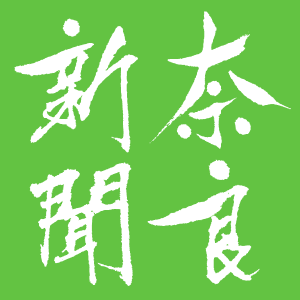古代東アジア最大の「蛇行(だこう)剣」や類例のない盾形銅鏡など、奈良市丸山1丁目の富雄丸山古墳(4世紀後半)から出土した貴重な遺物の保存・展示公開に向け、同市は3月、「(仮称)市文化財センター」の建設基本構想を策定した。整備予定地は市西部、同古墳と道の駅「クロスウェイなかまち」(同市中町、2026年度中開業予定)の近接地で検討。施設が老朽化している市埋蔵文化財調査センター(同市大安寺西2丁目)と市史料保存館(同市脇戸町)を新センターに統合し、2028年度から段階的に共用開始する計画を描いている。
富雄丸山古墳では近年の発掘調査で、蛇行剣や盾形銅鏡をはじめ良好な状態で見つかった木棺など重要な発見が相次いでいる。
基本構想によると、新センターの延べ床面積は6千平方メートル以上、敷地面積は7千平方メートル以上を想定。展示室は、富雄丸山古墳出土品を公開する特別展示室のほか、展示ホールや常設展示室、史料展示室、企画展示室の5室を想定している。
一方、現在の市埋蔵文化財調査センターは1983(昭和58)年に開館し、99年に新館を建設。約40年間の発掘調査で出土した遺物は整理用コンテナ約5万千箱にのぼり、旧館をはじめ敷地内外に設けた収蔵庫も満杯の状態。保存・保管場所の確保が困難となっている。
「奈良町」にある市史料保存館は92年オープン。市内に残る古文書や古絵図などの史資料の収集、調査、保存、展示をしているが、保管点数は約10万点に及びスペースが不足。両施設とも建物や空調機器などの老朽化も課題となっている。
基本構想では、新センターの整備に合わせて両施設の機能を集約する構想を提示。「収集・調査・研究機能」「整理・保存・保管機能」「展示・活用機能」「交流・体験機能」の効率化や高度化を図ることを方針に掲げている。
現時点の事業スケジュールによると、2024年度に基本設計、25年度に実施設計、26~27年度に建設工事を実施。27年度中から移転準備に入り、28年度に一般事務の業務を開始、29年度に収蔵・展示などをスタートする。
市埋蔵文化財調査センターの中島和彦所長は「富雄丸山古墳の超一級資料を管理し継承していける施設にしていきたい。これまで課題だった出土遺物の収蔵体制も整備し、公開して活用していきたい」と話す。
基本構想は市ホームページで公開している。