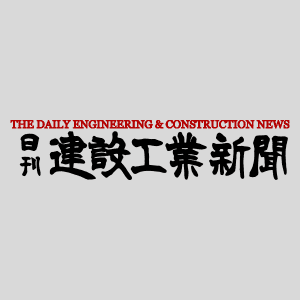◇自然資本拡充に長期的投資、近く閣議決定へ
中央環境審議会(中環審、環境相の諮問機関)は、環境分野を統合する最上位の計画となる「第6次環境基本計画案」(2024~30年度)をまとめた。急激に進む気候変動や生物多様性の損失・汚染といった環境危機の切迫性を強調。危機的状況から脱するため、物質的豊かさの追求に重きを置くこれまでの考え方を見直し、環境や自然資本を軸とした環境・経済・社会の統合的向上への転換を目指す。インフラ整備や土地利用の在り方を巡っても、自然資本の維持や回復、充実を中心に据えたい考えだ。
中環審は伊藤信太郎環境相に9日、計画案を答申した。計画は今月中旬の閣議決定を目指している。
環境基本計画は政府全体の環境の保全に関する総合的で長期的な施策の大綱を定める計画。第1次計画の策定(1994年)から今年で30年の節目を迎える。
環境分野を巡っては、23年に世界や日本の年平均気温が観測史上最高となったほか、人類の活動により生物多様性の損失が加速するなど、深刻な危機に直面している。
第6次計画案では、SDGs(持続可能な開発目標)の概念を表す構造モデル「SDGsのウェディングケーキモデル」の図に象徴されるように、経済社会活動が自然資本(環境)の基盤の上に成立していると指摘。近年顕在化している環境危機のように自然資本を毀損(きそん)すれば、経済社会活動に悪影響を及ぼすとの認識が世界的に定着しつつあると分析した。
こうした背景から第6次計画案では、環境政策を軸に、環境危機への対応と経済・社会的課題の解決を統合的に推し進め、「ウェルビーイング/高い生活の質」を創出する新たな成長の実現を目指す。
第6次計画案は旧来の環境、経済、社会システムの課題を踏まえ、ウェルビーイング/高い生活の質実現に向けた変革の方向性として▽ストック▽長期的視点▽本質的ニーズ▽無形資産・心の豊かさ▽コミュニティー・包摂性▽自立・分散-という六つの重視するポイントを挙げた。
自然資本や、自然資本を維持・回復・充実させる資本を「シン・自然資本」と位置付け、長期的な投資を促していく。50年カーボンニュートラル(CN)をにらみ、地域共生型の再生可能エネルギーの最大限導入に取り組む。洋上風力発電の排他的経済水域(EEZ)への積極展開や、地域の脱炭素化を支援する。公共施設の建築物を活用した再エネの導入や、住宅・建築物のZEHとZEB化も後押しする方針だ。
生物多様性の維持も喫緊の課題となっており、社会資本整備を巡っても生物多様性への配慮が求められる。自然環境の多様な機能を活用するグリーンインフラの整備や、民間投資の促進を通じて緑地を確保するまちづくりDXの取り組みを推し進める。
日本の国土は多様で恵み豊かな自然環境から成り立つ。シン・自然資本の拡充により、国土についてストックとしての価値を高めていく方針も打ち出した。国土の保全や水の涵養(かんよう)などの機能が発揮できるよう自然条件や地域のニーズを踏まえながら森林の整備・保全の取り組みを展開する。
ここ数年の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、強靱な国土づくりを進めるため、自立・分散型の国土構造への転換を目指す。その一環で自立分散・地域共生型の再エネの導入を加速する。
地域の自然資本とされる再エネを地域の自然や社会と調和した形で最大限活用し、エネルギーの地産地消モデルを構築。レジリエンス強化に加え、再エネ関連事業による雇用創出や地域活性化、地域経済循環の拡大の達成を図る。公共施設やインフラで、再エネの導入や省エネ化と防災・減災、国土強靱化対策を推し進め、脱炭素と強靱な国土づくりを統合的に前進させる。
ウェルビーイングや高い生活の質を実感できる都市や地域づくりへ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の取り組みを推進する。自治体が作成する立地適正化計画と地球温暖化対策に関する実行計画の連携を促進。環境課題と人口減少などの経済・社会的課題の同時解決を目指し、持続可能なまちづくりを進める。
福島第1原発事故の被災地で展開する環境再生事業も環境政策の重要な柱の一つだ。放射性物質の除染で生じた除去土壌の最終処分に向けた減容・再生利用の取り組みを国民の理解を得て着実に前進させる。