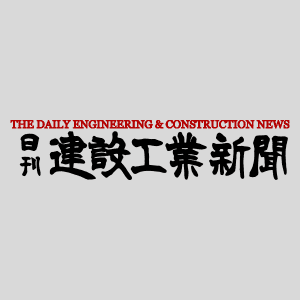能登半島地震の被災地で応急仮設住宅の建設工事が急ピッチで進んでいる。建設主体の石川県が災害協定を締結した8団体に加盟するハウスメーカーや県内外の工務店が設計・施工を担当。8日までに119カ所で計5771戸が着工した。うち恒久的な利用を視野に入れた木造は24%を占める1391戸。全国から建築大工技能者が集結する現場もあり、タイトな日程で早期完成を急ぐ。県は8月中の全体完成を目指しており、市町と連携し新規着工が必要な戸数を今月中にも最終決定したい意向だ。=2面に関連記事
県は復興後の地域のまちづくりも見据え、▽従来型(プレハブ)▽街づくり型(木造・長屋)▽ふるさと回帰型(木造・一戸建て風)-の3タイプで入居希望者に対応。プレハブ建築協会以外の7団体とは発災後に災害協定を締結し、各タイプに応じた供給体制を敷いた。迅速にボリュームを確保できるプレハブが先行する形で、8日までに計3557戸が完成した。
入居期間は原則2年だが、木造の2タイプは市町有住宅への転用などで継続利用を想定した構造・仕様とする。外壁や床材に県産材を活用し、地域の伝統的な住宅に多い「黒瓦」の屋根などで景観との調和を重視する。3月1日に着工した輪島市内の100戸の団地が、木造タイプの初弾として4月末に完成した。
初弾の団地を含む7カ所で計551戸の建設要請を受けた全国木造建設事業協会(全木協、大野年司理事長)は、JBN・全国工務店協会に加盟する元請の工務店に全建総連が建築大工を送り出す労働者供給事業のスキームを活用し工事に当たる。北海道と沖縄県を除く各都府県の組合機関で参画者を募り、11日までに実人数で538人の建築大工が現場に入った。先月中旬の最盛期で1日当たり約300人、現在も約200人が作業に従事する。
輪島市内では各100戸超の団地2カ所が今月下旬の完成に向け工事が追い込みに入っているが、施工管理を手掛ける工務店の現場監督によると技能者の手が足りていない。他地域からのアクセスの難しさなどから人が集まりにくく、短期間の滞在となる技能者も多い。全建総連は「今いる人に少しでも長くいてもらい、新しい人にも少しの日程でもいいから手を挙げてほしい」と呼び掛ける。